


個人向け国債が投資先として注目される中、「今買うべきか」「絶対に買ってはいけない」という議論が過熱しています。
日本の10年物国債利回りが1.3%に上昇し、21年ぶりの高水準を記録する一方、個人向け国債(変動10年、固定5年、固定3年)は低リスクな投資として人気を集めています。
しかし、トランプ政権の関税復活(対中145%、他国10~25%)や米国の高金利政策(4.5%)、円安(1ドル=142円)がもたらすインフレ圧力(消費者物価指数3.5%)が、個人向け国債の魅力とリスクに新たな光を当てています。
一部の専門家は「安全で手軽な投資」と推奨する一方、「絶対に買ってはいけない」と警告する声も根強いです。
→副収入に最適なFXについて漫画付きで楽しく優しく解説
個人向け国債の特徴と現状
個人向け国債は、財務省が発行し、個人投資家向けに設計された債券で、変動10年、固定5年、固定3年の3種類があります。
2025年5月時点の募集条件は、変動10年が基準金利(0.88%)+スプレッド(0.66%)で最低0.05%保証、固定5年が0.48%、固定3年が0.30%です。
元本保証と半年ごとの利息支払い、1年経過後の換金可(中途換金で直近2回分の利息相当額が差し引かれる)が特徴で、銀行や証券会社で1万円から購入可能です。
日銀の利上げ(3月0.5%、6月0.75%予想)と10年物国債利回りの上昇(1.3%)を受け、変動10年の適用利率は0.80%(2024年12月0.50%)に上昇し、投資家需要が増加。
財務省によると、2024年度の個人向け国債発行額は2.5兆円で、前年比20%増となり、50代以上の安定志向層を中心に人気を集めています。
「今買うべき」とする意見
個人向け国債の購入を推奨する声は、その低リスク性とインフレ環境への適応力に基づいています。第一に、元本保証と流動性(1年後の換金可)が、株式や投資信託に比べリスクを大幅に抑えます。
日経平均は4万円台で高値圏にあり、トランプ関税による企業収益圧迫(2025年利益2~3%減予想)が株価下落リスクを高める中、個人向け国債は「安全な逃避先」と評価されます。
第二に、変動10年は市場金利に連動し、2025年の10年物国債利回り上昇(1.3%、6月1.5%予想)が利息増を後押し。
みずほ銀行のファイナンシャルプランナー、山田真由子氏は、「インフレ率3.5%に比べ低利だが、元本保証は家計の守りになる」と指摘。
第三に、円安(1ドル142円)と米国の高金利(4.5%)が外債投資のリスクを高める中、国内資産の安定性が魅力です。
たとえば、米国債(10年物5.0%)は為替リスク(円安で評価損)や関税による価格変動が懸念され、個人向け国債は為替リスクゼロで手軽さが際立ちます。
特に、変動10年はインフレ環境での柔軟性が評価されています。日銀の植田和夫総裁は、6月の金融政策決定会合で0.75%への利上げを示唆し、インフレ目標2%超(3.5%)への対応を重視。
野村證券の佐藤健太郎氏は、「変動10年は金利上昇局面で利息が自動調整され、インフレ対策として実質利回りの目減りを抑えられる」と分析。
2024年の個人向け国債購入者の約60%が変動10年を選び、退職金や貯蓄の一部を安全に運用したい高齢者層に支持されています。
さらに、相続税対策として、個人向け国債は現金より評価額が安定し、贈与契約書なしで子や孫に譲渡可能な点もメリットです。
「絶対に買ってはいけない」という意見の根拠
一方、「絶対に買ってはいけない」と警告する専門家の意見は、個人向け国債の低利回りと経済環境の不確実性に根ざしています。
第一に、変動10年の実質利回りがマイナスである点です。2025年のインフレ率3.5%に対し、変動10年の適用利率0.80%では実質利回りが-2.7%となり、購買力の目減りが避けられません。
経済評論家の山崎元氏は、「インフレが4%に達すれば、10年間で実質価値が25%以上減少。貯蓄の安全神話は幻想」と批判。
第二に、機会費用の高さです。日経平均やS&P500のリターン(過去10年で年率7~10%)に比べ、個人向け国債の利回りは低く、長期投資の観点でリターンが劣後。
楽天証券の田中泰輔氏は、「若年層はインデックスファンドやETFでリスクを取るべき。国債はリスク回避の過剰な代償」と主張しています。
第三に、トランプ関税による経済リスクです。5月30日、米連邦巡回控訴裁判所が関税差し止めを一時停止し、米国債利回りが5.0%に急騰。
日本の国債利回りも1.3%に上昇し、関税による物価上昇(CPI0.6~1.3ポイント増)がインフレを加速させる懸念があります。関税は日本の輸出(米国向け自動車25%減予想)を圧迫し、企業収益悪化が日経平均を下押し。
個人向け国債は株価下落リスクを回避するが、インフレによる実質価値の低下が深刻化する可能性があります。
第四に、日銀の金融政策の不確実性です。日銀が6月に利上げを見送れば、円安進行(1ドル150円予想)が輸入物価(例:米国産米5キロ3000円)を押し上げ、国債の低利回りがさらに不利になります。
UBSのエコノミスト、青木大樹氏は、「金利上昇が急激なら、国債価格の下落リスクも無視できない」と警告しています。
今後の見通し
個人向け国債の投資価値は、今後の経済環境と日銀の金融政策に大きく左右されます。2025年の日本の実質GDP成長率は0.9%(前年1.2%)に鈍化し、トランプ関税による輸出減(18.1%減予想)と円安が成長を抑制。
インフレ率は3.5~4.0%で推移し、米国の関税(対中145%、他国10~25%)が輸入物価を押し上げます。日銀は、6月の利上げ(0.75%予想)でインフレ抑制を図るが、米国債利回り(5.0~5.5%)と連動し、日本の10年物国債利回りは1.5%に達する可能性があります。
ゴールドマン・サックスのアナリスト、トム・ケネディ氏は、「変動10年の利回りは2026年に1.2%まで上昇するが、インフレ率4%超では実質マイナスが続く」と予測。固定5年や3年は金利上昇局面で価格下落リスクが高く、変動10年が相対的に有利とされます。
一方、グローバルな金融市場の動揺も影響します。米国債の安全資産価値後退(10年物5.0%)は、投資家の資産シフト(金やドイツ債へ)を促し、日本の国債市場にも波及。
日銀の国債購入(年間80兆円)は利回り上昇を抑えるが、財政赤字(2024年GDP比6.5%)が国債需給を悪化させるリスクがあります。
シティグループのエコノミスト、村上直樹氏は、「関税の長期化と米国のリセッション確率(45%)が、日本の国債市場に不確実性をもたらす」と指摘。
消費者物価の上昇(例:米価5キロ4285円)が家計を圧迫する中、個人向け国債は安全資産としての需要を維持するが、リターンの低さが課題です。
購入時の注意点
個人向け国債を検討する際、以下の点に注意が必要です。第一に、投資目的の明確化です。元本保証を優先する退職者やリスク回避層には変動10年が適していますが、成長資産を目指す若年層は株式やETFを優先すべきです。
第二に、インフレリスクの考慮。実質利回りがマイナスとなるため、投資額を生活費の30~50%以下に抑え、インフレ連動資産(不動産投資信託など)と組み合わせるのが賢明です。第三に、購入タイミング。
日銀の利上げ局面(6月以降)で変動10年の利回りが上昇する可能性があり、少額分散購入(例:月1万円)がリスクを軽減します。第四に、換金ペナルティの理解。
中途換金は直近2回分の利息が差し引かれるため、1年以内の換金は避け、3年以上の保有を計画。第五に、販売機関の選択。
みずほ銀行や野村證券は手数料無料だが、一部地方銀行は購入手数料(1000円~)がかかるため、事前確認が必要です。
税務面も重要です。個人向け国債の利子は20.315%の源泉分離課税(非課税枠なし)が適用され、NISA口座での購入は不可。相続や贈与では評価額が額面ベースで計算され、税負担が軽減される点はメリットです。
楽天証券のファイナンシャルプランナー、林智子氏は、「変動10年はインフレ対策として有効だが、投資全体の10~20%に抑え、株式や外貨資産でバランスを取るべき」とアドバイス。
関税や円安の不確実性が高いため、最新の経済指標(CPIや日銀会合)を注視し、柔軟な資産配分が求められます。
まとめ
個人向け国債は、元本保証と変動10年の金利連動性が魅力だが、インフレ率3.5%超で実質利回りがマイナスとなり、「絶対に買ってはいけない」との声も。賛成意見は低リスク性と家計防衛を強調し、反対意見は低リターンと機会費用、関税による経済リスクを指摘。
2025年の利回り上昇(1.3~1.5%予想)と円安(1ドル150円の可能性)が投資環境を複雑化し、日銀の利上げや米国の財政不安が影響。購入時は、投資目的の明確化、インフレ対策、分散投資、換金ペナルティの理解、販売機関の選択が重要です。
個人向け国債は安全資産として一定の価値を持つが、過剰な期待は禁物で、経済動向を見極めた慎重な判断が求められます。
→副収入に最適なFXについて漫画付きで楽しく優しく解説
投稿者の人気記事




Floki Inuトークンを紹介~イーロンマスクにインスパイアされて開発~
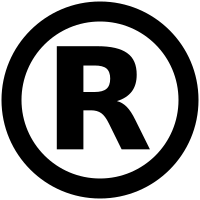
テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

最低賃金の推移2021。

いま頑張って働いている人たちへ【仮想通貨】でカンタン貯金UP!~バイナンスの使い方初心者編~

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

iOS15 配信開始!!

ウッドショック(´°д°`)↯↯

NasdaqがDeFi(分散型金融)関連のインデックスを上場させると聞いたので、構成銘柄を調べてみた

Gamestonk!! 〜ゲームストップ株暴騰の背景〜

オランダ人が語る大麻大国のオランダ
