

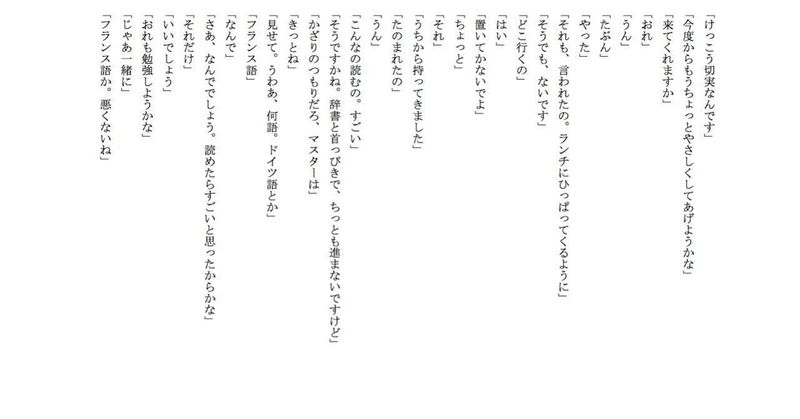
「おれも勉強しようかな」
「じゃあ一緒に」
「フランス語か。悪くないね」
「なんだってできるよ。ひまですよね。この店でむだにした時間を全部つかったら、すごいですよ」
「日本語の本は」
「好きですよ」
「よく読むの」
「そう、小さいころから。なんだか暗い子だった」
「いまは」
「いまは、ふつう」
「ふつうか」
「バイトとか考えられなかったな、むかしは。人にいらっしゃいませ、なんて、言える気がしなかった」
「ちゃんとやってるよ」
「そうかな。分からないですよね、働くって、なんですかね」
「給料もらうことかな」
「体、弱かったんです」
「子供のとき」
「うん。いろんなところが弱かった。ぜんそく持ちだったから、こっちに来たんだ」
「空気がいいから。田舎で」
「そうです。でも、あんまりかわんないかな、田舎も」
「じゃあ意味なかった」
「ぜんそくはなおりましたよ。まあ、精神的なところが大きいのかな」
「そんなに気に入ったの」
「ストレスなんて、ないから」
「ああ」
「でも、本当に、不思議なくらい。そういうことってあるんですね。ちょくちょく入院してたんですけど、こっちに来てからはないです」
「ちょくちょくって、気楽だな」
「入院ってしたことある」
「ない」
「ひまですよ。ここのバイトといい勝負」
「だろうね」
「クラスからお見舞いの言葉とかもらったりして。口をきいたこともない男子から、早く退院してね、なんて」
「それくらいしか書けないんだろう」
「変な気持ちだった」
「千羽鶴とか」
「ああ、もらったことない。自分でつくってたかもしれない。覚えてないけど」
「ほしかった」
「さあ、それも覚えてない。お手紙の返事書かなきゃいけないのか、どうか、それが心配でした。書いたんだっけ。だめだ、なんにも覚えてないや。ああいうの、やめてほしいですよね。誰もしあわせにならないと思う」
「やっぱり本読んでたの」
「そうそう、それで目を悪くしたんだった」
「ふうん」
「本屋さんになりたいって、ずっと言ってたんだって。小学校の文集とかにも、書いてあります」
「いまは」
「いまは、いまは、どうかな」
「あるんだ。ちょっとは」
「おじいちゃんの家が古本屋さんだったから、学校の休みにはよく修行に行きました」
「なにを勉強するの」
「まあ、ずっと本読んでただけですけどね。お客のいない間をぬすんで、すばやくきりのいいところまで本を読む技術かな」
「必要だね」
「少なくとも」
「うん」
「いつまでも、ここでバイトはしてられないですよ」
「なんで」
「だってそうじゃないですか」
「いてよ」
「そうもいかないですよ」
「ずっと、いたらいいよ。そのほうがマスターだって」
「どうしたんです。わがままみたい」
「やめるの」
「やめないですよ」
「じゃあ」
「いつかの話。それは、しかたないことじゃないですか」
「マスターも、いつまでやってるか、分からないからな。いつくじけて、店をほうりだしたっておかしくない。というか、いままで店が残ってるのが奇跡に近い」
「ね」
「おれなら、とっくに見切りをつけてるな」
「居心地がいいんだ。ここ」
「うん」
「本当は、いつまでも、わたしもいたい」
「だいじょうぶだよ」
「寒くないですか」
「いや。そこ、風があたるんだよ。おれはちょうどいい」
「そっか」
「こっち来たら」
「いいんですか」
「どうぞ」
「おとなり失礼します」
「はいはい」
「でも、いいのかなあ」
「なにが」
「なんでもないです」
「いいんだよ。なんだか分からないけど」
「こんないいバイト続けてていいのかって思うんですよ。そういうことないですか。そう、たぶん、わたしもたのしいし、お客さんもおもしろい人と知り合えるし、ずっとここにいたい。それが本音なんでしょうけど、心配なんでしょうね。外に出て、きっと、ここよりいい場所はないんだろうってことが」
「そんなことないよ。いや、そう言うと、さっさとやめていいってことになるけど、ううん。どうだろう」
「どうでしょう」
投稿者の人気記事




SASUKEオーディションに出た時の話

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

京都のきーひん、神戸のこーへん

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

バターをつくってみた

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界
