

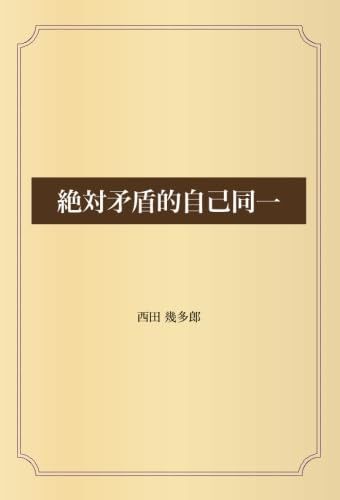
青空文庫にて読了。
最晩年の論文。
ライプニッツの『モナドロジー』を思わせる名刺代わりの一編だが、時節柄大東亜戦争肯定の文脈で読まれたりも。
本邦哲学界の巨人が最後に到達した「一即多、多即一」の実践的・宗教的論理であり、強引にまとめるなら、「絶対に対立するものが自己否定を通じて絶対的に一つになること、それが世界の本当の姿であり、私たちが生きる現実である」。
西田哲学のエッセンスというと聞こえはいいが、決して判りやすい内容ではない。
モナドロジー然り、結局最晩年の総まとめを斜め読みしたところで、思想全体の理解には程遠いのだろう。
弟子の下村寅太郎によるライプニッツ研究を目にし、下村本人に「いま自分に一番近いと思う哲学者はヘーゲルよりもライプニッツだ」と語ったエピソードが示すように、当論文がモナドロジーの影響下にあることは確実なのだが、それにしても判りにくい。
モナドロジーの半分も理解できた気がしない。
亜流ヘーゲル、亜流ライプニッツというか、ただのヘーゲルとライプニッツのいいとこ取りにしか思えない。
獲得ALIS:  66.62 ALIS
66.62 ALIS  11.10 ALIS
11.10 ALIS
新しく新しい騒音z。noteに読書感想や雑記を書いたり、Ableton Liveやら昔持ってた機材で作った楽曲をYouTubeやbandcampにアップしたり、最近はゲーム配信もしてます。
投稿者の人気記事



コメントする
コメントする
こちらもおすすめ!

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜
799.98 ALIS
947.13 ALIS

バターをつくってみた
906.43 ALIS
127.90 ALIS

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】
827.50 ALIS
125.92 ALIS

無料案内所という職業
596.41 ALIS
84.20 ALIS

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】
827.50 ALIS
125.92 ALIS

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。
144.63 ALIS
159.32 ALIS

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界
460.46 ALIS
216.64 ALIS

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた
599.04 ALIS
486.35 ALIS

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして
1.16k ALIS
161.20 ALIS

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話
1.34k ALIS
46.60 ALIS

SASUKEオーディションに出た時の話
494.64 ALIS
35.87 ALIS

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶
1.44k ALIS
38.31 ALIS