

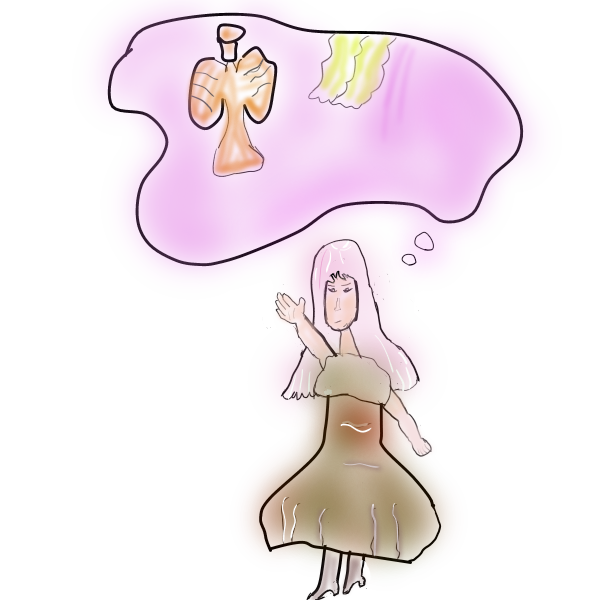
「ああ、神様!哀れな仔羊に何をお求めですか?」
「はああ」
あれ?ああ、夢なの?何か大事なことを偉い人から申し付かったようなのだけれども。
商家の娘は、昨日の出来事に興奮して中々寝付けずにいたが習慣に従って朝早い時間に起きて身づくろいを済ますと店先の掃除を始めた。
昔はかなりの美貌で街の男どもを切なくさせただろう夫人は、食卓でいつもより食欲のない娘を気遣うように、優し気に尋ねた。
「シェーラ、どうしたんだい、昨晩は何だかうなされていたようね?」
「お母さん、どうもしないわ。ちょっと街で魔物同士の争いを見たから怖くなっただけよ」
「なら、いいけど」
母親は娘にあまり五月蠅く構うと嫌がるので、すかさず引いてみた。
「母さん、わたし、どうなっちゃうんだろう?」
「大丈夫よ、心配しないで私がついているから。それに神様がいつも私たちを見守ってくれているから」
「うん、ありがとう」
一方、元クレアパレスにあるグループ杖《ワンド》Kの居城では・・・・・
後ろ手に手錠を掛けられた金髪の女性が呻いていた。
「うう、この屈辱は。こ奴を地獄の業火で永遠に燃やし続けても晴らせやしないのでございます。ああー、身内から滲み出すこの感覚は?なに、何なの?」
「おお、いい感じで吾輩の背中をマッサージできるようになってきたのう。だが、もっと押し付けるがよいぞ、それにその方。まさか感じてきておるのか?ふふっふ」
魔界の貴族であるロノヴェは、アスタロトの術中にはまり、自分より下級の魔族である下種なセーレに隷従させられていた。
そして、今は風呂でセーレの背中を己の胸を使って洗うという屈辱的な奉仕を強制されていた。
「ああ、うっ。胸への刺激が、まさか?この私がこんな下種に感じているのでございますか?うう、惨め過ぎますでございます」
「さて、風呂はもういい。続きはベッドへいって特上のマッサージをしてもらおうか?」
「はい、ご主人様、かしこまりましたでございます」
くぅ、このような恥辱を味わうことになるとは!
Kはアスタロトの魔術で、セーレとロノヴェの痴態を観ていた。
「ところで、アスタロトよ。これに何の意味があるのだ?」
「まあ、黙って見ておれ、あの魔界貴族は屈辱を味わえば味わうほどにその潜在能力が発揮されるのよ。特殊技能と思っていればいいわ」
「うん?それは、もっと強くなるということか」
「そう、単純なあなたにわかるのは、そういう表層の事実だけね」
「おお、なら我が兵力は増強されるわけだな。これで、野望へまた一歩近づくのだ!」
目 次
投稿者の人気記事




無料案内所という職業

機械学習を体験してみよう!(難易度低)

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

バターをつくってみた
