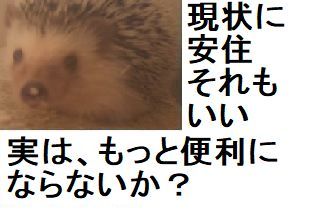


エントロピー増大の法則というのをご存知でしょうか?
熱力学第二法則というのが正しいらしいですが、ここではもっと雑に、汎用化した意味で使います。
物事は放置しておくと乱雑になるという意味合いになります。
元々は宇宙全体の事を考えてヒートデスに行き着いた考えと関連があったと記憶しています。
どういうことか、具体例を挙げて説明します。
水槽に仕切りをいれて、二分割します。
片方にお湯、片方に水を入れます。
そのままでもいいのですが、今回はこの「仕切り」を外します。
一気にお湯と水が混ざり合います。そしてしばらくは上部にお湯が下部に水がある状態でしょうが、数分後には混然一体となって「水槽のぬるま湯」として同じ温度のものになります。
別の例を挙げます。
トランプを買ってきました。封を開けます。順番に並んでいるはずです。
それをシャッフルしましょう。多少ズレる事はあろうとも、おおよそシャッフルすればするほど乱雑になると考えてよいでしょう。ある程度ばらけた後は、たまに偶然順番が整うことがありますが、基本乱雑です。
正確な事、詳細な事を言うと閉じたシステムの中での話とかいろいろと余談はありますが省きます。私自身、エントロピーの知識はこの程度の理解しかありませんので。
重複しますが、自然の中にそのままにしておくと、おおよそ、乱雑になっていくものである、と。
ここではこれが言いたいことです。
しかし、自然の中でもエントロピーが減少する現象があります。
それは、食事であり、生物が何らかの巣を作ったりする行為です。
逆に言えば、私は、生物が生物である所以は、エントロピーを減少させていることだと言えるのかもしれないなぁと思います。
整え、集中させ、作っていることが生きていることと言えるのではないかと。
であれば、ビジネスで「仕組み」を作っていくのはとても生物的で、大げさに言えば「生きている証」何じゃないかなぁ?と思います。
ではでは
私が最初にエントロピーの話を強く記憶にとどめたのは清水義範さんという小説家の方のエッセイです。
----------------------------------------------------------
・かんがえる、かがんでいる人
・Steemit
・Twitter
----------------------------------------------------------
投稿者の人気記事
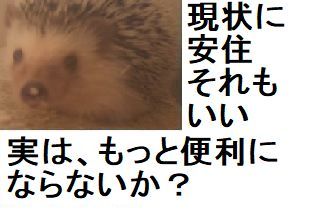
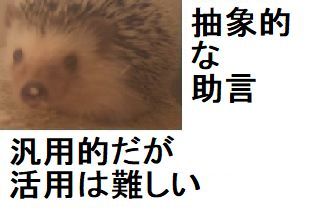
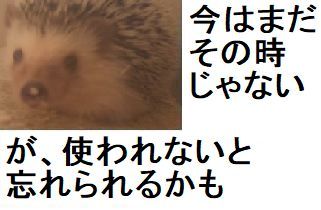

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

Gamestonk!! 〜ゲームストップ株暴騰の背景〜
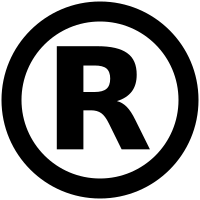
テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる
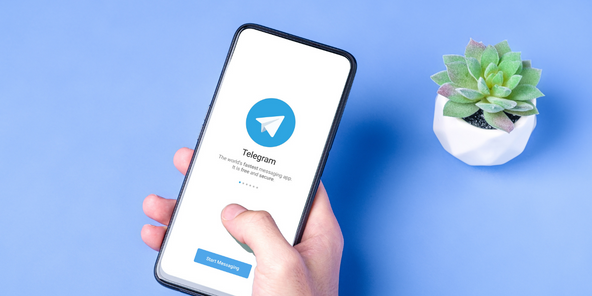
【第8回】あの仮想通貨はいま「テレグラム-TON/Gram」

NasdaqがDeFi(分散型金融)関連のインデックスを上場させると聞いたので、構成銘柄を調べてみた

【最新】Braveブラウザの素晴らしさを語る【オススメ】

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

ウッドショック(´°д°`)↯↯

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

Decentralizationについて語る時に僕の語ること

最低賃金の推移2021。
