

『ミミズと土』
ダーウィンが『人間の由来と性に関する淘汰(The descent of man and selection in relation to sex)』を出版してからも、休むことなく生物に関係する研究を続けました。
特に、食中植物の生態や花の受粉と昆虫の関係を解き明かすことに没頭し、1875年(当時66歳)の『食虫植物』を含めて植物に関する4つの論文を発表しました。
そんな彼の最後の論文は1881年(当時72歳)に仕上げた『ミミズと土(The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms)』です。
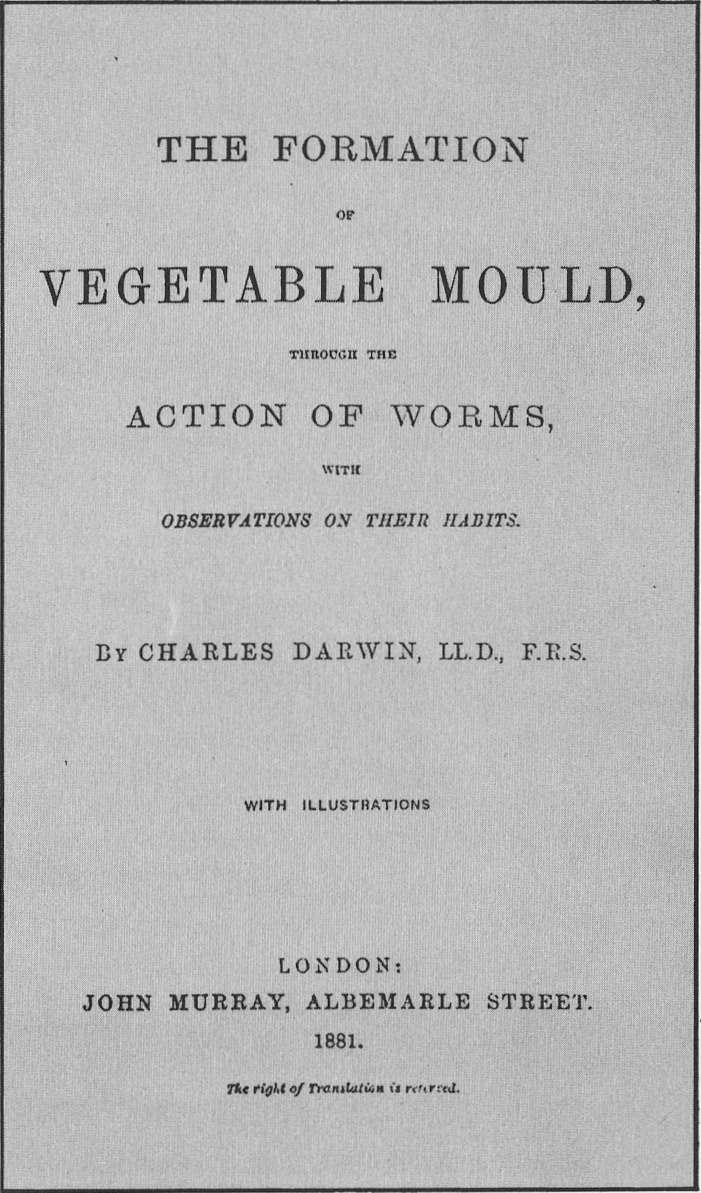
これは、ミミズの生態が土壌に与える影響を、観察と実験によって実証したものです。
ミミズの研究をしようと思ったきっかけは、エマと結婚するよりも前に遡ります。
1837年、ビーグル号の航海から帰って間もない頃、出航を後押ししくれたジョサイア・ウェッジウッド2世がダーウィンにあることを教えてくれました。

「地面に撒いていた石灰や石炭殻が、何もしていないのに地中に消えていく」というものでした。
ジョサイア2世が住んでいたメア邸には牧草地が広がっており、およそ10年前に石灰撒いた所、その層ごと地中に埋まっていったそうです。
それから6年ほど経ってから今度は石炭の燃えかすを撒いたところ、やはりその層も月日が経つにつれて地中に沈んでいったとのこと。
ジョサイア2世は、「ミミズによって土がかき回されることで、地中の土が少しずつ表面に移動したのではないか」と考えました。

これを受けてダーウィンは、「ミミズの活動という小さな現象が、地面全体を動かすほどの大きな結果を生む」というジョスおじさんの考えに強く傾倒しました。
ダーウィンがビーグル号の旅で得た“進化論”も、このミミズの力のように小さな現象の積み重ねだと確信していたからです。
1842年、ジョサイア2世の娘であるエマと結婚した彼は、ロンドンの中心から20キロほど離れたダウン村に引っ越すと、裏庭に見える牧草地に自ら石灰を撒きました。
牧草地には大小の石が見られ、子どもたちはこの様子から「石だらけの原っぱ」と口を揃えて言っていました。
ダーウィンは石灰の変化とともに、この石たちが地中埋まる様子を観察しようとしましたが、その前に寿命が尽きてしまうのではないかと危惧していました。
彼の予想に反し、小さな石は数年のうちに見えなくなり、大きかったものもやがては姿を消していきました。
近くの農民たちもこの現象を経験的に知っていたようで、彼ら曰く「自ら土の下に潜っていく」だそうです。
そんなミミズの力を実感し始めたころ、この研究は一旦棚上げにされます。
『ビーグル号航海記』の執筆をはじめ、フジツボやサンゴ、それに付随する地質の研究、そして『種の起源』についての調査があったからです。
彼が再びミミズの研究に着手したのは1870年代のころになります。
ルーシー・ウェッジウッドの協力
もし、ミミズが大きな石を埋めてしまうほど土を運ぶのだとしたら、一体どれほどの量の土を分解し、地上のものと交換しているのだろう。
ダーウィンはこの疑問を解決すべく、「一年を通してミミズの糞塊を観察してくれる助手」を探しました。
そんな物好きが見つかるのかと思われましたが、間もなく優秀な助手がサポートしてくれることになります。
それはダーウィンの姪にあたるルーシー・ウェッジウッド婦人です。
ルーシーは過去にもダーウィンの研究を手伝っており、定量的な観察ができる人物でした。
彼女は自宅の近くに観察区域を設け、ミミズの糞塊をひたすら集めては保存してくれました。
一年の間に集めた試料は乾燥重量で1m²あたり4kgほどになりました。
年間では4mmほど土の上に積もる計算となり、さらに雨風の助けもあることから、数年の月日のうちに石を埋めてしまうには十分な量でした。
29年越しの実験
1871年、ミミズの研究が進むにつれて、かつて石灰を撒いたダウン村の牧草地が掘り起こされることになりました。
29年越しの結果確認です。
石灰の層は、地表から18cmほどの深さにあり、年間でおよそ6mmずつ土が積もっていったことになります。
ダーウィンは、「古代の建造物や地面に放棄された歴史的遺物などもミミズたちによる耕しよって土に埋もれたことで、腐敗や破損から守られたとし、 考古学者たちは彼ら(ミミズ)に感謝すべきだ」と冗談めかして述べています。
しかし、人間が農耕を始めるはるか以前から土を耕していたのはミミズであり、考古学者でなくとも彼らが行ってきた土壌改良に敬意を表しても良いかもしれませんね。
投稿者の人気記事




Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

無料案内所という職業

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

SASUKEオーディションに出た時の話

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

機械学習を体験してみよう!(難易度低)

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】
