


こいつと最後に目が合ったのは、いつだったかな?
俺は幼馴染の顔を真正面から睨みながら、そんなことを考えていた。
幼馴染——ミキは、右手に持ったスプーンでグラタンを食べながら、左手でスマホを操作している。視線は画面に釘付けだ。グレーのカバーに収まったそれは、ほんのりピンク色に染められたネイルに弾かれて、コツコツと悲鳴をあげているように見えた。
ミキのやっていることは決まっている。SNSで自分の名前を検索しているのだ。エゴサーチというらしい。ミキはいわゆるイラストレーターなのだが、自分の評判が気になるんだとかで、ちょっとでも暇があれば今のようにスマホにかじりついてしまうんだそうだ。
何をそんなに気にしているのか、俺にはわからない。ミキのイラストを見たことがあるが、可愛い感じの絵だったと思う。過激な印象はなかったから敵は作らなそうだし、素人目には「上手」に見えた。ときどきファンレターみたいなものももらっているらしい。なら、好きになんか言ってるやつをわざわざ探さなくたっていいと思うんだが。
今日こうして二人で出かけているのは、ミキのためだった。ミキが、写真を撮りたいから海まで連れてけと俺に言ってきたからだ。だからこうしてわざわざ車を出して飯までおごってやっていると言うのに、合流してからこっちチラとも俺の顔を見やしない。どうなってんだ。
こうやってずっと見つめていても、スマホ越しの瞳には何も届かない。なんだかみじめになってきた。
今度こいつと食事する時はカウンター席にしてもらおうかな。
「やた! いい波!」
海に着くと、さすがのミキでもスマホから目を離した。元気に海辺まで走って行こうとして……すぐにヒョコヒョコとバランスを取りながら戻ってくる。
「歩きにくいー!」
「そんなサンダル履いてくるからだろ」
ここいらの浜は砂ではなく、拳大の石がゴロゴロ転がっている。小さい頃から何度も来ているのだから、ヒールの高い靴は適さないとわかっていたはずだが。|
昔からどっか抜けてるんだよなぁ。
ミキはえっちらおっちらと歩きながらハンドバッグからデジカメを取り出した。ストラップを首にかけながら、バッグを俺に押し付けてくる。
「持ってて!」
「おう」
賢明にもサンダルを脱いで裸足になったミキは、改めて波打ち際に向かった。水平線に向かってカメラを構える。
ここでも、ミキの世界に俺は写っていない。
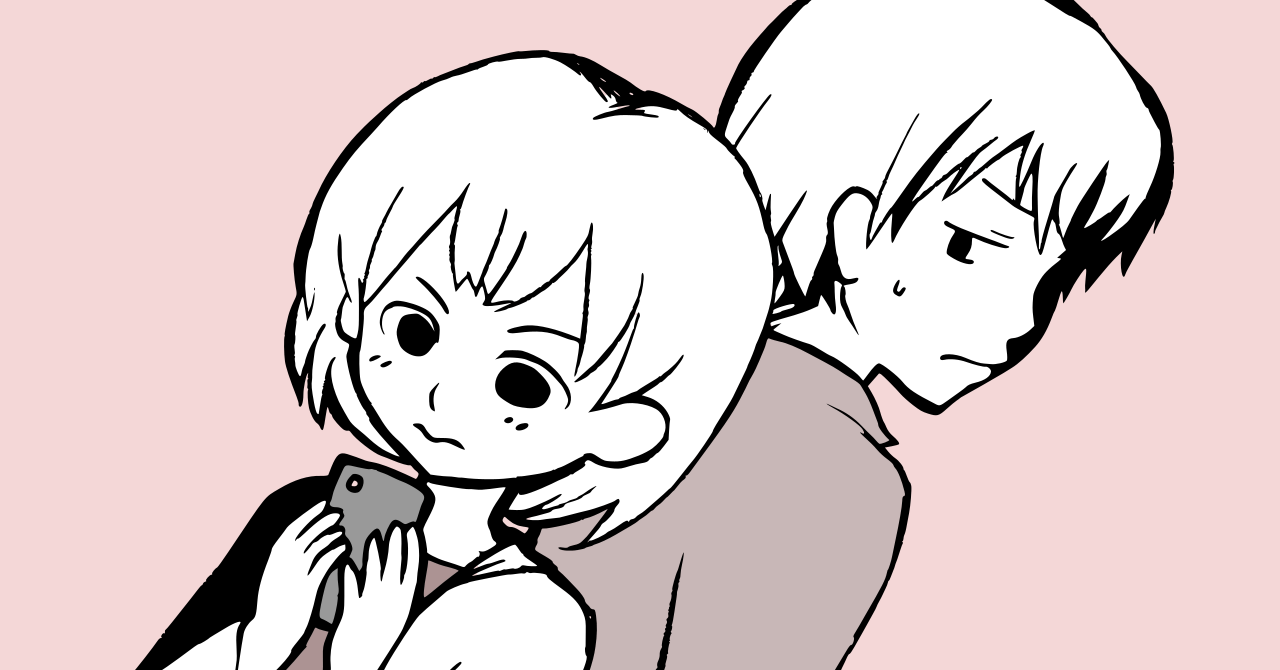
また、こっち見てる。
視線を感じて、ドキドキした。
晴れ渡った青い空に、ほどよい強さの風。写真撮影には絶好の日なのに、なんだか身が入らない。
幼馴染のシンちゃんとはずっと連絡を取り合ってはいたけど、顔を合わせるのは久しぶりだった。ちょっと見ない間に「男の人」になっていた。もうシン「ちゃん」って感じじゃないなと思っていたら、なんと声をかけたらいいのかわからなくなってしまった。なんだか気まずくって、顔が見られなくって……それなのに、シンちゃんはずっと私の顔を睨んでるみたいだ。
なんなの? なんかついてる? 嫌われるようなこと、したっけ?
それにしても、綺麗な空と海。すごくインスタ映えしそうなかんじ。スマホでも写真を撮っておこうかな、と思ったら、しまった。バッグに入れたままだった。
「あー! スマホ忘れた」
ついつい声に出てしまう。
取りに戻ろうかな。でも、何度も戻ってたらシンちゃんに呆れられちゃうかも。私がちょっとの間迷っていたら、背後から声が聞こえてきた。
「投げるぞー」
「え?」
声がした方を見るとシンちゃんが、大きく振りかぶっていた手を、こちらに向かってビュンッと振り下ろしたところだった。
灰色の何かが私の頭上を通り越し、波打ち際から十メートルくらい先の水面に、ぽちゃんと音を立てて落ちた。
「……ああああー!」
私のスマホ!
信じらんない! 先週機種変したばっかりだったのに! ソシャゲのバックアップしてないのに! お気に入りのカバーだったのに!
私はパニックを起こした。無我夢中で波をかき分けてスマホを探す。でも悲しいかな、グレーのカバーは目立たない。水は澄んでいて、大して深くはないのに、それらしいものは目に入ってこない。
シンちゃんの声が聞こえた。ゲラゲラ笑ってる。ひどい! なんてやつ!
「シンちゃんのばか! 一緒に探してよ!」
「ほら、ここだぞ」
「……は?」
信じられない言葉が耳に入ったので、私は中腰の姿勢から立ち上がった。びっしょり濡れた袖が重たい。ロングスカートの裾もぐしょぐしょだ。
シンちゃんは波打ち際に立っていた。右手には、グレーのシリコンカバーにぴったり収まった私のスマホが。
「さっき投げたの石だし。スマホ投げるとは言ってねーし」
ことも無げに言って、ぷくくと笑いを堪えてる。
私は言葉を失った。笑うしかなかった。
「あはははははは」
ゆっくり歩いてシンちゃんに近付く。
「はは! あははは!」
シンちゃんもまた笑い出した。
「ははははははは」
私はシンちゃんの前に立った。波がかかとをくすぐっていく。
シンちゃんは私より頭一つくらい背が高い。見上げたら目が合った。顔立ちは変わったが、小学生の頃から変わらない、いたずらっ子の目をしていた。
左手でシンちゃんの襟首をつかんで引っ張ったら、シンちゃんはびっくりした顔をした。私の右手はパーだ。振り上げる。
笑顔のまま言った。
「ゆるさん」
パァンという小気味いい音が波音に混ざって、消えた。
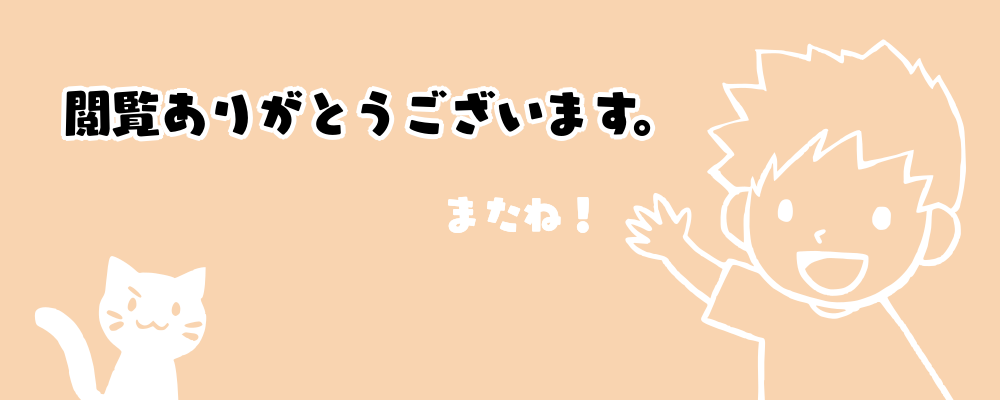
他の小説もいかがですか?
投稿者の人気記事




わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

バターをつくってみた

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

京都のきーひん、神戸のこーへん

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】
