


きいちゃんはカギを持っています。
きいちゃんのカギはなんでも開けることができる魔法のカギです。
ある日、きいちゃんが公園で遊んでいると、見慣れないおじさんがベンチに座っているのが目に入りました。
おじさんはピシッとしたスーツ姿で、膝の上にノートパソコンを乗せてカタカタとキーボードを叩いていました。とても真剣な表情でした。
おじさんはパパよりは年上だけれど、おじいちゃんよりは若そうに見えました。
次の日もその次の日も、見かけるたびにおじさんは同じベンチに座って、同じようにキーボードを叩いています。
きいちゃんは毎日おじさんを見ているうちに、おじさんが何をしているのか知りたいと思うようになりました。そこできいちゃんは、トコトコとベンチに近付いて行ってこう言いました。
「こんにちは。なにをしているの?」
おじさんはパソコンの画面を見たまま、ボソッと返事をしました。
「こんにちは。……仕事だよ」
きいちゃんは更に聞きます。
「どんなお仕事なの?」
「……パソコンを使うお仕事だよ」
「パソコンを使ってなにをするの?」
「……いろいろだよ」
「いろいろってなぁに?」
「……いろいろは、いろいろだよ」
だんだんきいちゃんのお口がへの字に曲がってきました。
「いろいろじゃわからないわ。ねぇ、それを見せて」
「……ダメだよ!」
おじさんは驚いてパソコンを閉じ、顔を上げて初めてきいちゃんの方を見ました。
「お嬢ちゃん、子供はあっちで遊びなさい」
「おじょうちゃんじゃないわ。きいちゃんよ」
「きいちゃん。おじさんの邪魔をしないでくれるかい」
「おじさん、毎日そこでなにかしているしょう? ねぇ、なにをしているのか教えて。
パソコンをちょっとだけ見せてくれたら、もうジャマをしないから」
きいちゃんが足踏みしながらお願いすると、おじさんは困った顔をしましたが、少し考えてからパソコンを横に置き、きいちゃんに向かって開いてあげました。
「ちょっとだけだよ」
「ありがとう!」
きいちゃんはにっこり笑顔になってパソコンをのぞき込みました。けれど画面には、真ん中に錠前の絵が描いてあるだけで他になにも見えません。
「この絵はなぁに?」
「どれどれ……おや、大変だ!」
おじさんがびっくりした顔をして言いました。
「パソコンに鍵がかかってしまった。これじゃあ中が見えないね。さ、あっちで遊んできなさい」
きいちゃんもびっくりしました。
「カギがかかっちゃったの? だいじょうぶ? 開けられる?」
「無理だなぁ。残念だけど、今日はもうお仕事できそうにないからおじさんは帰るよ」
きいちゃんはそれを聞いて得意げににっこりしました。
「カギなら私が開けてあげる!」
そう言うと、おじさんが「え?」と言っている間にパソコンに魔法のカギを差し込み、ガチャリ! と回してしまいました。するとパソコンの画面にできた扉がパカッと開き、中からブワッとたくさんのものが飛び出してきたので、そばにいたきいちゃんとおじさんはひっくり返ってしまいました。
最初に飛び出したのは数字たちでした。その次はひらがなや漢字など、きいちゃんの読めない難しい文字たちがちょうちょのようにひらひらと空に向かって散らばって行きました。
一番多く出てきたのは写真でした。猫やウサギなどたくさんのかわいい動物が写っています。きいちゃんはそれらを一生懸命目で追いました。なにせ、あっという間に視界から消えてしまうものですから。
きいちゃんは写真をひとつひとつ見ているうちに、写真ではない女の子の絵がときどき混ざっていることに気がつきました。
絵の女の子は時には笑っていたり、泣いていたりしていました。男の子と一緒にいる絵もありました。あまり上手ではありませんでしたが、優しい絵でした。
不意に、飛んで行く文字や写真が途切れました。きいちゃんがパソコンの方を見ると、おじさんがパソコンを上から押さえつけてゼェゼェ肩を揺らしていました。
きいちゃんが近づいて行くと、おじさんは両手で顔を覆ってしまいました。
「きいちゃん、見ただろう? 何が見えた?」
「かわいい写真がいっぱい! おじさんが撮ったの?」
「違うよ集めただけ……いや、ええと……」
よくよく見ると、おじさんの耳は真っ赤です。
「ほ、他には何か見た?」
「えーと、女の子の絵があったわよね」
「ああああああ」
おじさんは突然大きな声をあげて、大きな体をもじもじさせました。
「どれもこれも町中に飛んで行ってしまった。もうおしまいだぁ」
「ごめんなさい。集めるのを手伝うから、泣かないで」
「泣いてないよ! ありがたいけど、そういうことじゃないんだよ」
おじさんは両手をおろして、真っ赤になった顔をきいちゃんに向けました。
「飛んで行ったものをきっと町中の人が見るだろう。おじさんがかわいいもの好きで、あんなヘタな絵を描いてるってことをみんなが知るわけだ。ああ恥ずかしい! 忘れてくれたらいいのに!」
「忘れてほしいの? それならみんなの頭から記憶を取り出すことはできるけど……」
「本当かい? ぜひ頼むよ! そうじゃないとおじさんは明日から出歩けないよ!」
きいちゃんはおじさんの様子を見ていて不思議に思いました。
「どうしてそんなに恥ずかしいの?」
「そりゃ、こんなおじさんがかわいいもの集めてたら変だろう?」
「そうかしら」
「おじさんがそういうの好きそうに見えるかい?」
「あんまり」
「そうだろう! イメージと違うと変だ。だから恥ずかしいんだよ」
「うーん、それじゃあ、わたしはどんなものが好きそうに見える?」
「シチューとかだろ?」
「ううん。一番好きなのはね、梅干し! おばあちゃんが作り方を教えてくれたの。これって変なこと?」
おじさんは目をパチクリしました。
「でも、あの絵は? おじさんが描いてたら変だろう?」
「どうして? わたしはあの絵、好きよ」
「そ、そう?」
「ねぇ、女の子が赤い輪っかを持っている絵があったわよね。あれはなんの絵?」
「ああ、あれはね、輪ゴムなんだ。赤い輪ゴム。
きいちゃんは運命の赤い糸って知っているかな? あの女の子は運命の赤い輪ゴムを持っていて、女の子が輪ゴムで二人の指をしばるとね……」
おじさんはそこまで早口で喋ると、ハッとして首をブンブン振りました。
「とまぁ、おじさんはそんなお話を考えているところだったんだ」
「すごい! もっと聞かせて!」
おじさんは照れ臭そうに笑っています。
「みんなもきいちゃんみたいに話を聞いてくれるかな?」
「もちろんよ」
「そうかなぁ。そうかもしれないけど、やっぱりみんなの記憶は取ってくれるかい?」
「どうして?」
おじさんは笑って、不満そうにしているきいちゃんの頭をなでました。
「だって、お話が完成してからびっくりさせたいからさ」
それからきいちゃんとおじさんは町中を歩き回りました。
二人はパソコンから出て行ったものを拾い集めながら、それを見てしまった人みんなにお願いして、魔法のカギで頭を開けさせてもらうと、おじさんのパソコンの中身に関する記憶だけ取り出しました。取り出した記憶は、おじさんが持っていた輪ゴムで丁寧に束ねました。
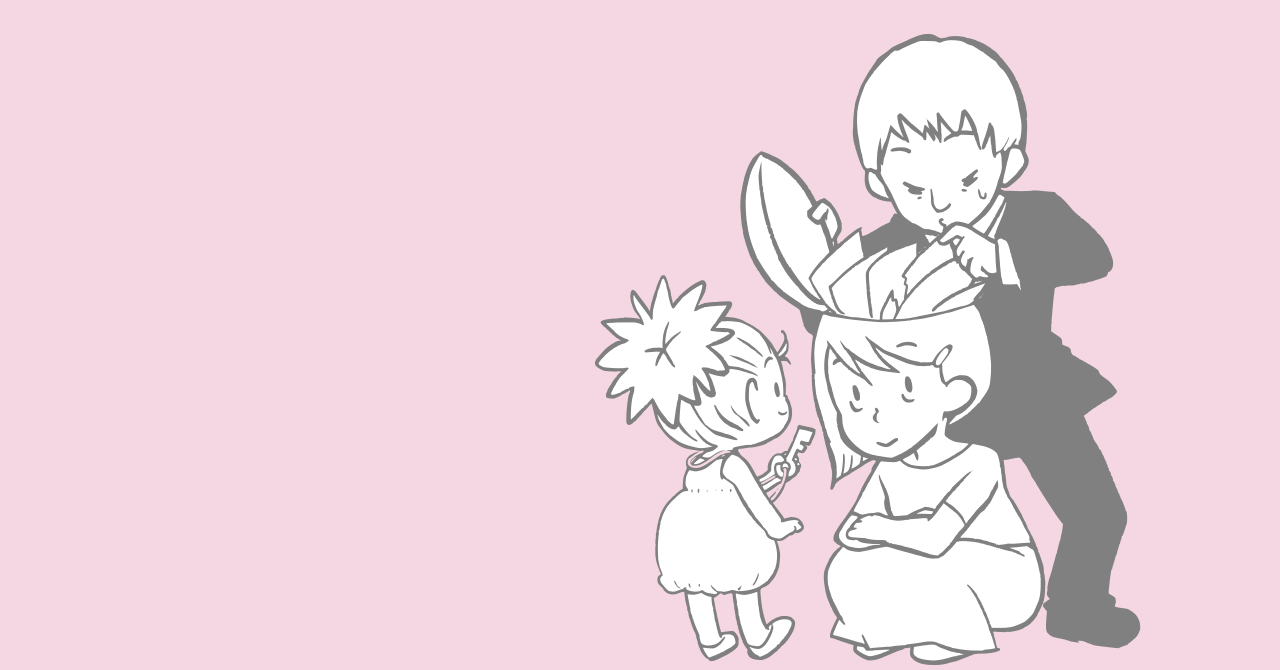
みんなが今日のことを忘れる頃には、きいちゃんはヘトヘトになっていました。おじさんは、お話が出来上がったら最初にきいちゃんに話すと約束して笑顔で帰って行きました。
きいちゃんはおじさんが見えなくなるまで手を振ってから、あなたを見つめて言いました。
「最後はあなたよ。頭を開けてもいいかしら?」
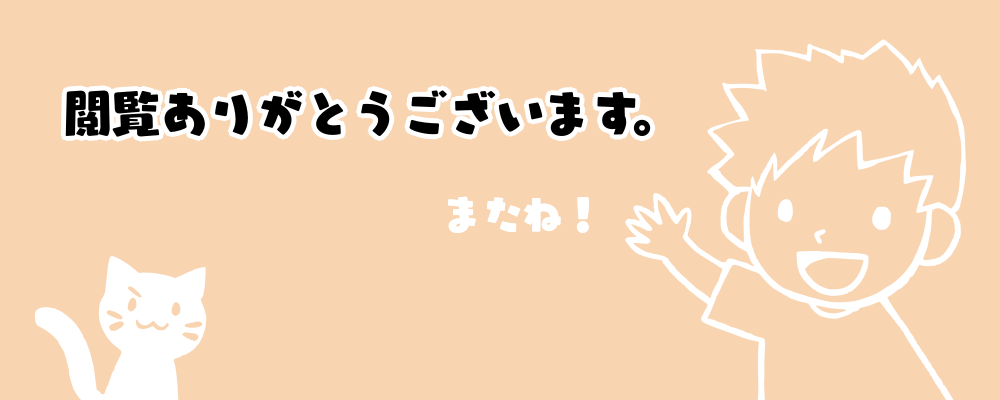
著者のブログ&Twitter
投稿者の人気記事




テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

無料案内所という職業

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

京都のきーひん、神戸のこーへん

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】
