


ある日の夜、ぼうやは真っ暗な部屋で目を覚ましました。
どういうわけか、ちっとも眠くありません。退屈したぼうやはカーテンを開けて窓の外を見てみました。
綺麗なまんまるの月が庭を明るく照らしています。
ぼうやの視界の片隅で草むらが揺れて、ひょこっと茶色い猫が顔を出しました。猫はキョロキョロとあたりを見回すと、ちょいちょいと尻尾を振ってから歩き出しました。すると、その猫に続いて別の猫がまた顔を出しました。猫はどんどん出てきます。
灰色の猫、縞模様の猫、痩せた猫、太った猫……たくさんの猫が一列に並んでぼうやの家の庭を横切って行きました。
「みんなどこに行くんだろう」
気になって見ていると、最後尾にいる小さな黒猫のヒゲが月に照らされて白く光っているのに気が付きました。
「あれ? シロヒゲもいるぞ」
シロヒゲはぼうやの友達の、ヒゲだけ白い黒猫です。
ぼうやはそーっと家を抜け出して、猫たちのあとを追いかけて行きました。
猫たちはぼうやの庭を抜け、横断歩道をいくつも渡って、鬱蒼とした林の中に入って行きました。ぼうやはところどころにあるぬかるみを避けながら、シロヒゲから目を離さないように一生懸命ついて行きました。
ひらけた場所に出ました。誰か人間が捨てて行ったのでしょう、ボロボロの冷蔵庫を中心にいろんな電化製品が山になっていて、てっぺんに真っ白でふわふわの毛並みの猫が座っていました。
集まってきた猫たちはぐるりとその大きな白猫を囲んで輪になりました。ぼうやは木の陰に隠れて彼らを観察することにしました。
白猫が茶色い猫に向かって言いました。
「これで全員だな?」
「へい、揃いやした!」
茶色い猫が元気に答えました。
(わあ、みんなしゃべれるんだ)
ぼうやはシロヒゲとしか話したことがなかったので、わくわくして身を乗り出してしまいました。
白猫が急に振り返り、怖い顔になりました。
「そこにいるやつ、出てこい!」
猫たちが一斉に白猫と同じ方向を見つめました。ぼうやがいる方です。
(うわぁ見つかっちゃった。どうしよう)
ぼうやは恐る恐る木の陰から出て、広場に歩いて行きました。
「人間?」
「人間だ!」
「子供じゃないか」
「なんでここに」
猫たちが口々に言います。
「ぼうや? ぼうやなのかい?」
シロヒゲが驚いた様子でぼうやのそばにやってきました。
「シロヒゲを見かけたから、気になってついてきちゃったの」
ぼうやがしょんぼりした顔で言うと、シロヒゲは「元気出しな」と言うように前足でぼうやの靴をポンポンと叩きました。
「おいシロヒゲ。その子はお前の知り合いか?」
白猫がゴミの山から降りて近づいてきました。
「はい。そうです」
「人間とつるむなとあれほど言ったよな?」
「面目ねぇ」
シロヒゲがしゅんとしています。
「ぼく、ここに来たらいけなかった?」
ぼうやが聞くと、白猫がジロリと睨んで来ました。
「俺たちの集会に人間が混ざるのも、人間に話を聞かれるのも、これまでなかったことだ。お前さんの友達は俺たちの規律を破ったのさ」
白猫の言っていることはぼうやには難しくて、どうやらシロヒゲが叱られているらしいとしかわかりませんでした。
(シロヒゲはぼくと話したことをないしょにしてって、いつも言っていたっけ。この猫さんに怒られちゃうからだったんだ)
「シロヒゲを怒らないで。ぼくとシロヒゲが会ったのはたまたまだったし、今日もぼくが勝手についてきたんだよ。シロヒゲは悪くないんだよ」
「……いい子じゃねぇか」
白猫が前足でシロヒゲをどつくと、小さなシロヒゲはひっくり返ってしまいました。
「とにかくぼうや、今日は大事な集まりなんだ。お前さんは今すぐうちに帰って俺たちとの縁をきっぱり切るか、俺たちの仲間に入るか選ばなきゃならん」
「親分!? 人間を組に入れるんですか?」
様子を見ていた猫がびっくりして言いました。
「口を封じるわけにもいかねぇだろ。そこらのネズミと違うんだぞ。
この子には分別がありそうだから誰彼構わず喋ることはなさそうだがな」
白猫は手振りでぼうやをしゃがませると、顔を近づけて来ました。白猫の顔の真ん中には真っ黒な鼻があり、目つきの鋭い両目は金色でした。
「俺はハナグロって呼ばれてる。こいつらは俺の子分たちだ。
どうする? お前さんも子分になるか? それともお友達と縁を切るか?」
「シロヒゲともうお話しちゃだめってこと?」
「そうだ」
「それはいやだよ。ぼく、ここにいるみんなと友達になりたい」
「そうか。それなら……」
ハナグロは少し目を閉じて考えました。
「今日は満月のまんまる祭りだ。お供え物を用意できたら組に入れてやろう」
シロヒゲがこそこそとぼうやに耳打ちしました。
「前の前の親分が満月みたいにまんまるで、満月の日に死んだってんで、綺麗な満月の日にはみんな集まってまんまるのお供えをすることになったんだ」
「まんまるのお供え?」
「こうやるのさ」
シロヒゲはゲーッと毛玉を吐き出すと、それをちょいちょいと整えて得意げな顔をしました。
ハナグロがそれをちらりと見てため息をつきました。
「お前は相変わらず下手くそだな。こうやるんだ」
ハナグロも同じように毛玉を用意すると、子分たちが歓声をあげました。
「さすが親分。まんまるだ」
しかしぼうやには、どちらもあんまり丸く見えませんでした。
「まんまるだったらなんでもいいの?」
「構わないがな、最初から丸いもんを持ってきても駄目だ。自分で作れなくちゃ認められないぜ」
「まかせて!」
ぼうやは一番近くのぬかるみに近づいて行くと、しゃがんで泥をすくいあげました。
こねこね ギュッギュッ
こねこね ギュッギュッ
ぼうやはあっという間にまんまるい泥団子を作ると、ハナグロの目の前に持って行きました。
猫たちがどよめいています。
「なんだあれ」
「まんまるだ」
「ぼーる?」
「ちょーだい! ちょーだい!」
「ダメよ」
ハナグロは驚いて震えています。
「なんだこれは……こんなに丸いお供え物は見たことがないぞ」
「ぼく、子分になれる?」
「馬鹿野郎! これほどの出来なら頭領にだってなれらあ!」
「えっと、よくわかんないけど、もっと作った方がいい?」
『つくってー!!』
その夜、ぼうやは大小様々な猫たちにせがまれてたくさん泥団子をこしらえました。泥団子を受け取った猫は皆とても嬉しそうに、「まんまる万歳!」と満月の下でくるくると踊りました。シロヒゲも楽しそうに泥団子にじゃれています。
「みんな丸いものが好きなんだね」
「生きてりゃ誰だって丸いものにロマンを感じるもんさ」
ぼうやとハナグロは並んで猫たちの様子を見ていました。
「さてぼうや、俺の子分になったからには色々と組の決まりを守ってもらわにゃならんぞ」
「うん。わかった」
「いい返事だ。よし、じゃあ早速相談なんだが…」
ハナグロはぼうやの耳元でそっと囁きました。
「俺の分も作ってくれないか? とびきり丸いのを頼むぜ」
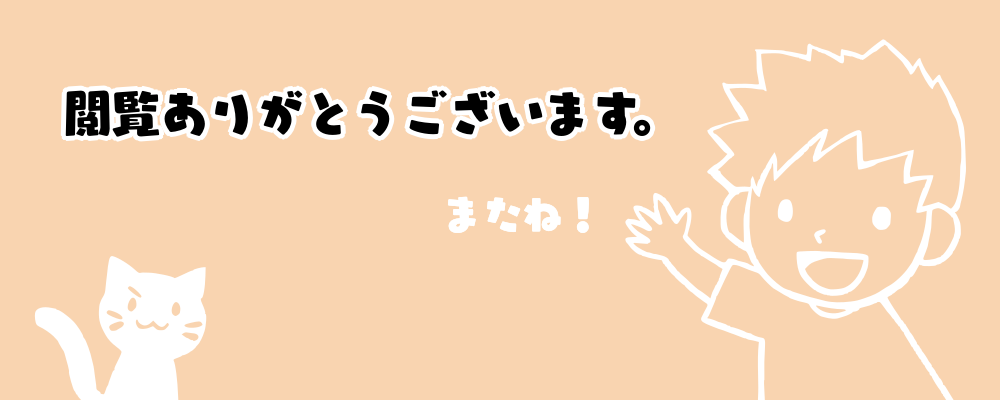
著者のブログ&Twitter
投稿者の人気記事




ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

SASUKEオーディションに出た時の話

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

機械学習を体験してみよう!(難易度低)
