


小さなぼうやと小さな黒猫のシロヒゲは、仲のいい友達です。
ぼうやが庭で遊んでいると、時々ひょっこりシロヒゲがやってきて、のんびりぼうやとお話をしたり、おやつを分けてもらったりして、夕方になるとフラッとまたどこかへ帰って行くのでした。
その日、ぼうやは砂遊びをしていました。
「ヤァぼうや」
「やぁシロヒゲ」
シロヒゲの声が聞こえたので顔を上げると、ぼうやは「おや」と思いました。
シロヒゲの隣に見慣れない猫がいました。すらりと体の長い、灰色の猫でした。
「初めまして、ぼうや。あっしはポッポと呼ばれておりやす。お見知り置きを」
「こんにちは、ポッポ」
ポッポは首をヒョコヒョコ前後に揺らしながら歩いてくると、ぼうやが作り置いていた泥団子を興味深そうに見つめました。
「ハハァ、こいつぁいいシロモノですなぁ。さすがはぼうや」
「ありがとう」
シロヒゲも白いヒゲを揺らしてやってきました。
「やいポッポ。ぼうやが戸惑ってるじゃないか。さっさと要件を言いな」
「おっといけねぇ」
ポッポはぼうやに向き直って腰を下ろしました。
「いやなに、ちょいと、あっしの縄張りで厄介な問題が起きてやしてね。人間の知恵を借りられないかと、このシロヒゲに案内を頼んだんでさぁ」
シロヒゲが隣でウンウンと頷いています。
「問題って?」
ぼうやが聞くと、ポッポは青い目を細めて言いました。
「三日くらい経ちますか。縄張りのあっちこっちで妙な唸り声が聞こえてくるんでさ。ぐおおと、これがたいそう大きい音でね。姿形は見えねぇが、一体どんな化け物かと、すっかりチビすけどもがびびっちまいまして。
兄貴分としては、なんとか正体を突き止めてやりてぇところでして、ぼうやなら何か心当たりがあるんじゃねぇかと思ったんですが、いかがでしょう?」
ぼうやはうーんと唸りました。
「大きい声でうなるオバケ? たくさんいるの?」
「声が聞こえる場所は一箇所や二箇所じゃないんで、何匹かいるんじゃねぇかと睨んでおりやす」
「こわいなぁ。安心して眠れないね」
ぼうやがぶるると震えていると、シロヒゲが思い出したように言いました。
「なぁ、そいつ、夜中は出ないんだろ?」
「あぁそうだ。おおよそ人間が寝るような時間になるとぱったり聞こえなくなって、朝になるとまた唸りだすんだ」
「お昼に出て来て、夜は寝てるのかな? オバケじゃないのかな?」
「さぁそいつはどうでしょう。たんに変わりもんかもしれねぇ」
「寝込みを襲ってやっつけちまおうぜ!」
「落ち着けやい。正体もわからないうちに喧嘩を売るやつがあるかい」
ポッポがちょんとシロヒゲをどつくと、小さなシロヒゲはひっくり返ってしまいました。
「うーん、ちょっとこわいけど、猫のみんなもこわいよね。そのオバケのいそうなところ、見に行っていい?」
「もちろん! 大歓迎でサァ。
あっしは一足先に行って仲間に話を通しておきやすんで、ぼうやはシロヒゲと一緒に後から来ておくんなさい。では」
ポッポは嬉しそうに顔をゆるませると、首を前後にヒョコヒョコ揺らしながら来た道を戻って行きました。
ポッポが見えなくなると、ぼうやはこっそりシロヒゲに耳打ちしました。
「ねぇ、ポッポの歩き方ってさ、ちょっとハトに似ているね?」
シロヒゲはそれを聞いて目をぱちくりさせました。
「そりゃそうさ。だからあいつはポッポなんだ」
ぼうやはシロヒゲとポッポの案内で、町のあちこちを見て回りました。
よくオバケの声がすると言う場所に着くと、地図と赤いペンを取り出してまんまるの印を書き入れました。ポッポから聞いた、猫達の証言をメモすることも忘れません。
五箇所目につくと、ポッポがぼうやだけに聞こえるようにそっと囁きました。
「そろそろ、ここいらで声が聞こえてくる時間です」
そこには人通りの激しい、大きな横断歩道がありました。何十人もの男の人や女の人が、猫を二匹連れて難しい顔をしている小さな男の子を不思議そうに見下ろしながら、ぼうやの横を通り過ぎて行きます。
緊張しているぼうやの耳に、車の音に混じって、ごおおおと低い音が届きました。
ぼうやはびっくりしてあたりを見回しましたが、オバケらしきものの姿は見えません。シロヒゲとポッポも周囲を警戒していましたが、何も見つけられないようです。
数秒経つと、唸り声はぱたりと聞こえなくなりました。
ふと見下ろすと、ポッポがじっとこちらを見つめていました。ポッポはぼうやと目が合うと、しっぽを軽く振ってから歩き出しました。他の人間がたくさんいる場所ではぼうやとお話ができないので「行こう」と合図をしたのでしょう。
ぼうやが歩き出すと、シロヒゲも慌ててついてきました。
ぼうやには一つ気になったことがありました。
(あんなに大きな音がしたのに、大人は誰も気にしてなさそうだったなぁ)
何も見つけられないまま日が暮れてしまったので、ぼうやはポッポと別れて、シロヒゲに家まで送ってもらいました。
「なんかわかりそうかい、ぼうや?」
「うーん、まだわからないよ」
「そうか。
ポッポのやつだって、何がなんでもぼうやに解決してもらおうなんて思ってないさ。楽に構えてていいんだぜ」
シロヒゲはそう言っていたけれど、いまにオバケが姿を現してポッポや子猫達を食べちゃうかもしれない、とぼうやは心配で、いてもたってもいられませんでした。
ぼうやはパパとママにただいまを言った後も、印をたくさん書き込んだ地図を家のあちこちに持ち歩いて離しませんでした。しかし、何回見ても何も思いつきません。
地図をテーブルの上に広げていたら、ママが様子を見にきました。
「さっきからずっと、何を悩んでいるの?」
「ママには言えないの」
ぼうやは眉間にしわを寄せて、真剣な表情です。
「あらそう」
ママはそんなぼうやの様子をとくに気にかけていないかのような顔をして、ぼうやの向かいに座って地図を見下ろしました。
「このあたりの地図だね」
「うん」
「赤い丸はなんの印?」
「ないしょ」
「こっちは文字だよね。なんて書いたの?」
「ないしょ」
「あ、わかった! 新しい駅を見てきたんでしょ」
「えき? なんのこと?」
「違うの? ほら、印の近くにあるでしょ。ここと、こっちも」
「えきって、電車の駅? ここに?」
「そうだよ」
「うそだぁ。線路なんてなかったよ」
その時、ママがテレビを指差しました。画面の中でアナウンサーのお姉さんが地域のニュースを読み上げています。
難しい言葉がたくさんあったので、ママが一つずつ説明してくれました。それを聞いているうちに、ぼうやの顔がみるみる明るくなっていきました。
次の日、シロヒゲとポッポがぼうやを訪ねると、ぼうやはニコニコしていました。
「シロヒゲ、ポッポ、こんにちは。待ってたんだ」
二匹の猫はびっくりして顔を見合わせました。
「こんにちは、ぼうや。何かいいことでもあったんですかい?」
「うん。オバケの正体がわかったよ」
「なんですって」
「いっしょに見に行こうよ」
ぼうやは昨日みんなで見て回った中から公園を選び、地図を指差してポッポに案内を頼みました。シロヒゲはオバケに会えると思って大喜びしています。
公園に着くと、ぼうやはきょろきょろと辺りを見回しながら何かを探し始めました。
「あった!」
それは地面に置かれた四角い金属の柵でした。柵の目は細かく、下は真っ暗な穴が空いていて中がよく見えません。この柵は穴に何か物が落ちないように、穴にはめ込んであるように見えました。
ぼうやは落ち葉を数枚拾ってきて、パラパラと柵の上に置きました。
「なぁぼうや、遊んでないでオバケを探そうぜ」
「違うよ。ちょっとここを見てて」
ぼうや、シロヒゲ、ポッポは柵を囲んで、少しの間じっとしていました。
すると、ごおおおという例の音が聞こえてきて、ぼうやが置いた葉っぱがふわりと宙に舞いました。
「やつだ! この穴から聞こえたぞ!」
「するってぇと、化け物はこの中に?」
シロヒゲとポッポが驚いています。
ぼうやはニッコリして言いました。
「次は直接オバケを見に行こう。あっちの方だよ」
ぼうやが指差している先は、公園のはずれにある茂みでした。茂みの先は下り坂になっているようで、その先がどうなっているか見えません。
ぼうやとシロヒゲが意気揚々と走って行こうとすると、ポッポが鋭い声で呼び止めました。
「ぼうや、行っちゃあいけねぇ」
「なんだいポッポ。物騒な顔しやがって」
ポッポは厳しい表情でぼうやを見つめて言います。
「ぼうや、あんたは利口だが、子供だ。爪も牙もねぇ。その先に化け物がいるってんなら、どうやって身を守るんです?
あっしらを気遣ってくれるのはありがたいが、自分の命と大して知りもしねぇ畜生、ぼうやなら、天秤にかけるまでもなくどっちが大事かわかるでしょう」
シロヒゲはそれを聞いて、しょんぼりと耳を下げました。
「そうだった。ごめんよぼうや。おいら、自分のことで頭がいっぱいだった。ぼうやが怪我するのはいやだよ」
ぼうやは膝をついて、シロヒゲの頭をなでてあげました。
「ありがとうシロヒゲ、ポッポ。
大丈夫だよ。危ないことはなんにもないから。びっくりさせようと思って黙っていたんだけど、実はオバケでもバケモノでもないんだ。
ねぇ、いっしょに行こうよ」
ぼうや達は、ポッポ、ぼうや、シロヒゲの順に並んでゆっくりと茂みの奥に進んで行きました。
やがて背の高いフェンスに突き当たりました。フェンスは横に長く続いていて、向こう側はほんの少しで地面が途切れていました。
「なんだ、行き止まりか?」
シロヒゲがフェンスに顔を押し付けて下の方を見ようとした時、また例の音が聞こえてきました。そして視線の先に何か大きいものが、ものすごい速さで姿を現しました。ゴオオオと、昨日から聞いていた中で一番大きい音がしました。
それはぼうや達の足元から出てきて、フェンスの向こうの方角に一直線に進み、少し先のトンネルの中に入っていきました。
その長い胴体がトンネルに全て吸い込まれて何も見えなくなって、大きな音が遠ざかると、気を取り直したポッポがぼうやを見上げて言いました。
「今のはデンシャってやつですね?」
「うん。そうだよ」
ぼうやはポッポとシロヒゲを交互に見つめながら、昨日ママに教えてもらったことを話し始めました。
「あれは地下鉄って言って、地面の下を走る電車なんだ。ときどき今みたいにちょっとだけトンネルから出てくることはあるけど、そうじゃない時はずっと、見えないところを走っているんだよ。
さっき穴を見たでしょう? あれはツウキコウって言って、地下鉄が通るトンネルとつながっているんだって。トンネルの中の空気が無くなっちゃわないように、たくさん穴をあけてあるんだって」
「なるほど、あっしらが聞いてたのは、デンシャの音だったんですね?」
「うん。電車がツウキコウの近くを通った時に、音が出てきてたんだね」
「葉っぱが動いたのはどうしてだい?」
「電車って、走っている時に大きな風を吹かせるんだよ。それも出てきてたんだと思う」
「なーんだ、バケモノじゃなかったのかぁ」
シロヒゲはごろんとその場に横になってしまいました。
「こら、態度が悪ぃぞ。
しかし、声——いや、音ですか。ここ最近になるまで聞こえなかったってのが、解せねぇんですが」
「えっとね、地下鉄、カイツウしたばっかりなんだ。駅が新しくできたんだって。ニュースでやってたよ」
「なるほどねぇ。いやはや、あっしらだけじゃ思いつきもしなかったでしょう。
いやぁぼうやのおかげで助かりました。さすが親分に一目置かれるだけある」
ポッポがやっと笑顔になったので、ぼうやは嬉しくなりました。
「こわくないよって、みんなに教えてあげてね」
「もちろんでさぁ。このポッポにお任せください」
ぼうやとポッポが笑いあっていると、すぐ近くから不思議な音が聞こえてきました。
すぴー…… すぴー……
音のする方を見ると、なんとシロヒゲが丸くなって目をつぶっています。
「あれ? シロヒゲ、寝ちゃったの?」
シロヒゲの白いヒゲがぴくぴくと動きました。
「むにゃ……ここ……風とお日様が気持ちいいぜ……」
地下鉄に乗っていると、ほんの少し明るいところに出ることがあります。
そこで外を見上げると、ほんの一瞬、斜面に猫が集まって気持ち良さそうに日向ぼっこをしている姿がよく見られるようになりました。
人間たちがそこを『猫山』と呼ぶようになるのは、もう少し後のお話です。
(→次のお話はこちら)
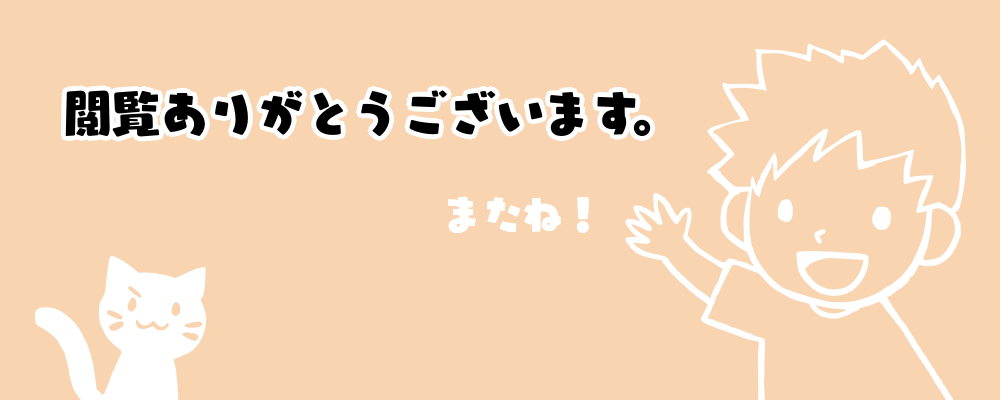
著者のブログ&Twitter
投稿者の人気記事




SASUKEオーディションに出た時の話

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

京都のきーひん、神戸のこーへん

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

機械学習を体験してみよう!(難易度低)

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

無料案内所という職業

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界
