


「来たな! よし、財布だ! 財布を出せ!」
姪のなぎさは俺の顔を見るなりそう言い放ち、母親からゲンコツをもらった。
「こら! ご挨拶が先でしょ!」
「あけましておめでとう! 財布出せ!」
「言葉遣い!」
「財布を出してください!」
「よしよし、それでいいのよ」
「いいのかよ! ねーちゃん、他にもっと突っ込むとこあるだろ」
なぎさの母であり、俺の姉でもある女は素知らぬ顔をして台所の方へ行ってしまった。
視線を下げると、なぎさが両手を揃えて上下に揺らしながら、キラキラした瞳でじっとこちらを見つめている。
「……まぁいいや。あけましておめでとう」
財布を出すわけにはいかないが、代替品の用意はある。俺は懐からポチ袋を取り出してなぎさに差し出した。
なぎさはひったくるようにしてそれを受け取ると、ぴょんぴょんと跳ねて喜んだ。
「けんきゅうしきんを手に入れたぞ!」
「研究資金?」
首を傾げていると遠くからねーちゃんの返事が聞こえて来た。
「なぎさは科学者なのよー」
なるほど、ごっこ遊びか。子供はそういうの好きだよな。
なぎさは今年で四歳。いや、五歳だったか? 赤ちゃんぽさはカケラもなくなり、身体もずいぶんと大きくなった。最近こまっしゃくれて来たとは聞いていたが、実際に会ってみると感慨深いものがある。まさか財布出せなんて言われる日が来るとは想像もしていなかったけれど。
俺は持っていた荷物を適当に隅の方に置き、部屋の真ん中にあるこたつに足をもぐらせた。向かいにはじーちゃんが座っている。
「じーちゃんもあけましておめでとう。元気?」
じーちゃんはにっこり笑った。しわだらけの顔がますますしわくちゃになった。しかし、そのまま何も言わずに震える両手で目の前の湯呑みを掴み、ゆっくりと口元まで運んで、ずずっと緑茶をすすった。……まぁ、元気そうかな?
じーちゃんを眺めていたら俺も何か飲みたくなった。俺は身をよじり、台所の方角に向かって叫んだ。
「ねーちゃん、俺の分のお茶残ってる?」
「ここにあるぞ!」
なぎさがどこからか湯呑みを持って来て、俺の前にドンと音を立てて置いた。
「こら、そっと置きなさい」
偉そうに言ってみたが、言い慣れないのでなんだかムズムズする。
俺は湯呑みを右手でそっと掴んだ。すると、予想外の冷たい感触。不審に思ってよくよく中身を見ると、やけに色が濃く、ドロドロしている。
「なんだこりゃ」
「わたしの試作品、一号だぞ!」
なぎさが胸を張って話し出した。
「お茶には眠気と疲れが取れる成分が含まれているのだ。なんというか知っているか?」
「ほう、なんだ?」
「カフェインだ! お茶が苦いのもカフェインのせいなのだ! わたしはカフェインをたくさん集めて、疲労回復ドリンクを作ることにした!
わたしはこの研究で子供の科学者として有名になって、科学界のきん……金……金太郎をうっちゃってやるのだ!」
「……金字塔を打ち立てる、か?」
「きんじとうをうちたてるのだ!」
果たして意味をわかって言っているのか怪しい部分はあるが、セリフはなかなか様になっている。なんとなく科学者っぽい。ただしマッドな方の。
俺はニッコリ笑ってなぎさの頭を撫でてから、試作品とやらをそっと置いた。
「ねーちゃん、なんか飲み物ちょうだい!」
「これ! これを飲むのだ!」
なぎさが腕にすがりついて来た。
「えー、これ飲めるのか?」
「とにかく飲んでみろ」
「やだ。別のがいい」
「飲んでよ! ねぇ飲んで!」
いかん。なぎさが涙目になって来た。喋り方も素に戻って来ているし。
できればこのような得体の知れないものには関わりたくないのだが、幼女に泣かれるのはつらい。俺はしぶしぶ湯呑みの中身を一口だけ舐めた。そして悶絶した。
苦い。とても苦い。苦味しかない。
「一体どうやって淹れたんだよ、これ……」
「じーちゃんの飲み残し集めた。一週間分くらい」
「オゥェエエエ」
「キャー! 汚い! 口に入れたもの戻しちゃダメでしょ!」
「なんてもの飲ませるんだこのクソガキ!」
「もー! せっかく集めたのに! ひどい!」
「集めんでいい! 生物兵器でも作るつもりか!」
子供のやったこととは言え、あんまりだ。この怒りはどこに向けたらいい? 親か? 我が子の恐ろしい研究を放置していた親が悪いのか? おのれねーちゃん文句言ってやる。
俺は湯呑みを持って立ち上がった。大股歩きで台所まで行き、キョトンとしているねーちゃんをシンクから押しのけ、湯呑みの中身をぶちまける。それから手で水を汲んで口をすすいだ。
後からついてきたなぎさが湯呑みの行方に気づいて泣き崩れた。一週間の努力が無になったことがショックなのだろう。
ねーちゃんが腰に手を当てて言う。
「もー、なに泣かせてんのよ」
「俺も泣きたいよ」
科学者様の監督者に罵詈雑言を浴びせるつもりでここに来たが、口の中がスッキリしたら少し頭が冷えて来た。
あのおぞましい液体を放置しておく選択肢はなかった。でも、ちょっとやり方が大人気なかったかな……。
なぎさは床に突っ伏して激しく泣いている。つらい。
俺にできることはなんだ? 大人として、現実を教えてやることだ。
俺はその場に膝をつき、なぎさの背中をポンポンと叩いた。
「なぎ、起きろ」
しばらく待っていると、なぎさが肩を震わせながら顔を上げた。涙と鼻水でぐしゃぐしゃの、ひどい顔だ。
俺はなぎさの真っ赤な目を見つめ、できるだけ優しい声で言った。
「あのな、コーヒーって知ってるか?」
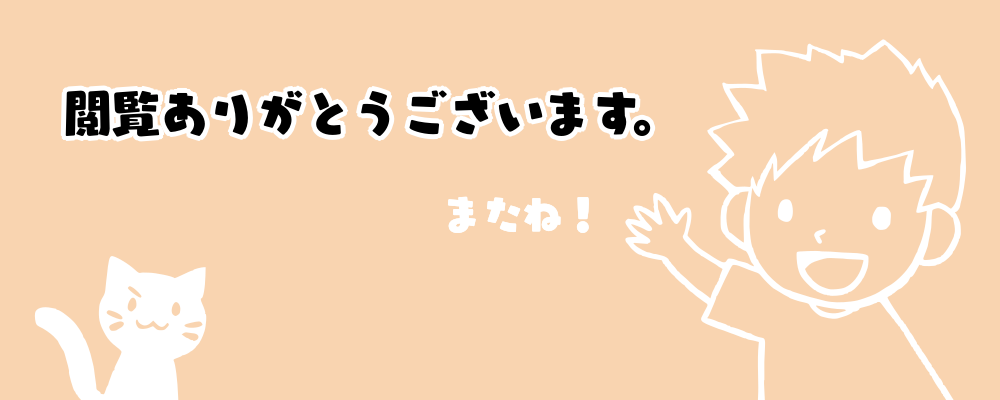
よろしかったら別の小説もどうぞ(・ω・)ノ
投稿者の人気記事




テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

SASUKEオーディションに出た時の話

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

バターをつくってみた

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

機械学習を体験してみよう!(難易度低)

無料案内所という職業

京都のきーひん、神戸のこーへん
