


小さなぼうやと小さな黒猫のシロヒゲは、仲のいい友達です。
ぼうやの住む街は今、どこもかしこも雪が積もって、真っ白です。
公園でひとり雪遊びをしていたぼうやは、すべり台の下で怖い顔をしている、真っ白いヒゲの黒猫を見つけました。
「こんにちはシロヒゲ。なにをしているの?」
「やぁぼうや。あれを見なよ」
シロヒゲが小さな手でさした先にはベンチがありました。その上に、ダンボール箱が置かれています。箱にはみかんの絵が書いてありました。
「あそこからなんだか嫌な匂いがするんだ」
シロヒゲは怒ったような顔で、黒い毛を逆立てています。
ぼうやはクンクンと匂いをかぎながら、箱に近づいていきました。けれど、あと一歩というところまで来ても、気になる匂いは感じません。
ダンボールの口は閉じていましたが、テープでとめられている様子はなかったので、ぼうやは思い切って中を見てみることにしました。
箱を開けてすぐ、ぼうやはびっくりしました。箱の中で、タオルにくるまった小さな犬が、寒そうに震えていたからです。
慌てたぼうやがタオルごと犬を抱えて走り出すと、シロヒゲがあとからついてきました。
「ぼうや、どうしたんだい?」
「子犬が寒そうなんだ」
「ゲェ、犬だって?」
シロヒゲはすごく嫌そうな顔をしましたが、足は止めませんでした。
「そんなやつ放っておきな!」
「だって、かわいそうだよ」
言い合っているうちにぼうやの家につきました。二人はどたばたと玄関を通り抜け、電気ストーブの前に子犬を連れていきました。
しばらくすると、子犬の震えはおさまりました。タオルの中で身じろぎしながら、キャンキャン泣いています。ぼうやはその悲しそうな鳴き声を聞いていると、なんだか落ち着きませんでした。なにしろ、この子犬はシロヒゲよりもずっと体が小さいのです。
「ねぇ、この子も言葉をしゃべれるかな?」
「さあな。でもこいつ赤ンボだろ。無理だよ」
「どうして泣いてるんだろうね」
「おいらが知るかい」
シロヒゲはぷいっとそっぽを向いてしまいました。
ぼうやはふと思いついて、キッチンからみかんを持ってきました。子犬の前にすわって皮をむき始めると、シロヒゲがものすごい速さで部屋のすみっこに逃げて行ってしまいました。
「なんだいそりゃ! ひどい匂いだ!」
「みかんだよ。おいしいよ」
「うそだ! 食いものの匂いとは思えないぜ!」
子犬は、ぼうやの手の上に乗ったみかんをモリモリ食べました。ベロが手に当たるとくすぐったくて、ぼうやはふふっと笑いました。
「シロヒゲも食べてみる?」
「おいらはいらねえ! いいから外に出してくれよ!」
ぼうやがシロヒゲのそばの窓を開け始めると、シロヒゲは窓の隙間に体を押し込むようにして庭に出て、雪の上をピューッと走ってどこかへ行ってしまいました。
子犬は時間をかけてみかんをまるまるひとつ食べると、ウトウトし始めました。
ぼうやは床に頬杖をついて、眠った子犬をうっとりと眺めました。
「眠るとまん丸になるんだなぁ。小さな黒いぶちがたくさんある。そうだ、ミカンって呼ぼう」
その時、ぼうやは困ったことを思い出しました。
ぼうやのママは動物が苦手なのでした。中でも、犬は大嫌い。写真を見るのもつらいと、前に言っていました。
ママが帰ってきてミカンを見たら、とてもびっくりすることでしょう。きっと、「元の場所に戻してきなさい!」と言うはずです。
ミカンをまた寒い外に連れて行くなんて、かわいそう。ぼうやは憂鬱になりました。かと言って、パパやママに隠れて飼おう、と言う気持ちにはなれないのでした。
思い出すのは、シロヒゲのこと。あんなに嫌な顔をするなんて。もしミカンがぼうやの家の子になったら、ぼうやは嬉しいけれど、シロヒゲはどうでしょう? これまでのように会ってくれなくなるかもしれません。それはそれでぼうやにはつらいことでした。
どうしよう……どうしよう……
ぼうやが不安になってきた時、うしろからコンコンと音がしました。
見ると、窓ガラスの向こうでシロヒゲが手を振っていました。
戻ってきてくれたんだ! 嬉しくなったぼうやはすぐに窓を開けてやりました。
じゅうぶんに窓が開いても、シロヒゲは中に入ってきません。気まずそうにうつむいています。
「どうしたの?」
ぼうやが聞くと、シロヒゲは
「ちびすけのことおいらの親分に話したんだ。そしたら、犬には犬の道理があるって怒られちまって……」
小さな声でゴニョゴニョと返事をしました。けれど、ぼうやにはうまく聞き取れません。
「なぁに?」
「……とにかく、そいつを連れて出てきてくれるかい?」
シロヒゲが庭の真ん中に向かって歩き出したので、ぼうやはミカンをまたタオルにつつんで抱き上げ、あとをついて行きました。
外はすっかり暗くなっていました。いつの間にかちらちらと降り始めていた雪が、ぼうやのほっぺたをくすぐりました。
ぼうやとシロヒゲは雪山の前で立ち止まりました。ぼうやのパパが雪かきして作った山です。シロヒゲが静かなので、ぼうやも静かにしていました。
ぼうやが、白い息をほうっと五回ほど吐いた頃でしょうか。シロヒゲが不機嫌そうに「にゃあ」と鳴きました。すると、雪山のうしろからぬうっと黒い影が出てきました。
よく見ると、それは大きな犬でした。三角の耳がピンと立った、口のまわりと手足の先が茶色い犬です。毛が短くて、スラリとしています。
大きな犬はゆっくりぼうや達の方に近づいてきて、ぼうやの前に腰を下ろしました。
シロヒゲがぼうやに言います。
「ここいらの犬の親分だそうだ。こいつにちびすけを渡してくれ」
「え、でも……」
「ぼうや」
犬の親分が口を開きました。うんと低い声でした。
「その子は捨て子だろう。保護してくれて感謝する。あとは我々に任せてくれ」
「……ミカンを元気にしてくれるの?」
「ミカンとは、その子の名前かね?」
ぼうやはコクリとうなずきました。
「大丈夫だ。子育てに慣れた仲間が待っている」
ぼうやは少し考えてから、ミカンを犬の親分に差し出しました。
「ありがとう。この子が大きくなったら、きっと君に恩を返させよう」
犬の親分は大きな口でそうっとミカンをくわえると、音もなく歩いて庭を出て行きました。
しばらく経つと、ぼうやはポツリと「行っちゃった」とつぶやきました。
シロヒゲがそばによってきて、ぼうやのくつを撫でてくれました。
「ごめんよ。前に、ぼうやの家は動物を飼えないって言っていたから、出しゃばった真似しちまった」
「……ううん。ありがとう。ちょうど困ってたんだ。
ぼくね、シロヒゲが好きだよ。ミカンもいっしょなら、きっともっと楽しいんじゃないかと思ったんだけどな」
「そうかい。……さっきはごめんな」
「いいよ」
ぼうやはしゃがんで、シロヒゲの方に両手を伸ばしました。シロヒゲをぎゅっと抱きしめたくなったのです。
シロヒゲはニコッと笑っておとなしくしていました。けれど、ぼうやの手が顔に近づいてくると、ものすごい勢いで体をそらしてぼうやから離れました。
「くさいっ!」
シロヒゲはそう言いながら雪の上をゴロゴロ転がっています。
「もう、シロヒゲったら。へんなの」
ぼうやの指先は、さっきみかんをむいたせいで黄色く染まっていました。
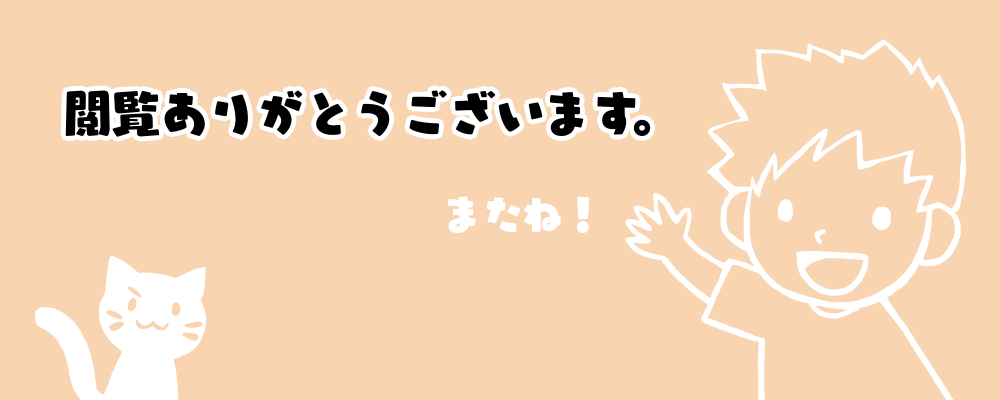
ほかのお話もいかがですか?
投稿者の人気記事




17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

無料案内所という職業

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

SASUKEオーディションに出た時の話
