

新鮮な素材を最適な調理法で仕上げる、これが美味しい料理の神髄だ。
「キール、まだなの?」
「リサ、ちゃんと血抜きとかしておかないと旨い料理は出来ないんだぞ。もう少し、待てよ」
釣った魚をそのまま豪快に木の枝に差して焚火で焼くのもそれはそれで美味いもんだが。折角のいい魚だ、刺身で食べたいよな。
血抜きした後は頭を落とし、鰓や内臓を取り除き海水で洗い流す。黒鯛に似た魚を三枚に下ろし、板に身を皮を下にして置きナイフを心持ち上にする感じで皮を剥ぐ。 身を斜めに切り最後の瞬間垂直にナイフの刃を立てる。黒鯛のに似た魚の刺身の完成だ。残した皮は、少し塩を振って香ばしく焼き上げる。
頭と骨から出汁をとってスープを仕上げて、キャンプ飯の完成だ。
「うん、美味しいね。刺身だっけ?すっきりとした味わいで、いいね」
(でも、狩りに来てこんなお店屋さん顔負けの料理を出すキールって何者なのよ?) 「ああ、こうして焼いた皮で巻いて食べるのも美味いぞ」
「ああ、ほんとだ」
『ところで、キール。こんなところで、何を待っているのだ?』
洞窟を背にし、磯での釣果を料理してピクニックを楽しんでいる様にも傍からは見えるかも知れないが実はこれには深い理由があった。
「ほう?わしに何を造らせたいんだ、若いの」
「まあ、これを見てくれ。こいつに足りない ー 部品《パーツ》を造って欲しいんだ」
「おお、こ、これは!」
「む、無理だ。これに合わせるパーツだと素材もとんでも無いものになるぞ。そんなものは、ここに無い!」
「無ければ、俺たちで探してくるさワフードさん」
という訳で、凄腕の鍛冶師に製作を依頼をしたんだがその条件として、最上の素材を入手する約束をしたんだ。
『それが、この洞穴にあるのか?』
「ああ、あるというか。居るんだよそいつが」
『なるほど、そ奴が目覚めたらしいな』
ズドーン、ズドーン。腹に響く重低音、大きな唸り声、洞穴の中から現れたのは巨大な生物、そう全身鱗に覆われ、大きな翼を持つ竜であった。
「ええ、キール竜と闘うなんて聞いて無いよ」
「ああ、闘うなんて言ってないからな。
こんにちは、元気かい?」
『キール、まさかこの竜と知り合いか?』
『見ない顔だな。まあ、元気だが。元気過ぎてちょいと旨そうな匂いを嗅いだら無性に腹が減ってきてな』
「そうかい、まだたっぷりとあるから人間の料理で良かったら食べてみるかい?」 『ふっ、なら試しにご馳走になろうか』
『おお、キールこの刺身とやら美味いのう。普段の丸呑みにして喰うやり方だと判らぬ繊細な滋味が感じられるのう』
「まあな、骨も内臓も身もいっしょくたにして喰っていたらこの微妙な味わいには気付かないだろうな」
一人の見知らぬ少女が、美味しそうに黒鯛に似た刺身や海老などを瞬く間に平らげていく。そう、竜本来の姿では一瞬のうちに食べ尽くすのを残念に思った彼女が少女に擬態しているのだ。
『うーん、堪能したぞキール』
「お粗末様」
『これほどの美味を頂いたからにはお礼をしなくてはな』
「まあ、俺にも下心があってやって来た。こいつを補完する部品を造るためお前の鱗を何枚か貰いたい」
『ほう、その者ソローンの身体や手足をか?
まあ、良かろう鱗はくれてやる。それにその者は稀有なホムンクルス故、我の鱗だけでは補完し切れぬな』
『ふっ、流石は永の年月を生きた竜よ、偉大な「ソローンの造り手」様の御業を解っておるようだの』
『故に我の右眼を暫くの間貸して遣わそう』
「眼を。お前大丈夫なのか?」
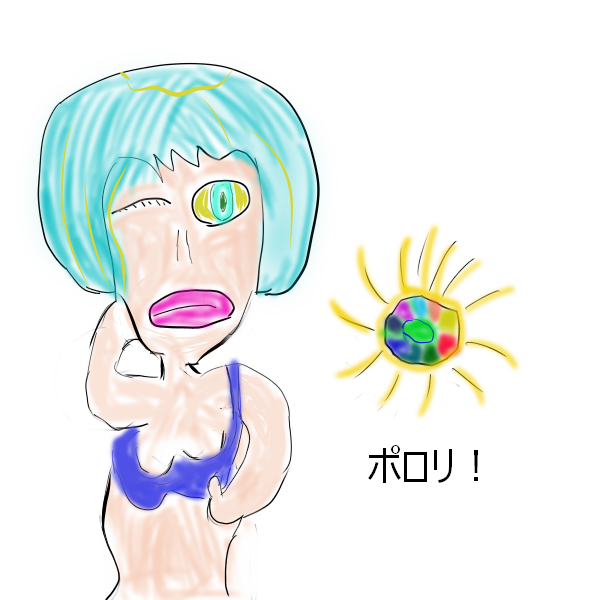
『なーに、用が済めば我が元に戻って来るわ。それも数年も経ずにな・・・・・・』
『ふっ、永い旅にならずに済みそうか。
旅が成就するか、はたまた終わるかは別として・・・・・・』
目 次
投稿者の人気記事




バターをつくってみた

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

京都のきーひん、神戸のこーへん

SASUKEオーディションに出た時の話

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる
