

この日、町には見慣れない旅人が訪れた。性格残念な美女と見目麗しい美青年のカップルが、何の特産品もない町にふらりと現れたのだ。
「それで?」
宿屋の食堂で美女が美青年に問いかける、早く話を聞かせろと圧力を掛けながら。 「やだな、先輩。食事中はもっと楽しい話をしましょうよ」
「ふん、それで・・・・・・」
美女が冷たい視線で睨みつけるとようやく美青年は観念したかのように計画を話したのだった。
「ねえ、娘さん。頼みがあるんだけど」
「はーい、今行きますよ」
宿の店番をしていた娘が、食事時を過ぎて客がまばらな食堂にまだ客が残るテーブルに呼ばれて、追加注文を取りにやって来た。
「ごめんなさいね、このスプーン落としちゃって。別の物に替えてくださる?」 (え?うちの食器じゃないよね。うちのスプーンは木製だし、こんなキラキラした金?のような上等な物じゃないわ)
「あのう、それはうちのスプーンではないみたいですが ・・・・・・」
「あら、そう。でも、ようく見てごらんなさい。ほら、あなたの可愛いお顔が映っているわよ。やっぱり、あなたのものよ」
「ええ、そうですね」
「じゃあ、替わりのスプーンを持って来てね」
「はい、わかりました」
宿屋の娘は、大事そうに金のスプーンを前掛けの隠しにしまい込むと台所へ向かった。
「お客さん、お待たせしました。替えのスプーンです」
「ええ、ありがとう」
「えへへ、今日は良いことがあったな。儲かっちゃった、こんな上等なスプーンいったい幾らで売れるかなあ?
それか大事にとっておいて、私の嫁入り道具にするのもいいかな。
生まれて来る赤ちゃんに咥えさせたら、一生お金には困らないっていうし・・・・・・」 (ああ、それにしても綺麗ねぇ。なんだかいろんな嫌なことがもうどうでも良くなってしまうみたい。母さんの小言も父さんの鼾もいいやってなっちゃう。
不思議ねえ)
「誰か、いないかい?三本通りを挟んだ向こうの宿屋に配達に行っとくれ。
もう、みんな出払ってしまったのかい」
「母さん、私行って来るよ」 商店の娘が配達に名乗り出た。
「ああ、シェーラ済まないね。じゃあ、この商品だから頼んだよ」
「はあい、行って来ます。支払いは月締めでいいんだよね?」
「そうだよ、来月五日の支払いは締めて十万霊子《レイス》になるから残高には気を付けるように言っといてね」
「ええ、あんまりお客様を信用しないのもどうかと思うよ、母さん」
「この娘ったら、だんだん死んだ父さんに似て来たねぇ・・・・・・
もう、さっさと行っといで」
「何か他に入用の品はありませんか?
はい、それでは来月の五日には合計十万霊子を口座から自動で引き落とされますのでよろしくお願いしますね。
ええ、苦労人の母が心配性なもので。ええ、こちらがそんな不義理をすることは無いのは百も承知しております。 では、毎度御贔屓に」
食堂のテーブルにいた女が、少女に問いかけた。
「ねえ、若い店員さん。あなたの所でこういう物は買っちゃくれないかい?」
「はい、ただいま。拝見してもよろしいですか?」
「ええ、見て頂戴。なかなか綺麗でしょ?」
女はキラキラ光る飾り玉の付いた首飾りを少女の手に置いた。妖しくも煌びやかに輝く様は、到底少女の小遣いでは買えない値段に思えた。
「ほう、本当に綺麗だわ。もちろん、うちで買い取りたいと思いますが・・・・・・
正直言って、私には幾ら値段を付けてよいやら。お客様、お預かりするのも高価なお品ですので明日店の者を商談に来させますので、お待ち願いますか?」
「ふうーん、お嬢ちゃんお名前は?」
「はい、○○商店の娘でシェーラと申します」
「そう、シェーラね。あなたのことは気に入ったから、これはあなたにあげるわ。それで、まだ同じような首飾りがあるから是非商談のときは店主さんにも来ていただけないかしら?」
シェーラは、いきなり自分の物になった首飾りから目が離せなくなった。そして心も妖しく輝く石に囚われていた。
「はい。明日は母さんと商談に参ります、ご主人様・・・・・・」
「結構、大変結構よ。ふふふ」
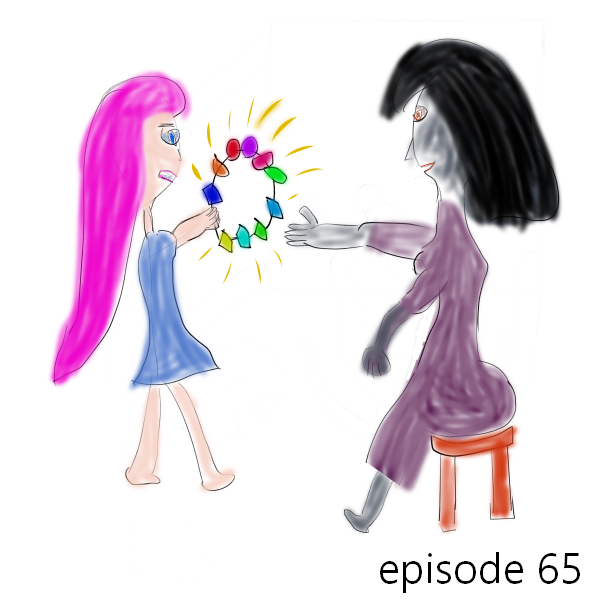
目 次
投稿者の人気記事




警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

無料案内所という職業

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

機械学習を体験してみよう!(難易度低)
