

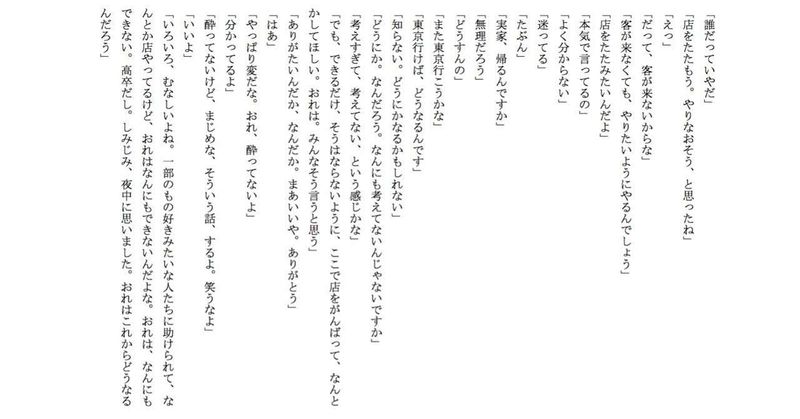
「迷ってる」
「たぶん」
「実家、帰るんですか」
「無理だろう」
「どうすんの」
「また東京行こうかな」
「東京行けば、どうなるんです」
「知らない。どうにかなるかもしれない」
「どうにか。なんだろう。なんにも考えてないんじゃないですか」
「考えすぎて、考えてない、という感じかな」
「でも、できるだけ、そうはならないように、ここで店をがんばって、なんとかしてほしい。おれは。みんなそう言うと思う」
「ありがたいんだか、なんだか。まあいいや。ありがとう」
「はあ」
「やっぱり変だな。おれ、酔ってないよ」
「分かってるよ」
「酔ってないけど、まじめな、そういう話、するよ。笑うなよ」
「いいよ」
「いろいろ、むなしいよね。一部のもの好きみたいな人たちに助けられて、なんとか店やってるけど、おれはなんにもできないんだよな。おれは、なんにもできない。高卒だし。しみじみ、夜中に思いました。おれはこれからどうなるんだろう」
「おれだって」
「酔っぱらって、覚めかけた頭で、見てた。まわりが一番気持ち悪く見える。それでまた、飲んだ」
「あ、雨」
「やっと小降りになってきた」
「これなら、出れるよ」
「どうして季節はめぐるのでしょう」
「さあ」
「おれはこっちで何回、桜を見たんだっけ」
「さあ」
「それが散るのも。みんな、同じだ。もういつがいつのことだったか」
「なに」
「てきとうなことばっかり言うなよ。ちゃんと考えてるか。それとも、本当に分からないのか」
「分からないですね、さっぱり」
「なんのために大学入ったんだよ」
「買いものですか」
「うるせえ。携帯。取りに行くんだよ」
「おれも帰る」
「すぐそこだから」
「じゃあ一緒に行く」
「待ってろよ」
「はあ」
「昨日知り合ったんだよ。悪かったね。その子に携帯貸してたのを、忘れてたの」
「悪くはないよ。ああそうなんだ」
「そうやって変な目で見るから、めんどくさくて言わなかったんだよ。女の子。高校生くらいの」
「高校生。ふうん」
「おれから声かけたとかじゃないよ。となりのベンチで、ぼんやりしてた。いつのまにか、そこにいて、ちょっと離れて、ならんでたことになるのかな。しばらく。一時間か、二時間か」
「ひまな人たちだな」
「それで、携帯、貸してくれって、突然言われた」
「貸したんでしょう」
「らしいよ」
「なにそれ。どういう話になるの」
「別に落ちなんかないよ。それだけの話だよ。それだけ。いま、待ってるんだって」
「じゃあ急がなきゃ」
「たぶんね」
「はあ」
「家出か、けんかか、知らないけど、あやまってるみたいだった。見ちゃいけないというか、聞いちゃいけない気がして、おれは逃げた」
「そんな時間になればたいていあやまるよ。けんかじゃなくても」
「まあ、だといいね」
「なんにしても、帰れたんでしょう」
「そう言ってた」
「よかったね」
「しかし、あんな時間にひとりでいるのは、それがもうただごとではない。おれは心配なんだよ」
「自分のこと言ってんの」
「おまえは、いままでの人生でなんの悩みも苦しみもなく、まったく順調に生きてきたような顔してやがる。そういう覚えがないのか。人生について、深く考えたことが」
「それをマスターから言われるのも心外だな。いきなり昨日今日になって悟りを開いたようなこと言って。それは、人なみにものを考えますよ。おれだって」
「じゃあおれの気持ちが分かるか」
「分かるわけない」
「じゃあおれのかわりに携帯もらって来い」
「また変なこと言う」
「行って聞いて来い」
「なにを」
「人生について、ちょっとでも」
「結局、会うのがいやなんですか」
「なんだか」
「うん」
「いや、でも、ごめん。本当にごめんだけど、なあ、きみねえ、やっぱりなんにも考えてないよ」
「はあ」
「たとえば、じゃあ、高校のときでいいよ。早く、東京に出たいとか、卒業して、どうしようとか」
「どうして、こんなことでおれが怒られるんですか」
「いいから」
「むずかしいです」
「むずかしいだろう」
「いきなり言われても」
「自分のことじゃないか」
「あの」
「どうした」
「こういう話なら、またあとにしませんか。今夜でも、明日の夜でもいいけど」
「逃げるなよ」
「はあ」
「分かったよ」
「おれ、待ってればいいんですか」
「そうだよ。せっかくこんな時間までいたんだから、昼もつくってやるよ」
「どうも」
「なんだこれ。おい」
「あじさいですね」
「さっきの婆アかな。なんでこんなもん忘れていくんだ」
「捨てたんじゃ」
「あ、やんでる」
「どんよりしてる」
「これから憂鬱だな」
「置いとくの、あじさい」
「置いとくよ。このへん。ほら、いいじゃない」
「サボテンかどっちか、どけたほうがいいと思う。もうごちゃごちゃしてなにがなんだか」
「そうかな」
「待たせてるんでしょ」
「いじるなよ」
「うん」
「待ってろよ」
「いってらっしゃい」
投稿者の人気記事




【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

バターをつくってみた

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶
