

映画バベルは、人と人の間に引かれた境界がテーマだと感じた。
人造的なシステムとしての境界だ。
それはバベルの塔の神話のように神が罰として与えたものなどではなく、人間自身が作り上げ、意識的にも社会的にも維持し続けている境界だ。
映画バベルにはいくつもの境界が描かれている。
モロッコにおいては、そこを巡る観光バスの内部と外部の間にある境界だ。それは窓ガラス一枚の境界だ。
旅をしていて、観光バスに乗るとこの境界をとても強く感じることがある。
さっきまで、そこの地面で、乞食といっしょに地べたに座っていたとしても、バスに乗ってしまえば、少し上のほうからそこの人々をガラス越しに見下ろす位置に入ってしまう。
そのとき、とてもせつなくなる。
だが、自分にはその境界を破ることはできない。
その証拠に乞食と一緒に座っていたときにも僕は腹帯の中に巻いた日本国パスポートをけっして破いて棄てようとはしなかったではないか。
ごくたまに本当にそれを破いて棄てる旅行者がいるようだが、(友人にもひとり、火にくべてしまったやつがいたが)、それこそ、ぶっとびの本物の境界破りであろう。
さて、映画バベルでは、その観光バスの窓ガラスという境界は、子供がいたずらで放った銃弾で簡単に貫通されてしまう。
それによって重傷を負った妻(元妻?)を必死で介護する夫(ブラッド・ピット)に、観光バスのほかの乗客たちはことのほか冷たい。
大使館などの対応も、政治的思惑がからんで、個的な命は優先してくれない。
結局、一番助けてくれたのは、近くの村出身の現地人ガイドだ。
彼と、怪我人の間にだけ、システムとしての境界を越えたつながりが自然に生まれていく。
いざというときに、助けてくれる人は誰か。
それは、システムの中にいる人間ではなく、ただあたりまえにそこにいる人間だと思う。
そのことがよく描かれている。
20代のころ、僕もインドネパールなどを放浪する旅行者だったが、30代のころ、縁あってロスアンジェルスの領事館のパーティに参加したことがあった。当時僕は仕事で外交官パスポートを持っていたのである。
そのとき、以前にインド大使館にいたという日本人女性が「日本人の若い旅行者たちは、無謀なことをしていざとなると大使館に頼ってくるので困る」などと話していて、
聞いていた僕は「以前は僕もインドで無謀かもしれない旅をしていたけど、大使館なんて何の役にも立たないとみんな言っていた。困ったとき、助けてもらうのは、そのとき隣にいる普通の人間だった。日本人だろうと、インド人だろうと」と言ってやった。
イラクで香田さんという旅行者が殺されたとき、日本政府は「自己責任」と言った。
あのときもそれを思い出した。根本的には「助けてくれるのは、そのとき隣にいる普通の人間だ」というのは、真理だと思う。
しかし、システムによる境界が張り巡らされた世界では、その争いが、ただの人とただの人をまで分断してしまっているので、隣にいる人との間に境界ができてしまっている。
通じない。
反対勢力の人間としてしか見られない。
それが悔しい。そうしておいて、後に「自己責任だ」という、国家というものが悔しい。
さて、「バベル」に描かれている二つ目の境界線は、メキシコとアメリカの間の国境線だ。
アメリカのサンディエゴに住んでいた家政婦が、預かっている子供と一緒に、息子の結婚式のためにメキシコ側にわたり、アメリカ側に戻ろうとして、国境でトラブり、追われる身となる。
子供たちは「悪いことをしていないのに、なぜ逃げるの? 悪者なの?」と問う。
答は、「システムに適合しないから逃げるの」であるが、そんな説明は通じない。
ただ「悪者じゃないの」と釈明するばかりである。
僕もサンディエゴに三年間住んでいたので、何度かその国境を越えたが、アメリカ、メキシコの国境は、世界の中でも最も貧富の差が激しい国境のひとつであろう。
僕がサンデイエゴに住んでいる間に、そのメキシコ側で日本人社長が誘拐されるという事件もあった。
またカリフォルニア州はそれまで不法入国の子供にも高校までの教育を無償で保障していたのだが、住民投票によってその制度が否定されるという画期もあった。
サンディエゴの道路のいたるところには、子連れの不法入国のメキシコ人が道路を横断するところを描いた標識があり、鹿などの動物が道路を横断する標識と数を競っている。
その可能性があるから速度を落とせ、危険であるという標識である。
が、実際にそのようなメキシコ人を轢いてしまったとしても、罪に問われたり、賠償を迫られたりすることはない。
そのようなメキシコ人はそこにいてはいけない存在なのであり、現に事実、生きた人間の親子として存在していたということを「あってはならないこと」として否定されてしまう存在なのだ。
この映画が、観光バスのガラスの内と外の次に、アメリカ、メキシコ国境を、境界線の象徴として用いたのは、経験的に言って「まさしく、そうだ」と思わせるに足る。
続いて、この映画に描かれている三つ目の境界線。
それは、菊池凛子が助演女優賞をとって話題になった耳の聞こえない少女の世界と、聴覚障碍のない人の世界の境界だろう。
しかし、僕がこの映画を見た当時のブログは、二つ目の境界線の話題でプツリと切れていて、続きが見つからない。
その後、 実際に身体障碍者になった今思えば、それは、今こそもう一度この映画を見て、三つの境界線の描かれ方と、その有機的繋がりについてのレビューを完成させろという意味なのかもしれない。
僕はこの映画を一度しか見ていない。
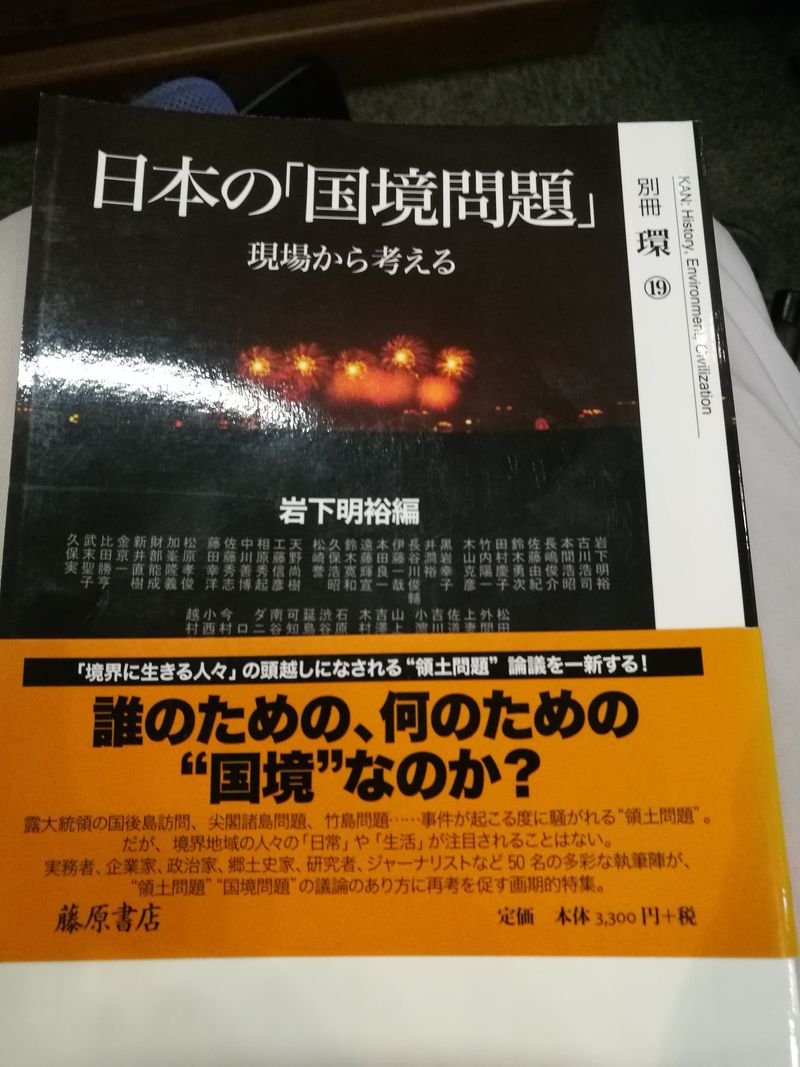
投稿者の人気記事




17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

京都のきーひん、神戸のこーへん

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

バターをつくってみた

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】
