

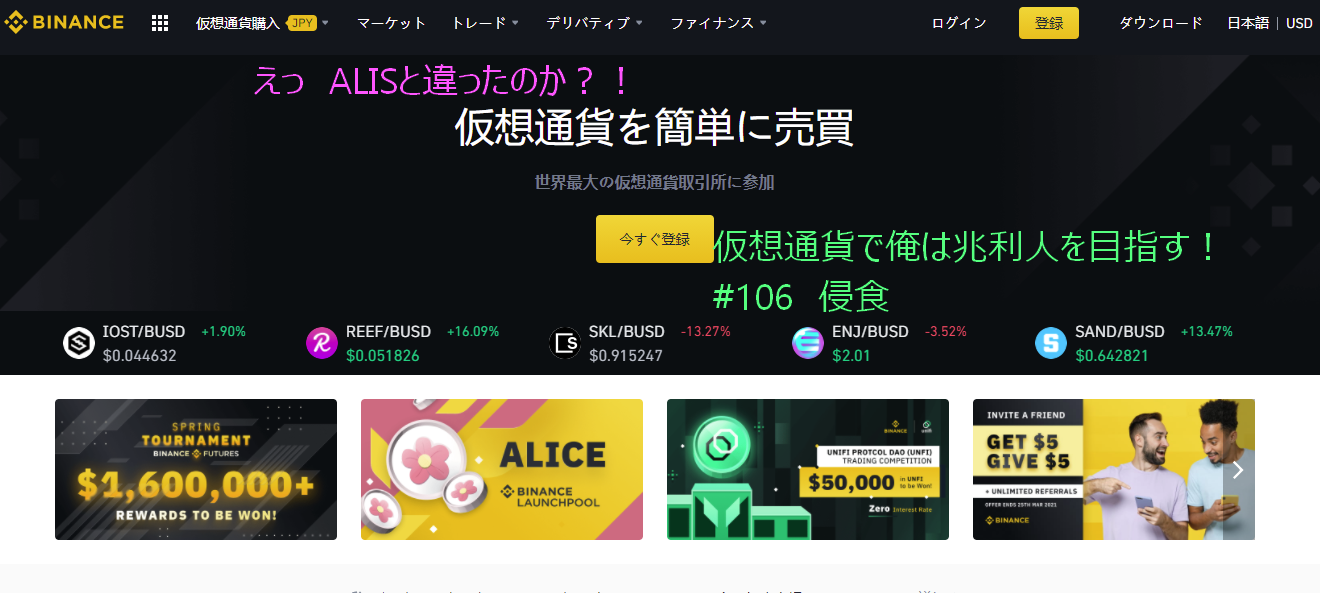
106 侵食
早く、もう待てない・・・・・・
う、ううー・・・・・・
ドバイの高層レストランを貸し切って食事をする。これは、もはや金銭で買えないレベルの贅沢である。まあ、そんなことを気にする人間では最初からなかった人物のにとっては真にどうでもいい評価であった。
「ふふ、そろそろ収穫の時期かしら。エネルギーと質量と速度、条件が揃った気がするわね」
「御意、社長の思惑通りに状況は推移していると思われます」
黒い服を纏った男は主人に答えた。
「ふーん、そんな当たり前のことをいう暇があるのね、あなたには・・・・・・」
地上階の数分の一は海中に没している高層レストランで側近は、命の終焉を覚悟した。故に晴れがましい笑顔で、はい、と答える。
「なーんだ、全てわかってるようね。これだから、側仕えを何百年も使うのは考え物だとお爺様が仰っていたのね。でも、使い勝手のいい手下を育てるのも面倒だし。もうしばらくあなたには居て貰うわね、セバスチャン」
「はい、社長・・・・・・」
自分の名前がセバスチャンでないことを抗議する必要性など微塵も感じぬ体で召使いは答える。
「そういう訳だから、あの紅の災害を招待してね。セバスチャン」
「かしこまりました」
北米大陸跡の東海岸に大災害前と変わらぬ風情で佇む自由の女神像に黒い闇が迫る。
青銅の女神像が、強大な力により胴体からへし折られた。
「乱暴な挨拶ね、誰かしら?」
「社長の使いの者だ。晩餐に招待するのでついて来て欲しい」
黄金の弾道ミサイルの上に腰かけたスカーレットに、黒服の男が答えた。
「ふうん、下っ端に文句を言っても始まらないわね。まあ、いいわ案内して」
「では、ついて参れ!」
黒服の男は、東へ、沈没したアフリカ大陸の方に飛び立った。スカーレットは黒服の男の後方から追い抜かさないように気を付けて尾いていった。一時間ほどで、目的地に着いたようだ。
「社長、お客様をお連れしました。」
「そう。セバスチャン、ご苦労様」
「ところで、あなた。用件は何?寂しいから食事に誘ったとかいう玉じゃないでしょ!」
「ふふ、理由?そうね、あなたに興味があるから。というよりも、乱導竜のお気に入りにほんの少し興味があるというのが正確かしらね」
「竜に、あなたは一体・・・・・・」
「まあ、せっかちさんね。折角用意したんだから、堪能してちょうだい、あなたの最期の晩餐なんだから、ふふ」
「まあ、日本だと腹が減っては戦は出来ぬというらしいわね、竜から聞いたことがある。高級そうな店だから期待させて貰うわ」
デザートを食べ終わって、紅茶を一口飲んで社長が問う。
「どうかしら、お口にあったかしら?」
「ええ、美味しかったわ。人外の提供できる味では無いわね、不思議なこともあるわね」
「ふーん、気づいていて。あなたも、大概ね。まあ、自分で気付いているのかしら?既に引き返せない所にいることが」
社長と呼ばれる女が、黒服を棉あめのように吸い込んで食べてしまった。
「それがあなたの戦闘開始なの?ずいぶん、食いしん坊さんね」
「やせ我慢は、よしたら?もうすでに自分と魔人の区別が覚束ないはずよ。
そう言えば、名乗って無かったわね。別れの前に一応名乗ってあげましょう、いわゆる冥土の土産という奴ね。西城斎酒《ゆき》よ、間もなくあなたを地獄に送る者の名を覚えておきなさい!」
斎酒が名乗った瞬間、彼女の周りにあった靄が消えたのかと思うほど今までぼんやりと女性がいると感じていたのが、鮮明に恐怖と美の体現者としての姿が浮き彫りになった。 斎酒の繰り出す雷が、スカーレットの防御の金扉に弾き返され高層レストランは脆くも崩れ去った。
「くっ、これほどの力をただの人間だった者が操るとは。警戒すべきは魔人アスタロトなのか?ええい、そろそろ限界が近いはず。消え去れ、燃え尽きよ!」
斎酒の全身から湧き出す紅蓮の炎がスカーレットに殺到する。
「闇《サラーム》金の精霊《ダハブ》よ、原始の炎で弾き飛ばして!」
眩い光と数万度の炎が、紅蓮の炎を一掃すると斎酒の全身を蕩かしていった。
「くっ、最後の時を迎えたらしいわね。そう、わたくしの戦場はここではないみたいね。気を付けなさい。笑顔ですり寄る者を詐欺《スキャム》はいたるところに存在するわ、ごきげん、よ、う・・・・・・」
「西城斎酒、彼女は一体? ・・・・・・」
クジラの背に揺られながら、スカーレットは己が口座の残高が増えたことを確認すると寂し気に微笑んだ。
<<前話 次話>>
目 次
今週のピックアップ
投稿者の人気記事




NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

機械学習を体験してみよう!(難易度低)

SASUKEオーディションに出た時の話

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話
