


35 条件
「え?あんた、今なんて言ったの?使い魔を借りたいですって!冗談じゃないわ」
深い湖を想わすような青色の表面を水が流れるように、あるいは水面に光が乱反射するように刻一刻と変化していく不思議なドレスを纏った大変綺麗な少女が俺の願いに拳を震わせて激高していた。誰が呼んだか青の悪魔、下僕一号だ。
「まあ、俺の話もきいてくれ。下僕一号」
「ふんっ、人の名前も碌に知らない癖に頼み事なんてね。笑っちゃうわ」
「それは、お前が教えてくれないからだろう!ご丁寧にネコさんにまで口止めしているしさ」
腕組みをしながらこちらを、こちらを値踏みするような美少女、ただし性格はかなり強烈に悪いときた。ネコさんにこいつの好きな物でも聞いといて、贈り物送ってご機嫌取りでもすれば良かったかな?
「そうね、下賤な人間の心臓とかは割かし好きかもね。ふふ」
「おい、そんなもの差し出せる訳ないだろうが」
「そうね、その程度の覚悟で私の大切な使い魔を気軽に貸し出せと言えるメンタルがある意味尊敬に値するわね。
でもね、残念なことに例えあなたに使い魔を貸し出したとしても、決して彼らはあなたに力を貸さないわ。
使い魔に命令を下せるのは別に私が偉いからじゃないのよ。使い魔に命を投げ出させるだけの力と恐怖で、ねじ伏せたから。私も使い魔も命懸けの勝負を経て納得のいく上下関係が構築されたのよ。
命を賭ける覚悟のある者だけが、彼らを従えることが出来る。使い魔の主でいるとは、そういうことよ」
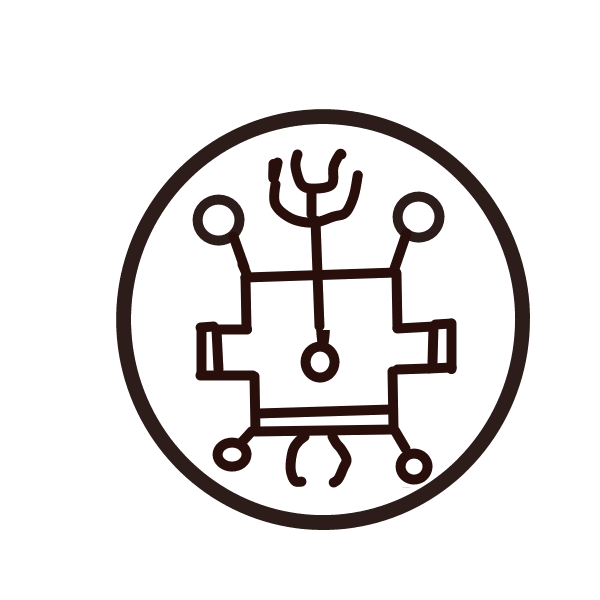
俺は、少し下僕一号を見直したかも知れない。だが、そんなことをこの場で言う場面ではないよな。なら、俺はどうする?どうすれば、目的を達成できる?
「なら、俺も使い魔に力を示せば良いってことだよな?いいさ、じゃあ、やってやる。使い魔と勝負させろや!」
俺は、ありったけの気負いを声に乗せて啖呵を切った。
「そう。マスターの客人とはいえ、決闘による覚悟の上での不慮の死なら問題はないわね。ありがたく、その心臓を賞味してあげるわ。
セーレ、ここに現れ、この者と戦え。万が一この者に敗れるときがあらば、その力、誰にも負けぬ『速さ』をこの者に貸し与えること、我が認る」
禿げあがった頭の小太りの男、いや魔人が現れた。
「仰せのままに、ご主人様。しかしこの人間を倒してもよろしいのでしょうな?フリではなくて、本気でやらせて頂きますよ。あとで、罰を受けるとか無しにしてくださいね。
うほん、お初にお目に掛かります。私はセーレ、魔界一の速さで知られた者。日頃のうっ憤晴らしに付き合っていただこう!」
いきなり、魔人かよ。たかが、使い魔とあなどっていたが館の庭で戦うような相手じゃないだろうにと思っていたら、いつの間にかセーレと俺、そして下僕一号は荒涼とした岩だらけの平地に移動していた。
「心置きなく戦えるようにサービスですわ、お客様。これが最後になると思いますわ」
使い魔との決闘に際して、審判役の下僕一号が気を利かしてどこだかわからないが荒れ野にご招待してくれたという訳だ。
「まあ、やってやる。こんな所でくたばっていたら、兆利人になどには成れないのだから。そう、仮想通貨で俺は兆利人になる!」
<<前話 次話>>
目 次
投稿者の人気記事




Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

SASUKEオーディションに出た時の話

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

バターをつくってみた
