

56 骸骨

南西に位置するユスキュー大陸を支配しているのは、マサツ帝国だった。帝国は精強な軍隊を持ち大陸内の周辺諸国を属国としていた。
その属国の一つ、アヒュー王国が大陸の南部一帯を治めていた。アヒュー王国の主な産業は漁業と伝統的な陶磁器の生産だった。
だが最近はアヒュー王国の主要産業である漁業は低迷の一途を辿っていた。大陸付近の天候不順、海流の変化等様々な要因が重なり漁獲高が激減した。(ただし、この分析は科学的なものではなく、漁村の長老が確か自分の若い頃にもこういう不漁の時期があったなあという正に老人の知恵に基づくものであった。)そこに帝国の増税を受けてアヒュー王国は、更に上乗せして領民に重い税を課した。
このため、長く続く不漁と帝国の税率引上げによりアヒュー王国の財政状況は悪化しつつあった。
一方ユスキュー大陸の更に南に位置するナッキオ群島では数年ぶりの豊漁を迎えていた。また、ナッキオ群島を支配するハナ王国は第二王子の献策を入れ物々交換主体から仮想通貨イージェイ(EJ)主体の経済に移行していたため流通の改善、新技術の導入等により漁師の暮らし向きはアヒュー王国と比べると雲泥の差となっていた。
なりふり構って居られなくなったのか、はたまたハナ王国を妬んでなのか、アヒュー王国の漁師たちは更なる豊富な漁場を求めてハナ王国の支配するナッキオ群島周辺にまで出漁するようになっていた。当然、自らの縄張りを侵されたハナ王国側からはアヒュー王国へ強い苦情の申し入れやがあったが聞き入れられず。ついにアヒュー王国の船に対するハナ王国の軍船による警告や取り締まりがエスカレートしてアヒュー王国漁船の拿捕等にまで発展していった。
そんなある日のこと、アヒュー王国の将軍の元にある男が面会を求めてきた。腕には小さな女の子と抱えていた。いや、それは物言わぬ人形だった。
身長五十センチくらいの金髪碧眼のビスクドールを抱えて将軍に面会を求めて来た怪しい男は、何故か警備の者たちにも不審がられずに将軍と短い要談を終わらせていた。
男が向かったのは船着き場だった。そこには軍船が一隻停泊していた。男は警戒に当たっていた水夫に丸めていた羊皮紙を渡すと船長室に案内されていった。
暫くして船長は独り寂しくその任を解かれ少ない荷物を持って船を降りて行った。
ナッキオ群島の北部に位置する島周辺で、漁を行っていた船が沈められるという事件が何件も発生していた。生き残った漁師の証言では、おんぼろの船がいつの間にか現れて何も言わずに大砲で攻撃してきて、必死で網を切り離して逃げたが沈められてしまった。悔しい俺たち漁師に何の恨みがあるんだと涙ながらに死んでいった者たちの代弁をしていた。
既にナッキオ群島の漁師にとって、おんぼろ船は死と同義語であった。
元軍船の上ではアヒュー王国の国旗は既に外され、血を滴らせた髑髏の旗が替わりに風にはためいていた。船名もドルフィン号から、ペンタクルス号に毒々しい血の赤で塗り替えられたいた。
ペンタクルス号の船長、Jは己の部下となった船員に対して訓示を行っていた。
「いいな、奴らに情けを掛けるなよ。鼻ったれ野郎の漁船は全て沈めろ。もし、鼻ったれ野郎の軍船が出しゃばって気と時は、おい、お前!どうする、鼻ったれ野郎の軍船が出てきたら、ええ?答えろ!」
「はい、大砲で沈めます」
「そうだ、鼻ったれ野郎は漁船だろうが、軍船だろうが撃って、沈めてしまえ!これがペンタクルス号のドクトリンだ。覚えとけよみんな」
「おう!」
船の部屋の中で一番の部屋で独り高級な酒を飲みながら寛ぐJ。
「まあ、今日の訓示は良かったわよ、J。あなたにしてはね、軍事経典《ドクトリン》を語るとか成長したものよね。あのチーム杖《ワンド》にいた頃とは大違いね」
「抜かせ、アスタロト。俺はKごときとは器が違うんだ、そう、今じゃ恐怖の海賊船、ペンタクルス号の船長J様なんだよ、俺は!」
ペンタクルス号は、見た目は古いオンボロの船に偽装されていたが中身はアヒュー王国としては最新の軍船だった。攻撃装備も最新式の大砲を左右に六門づつ装備しており、その速度も一級品で並みの軍船では追いつけないほどだ。
ハナ王国の漁船はおろか軍船でさえも、ペンタクルス号を目にした瞬間全速力で逃げ出す始末なため、Jが増長するのも無理の無い話だった。
「まあ、せいぜい楽しむのね。今は一度きりしか無いのだから。忠告はしたわよ」
「へん、心配するなって。このJ様に任せておきなって」
青い瞳に妖しく夕陽を映して、アスタロトは薄く微笑む。
<<前話 次話>>
目 次
今週のピックアップw
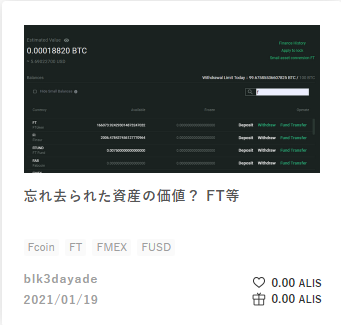
投稿者の人気記事




警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

無料案内所という職業

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

京都のきーひん、神戸のこーへん

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。
