

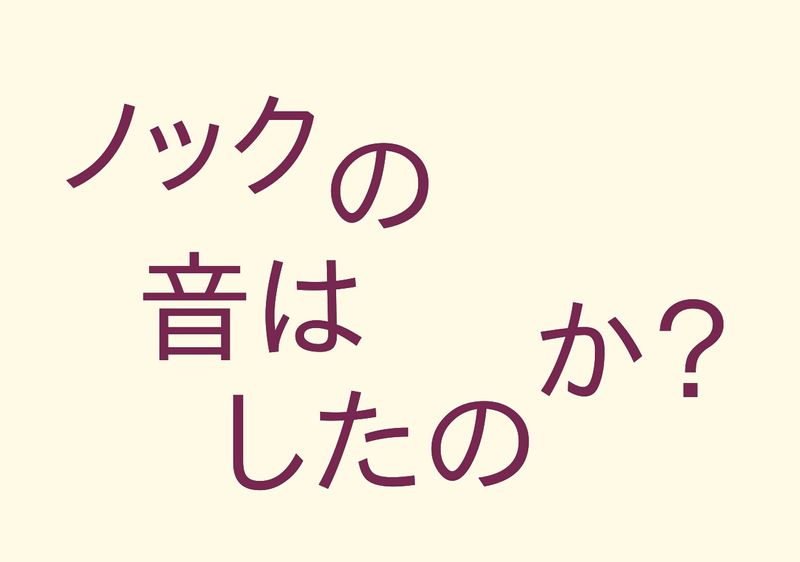
[3 - 4 分で読めます]
ノックの音がした。
ここは、大都市の郊外にある田舎街で、おんぼろアパートの一室に、青年は住んでいた。とんとん、とん、と三回強めに叩かれたノックの音で、青年は目が覚めたのだった。まだ室内は暗い。窓から入ってくるカーテン越しの街灯の光に照らされる枕元の時計を見ると、針は四時を少し回ったところだった。
こんな時間に誰だろう……。誰かのいたずらだろうか。青年は、ねぼけた頭でそんなふうに考えながら、布団の中で伸びをした。六畳と三畳の和室に小さな台所と手洗いがついただけのアパートの、ずいぶんくたびれた入り口の扉のほうを、布団の中からうかがったが、特に人の気配は感じられなかった。
本当にノックの音だったのだろうか。しんと静まり返った夜の街の静寂に包まれていると、さっき確かに聞いたと思ったノックの音が、本当にしたのかどうか、だんだんと曖昧なものに思えていった。
何か別の物音を聞き違えたのかもしれない。それとも、そもそも音などしなかったということだって考えられる。青年は、とてもリアルな夢を見ることがあった。夢の中で自分の部屋で寝ていて、体が浮き上がり始め、なんとか止めようと必死になって、はっと気がつくと目が覚めている。ついこの間も、そんな夢を見たばかりだった。ノックの音と思ったのは、夢の中で聞いた何かの音だったのかもしれない。
そんなことをぼんやり思っていると、扉のほうで、何かが擦れるような音がした。青年は、緊張して体がほてるのを感じた。誰かが、あるいは何かが扉の外にいるのだ。
青年は布団の中で上体を起こし、ほかに何か音が聞こえないかと意識を集中した。呼吸に気をつけ、ゆっくり吸って、ゆっくり吐いて、肩の力を抜くように心がけながら耳を澄ませた。けれど、冷蔵庫のモーターがたまについたり消えたりする音以外は、時折り、遠くの街道を走るトラックの音が響いてくるだけで、入り口の外で何ものかが音を立てることはなかった。
風でも吹いて、何か音がしただけだったのだろうか。いや、それほど風が強いようには思えない。犬か猫でも? それだったらもう少しがさごそと音がしてもよさそうだ。あるいは、まったくの空耳だったのかもしれない。こんな未明の時間に目が覚めて、意識の状態も少し普段とは違うのだろう。過敏な神経がありもしない音を創り出してしまうことなど、よくあることに違いない。
すると今度は、扉の向こうから、短いうめき声のようなものが聞こえた。人だろうか。それともやはり猫? 青年は布団を抜け出すと、ゆっくりと入り口の扉に近づいていった。扉の前に立って、その向こう側をうかがう青年の手は、緊張で汗ばんでいた。酔っぱらいでも倒れているのだろうかと考えたが、何か得体の知れないものが、夜の闇の中に潜んでいるような気がして、青年は声をかけてみることも、扉を開けることもできなかった。
勇気を持って扉を開いてしまえば……。多分そこには何もおかしなものなどないに違いない。空耳か、それとも野良猫か何かの仕業で、とにかく、何も恐がるほどのものなど、ありはしないのだ。
理性の声は、青年にそう自分に説明したが、青年の中で落ち着きを失った小さな獣は、そんな理屈付けを聞く耳など持たなかった。
扉の外は、まだ闇だ。闇の中にはどんな怪物が潜んでいるかわからない。迂闊に開ければ命を落とすぞ。化け物に魂をさらわれて、もうここに戻ってくることはできなくなってしまうぞ。
そんな話は漫画や映画の中だけの話だと、青年は思っていたはずなのに、なぜか今は、扉を開けると、本当にそうした邪悪な力がこのアパートに入り込んできて、取り返しのつかないことが起こってしまう、そんな想像を抑えることができなかった。左の額を汗が一筋流れた。
青年はゆっくりと深い呼吸を繰り返し、肩から両腕にかけての力を抜いた。そして、青年は呪(まじな)いを使うことにした。
ノックの音はしなかった。
そうだ、ノックの音など初めからしなかったのだ。夢の意識と過敏な神経が創り出した、実際にはありもしなかった音の正体など突き止める必要はない。そのことはもう忘れて、布団の中に戻ってもう少しゆっくりしよう。
それが自分の弱さからくる言い訳に過ぎないことに、自分自身、気づいてはいたが、青年はその弱さを許すことにした。今はまだ力が足りないのだ。力が足りないのに無理に恐怖と向き合うことはない。きちんと力を蓄えて、次の機会には化け物の正体を見極めればいいのだ。
青年はそう決め込むと六畳間に戻り、布団にもぐり込んだ。心臓はまだどきどきしていたが、ゆっくりと深呼吸を繰り返す。そうやって、魔物の時間が過ぎ去っていくのをじっくりと待つことにした。もうじきだ。もうじき、東の空が白んで、逢魔が時も終わりを告げるのだ。
[星新一氏の短篇集『ノックの音が』へのオマージュ作品です]
---
とし兵衛@投げ銭作家
投稿者の人気記事




iOS15 配信開始!!

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

「もののけ姫」着想の地であり魑魅魍魎の最後の砦 知られざる京都洛北・志明院へ

解剖学から考えるグラップラー刃牙の必殺技:三半規管破壊

「鬼滅の刃」の主人公は炭治郎ではなく、盲目/隻腕/両足義足のキャラだった【編集者の仕事ぶりに脱帽】

装甲騎兵ボトムズ 塩山キリコと谷口キリコの違い

初投稿です🌱|発売まで@1か月|ワクワクがとまらないFF14パッチ6.0

「キラ様…」『DEATH NOTE(デスノート)』📖の最終話で祈りを捧げる女性は誰なのか

かわいいキャラクターの作り方

ジャンプ+掲載の画像使っていいか念のため聞いてみた件と電車で読みたい漫画4選

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして
