

鮮干煇(韓国)「背面」
卫慧(中国)「上海ベイビー」
村上春樹(日本)「風の歌を聴け」
宮本輝(日本)「星々の悲しみ」
が、最終候補に残った。
どれも捨てがたいし、時節柄は「背面」に触れたい気持ちは強かった。
いきなりでしたが、この件です。
そもそもの、はるか先生の企画。
それにしても何千冊、もしかすると万を越える本の中から残ったのはすべてアジアの現代小説というのはいかがなものだろうか。
数々の経典・禅籍や聖書よりも
老子の「道徳経」よりも
親鸞の「歎異抄」よりも
タゴールやランボーの詩よりも
小説を選ぶのか。
そしてその小説において
デュラスの「ラマン」よりも
ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」よりも
アジアの小説を選ぶのか。
そうなのか。
最も自由で何をしてもいい文学の形式はやはり小説だと思っているのだな。
詩を小説として書いてもいいとすら思っているのだな。
だから、こんなものを書けたら、死んでもいいと思えるような書物は
経典でもなく、詩でもなく、小説なのだな。
そして、僕が最終的に選んだのは、宮本輝の「星々の悲しみ」だった。
「錦繍」も捨てがたい。
だが、初めの一字から終わりの一字までぴたりとくるのは、「星々の悲しみ」だと思った。

と思って開いてみると、若い僕はこの小説を推敲してしまっているのが、笑える。
まあ、ノーベル文学賞の川端康成の「伊豆の踊子」も推敲してしまっているのだから、むべなるかな。
しかも、今読んでも、僕の推敲の方がいいと思う。(笑)
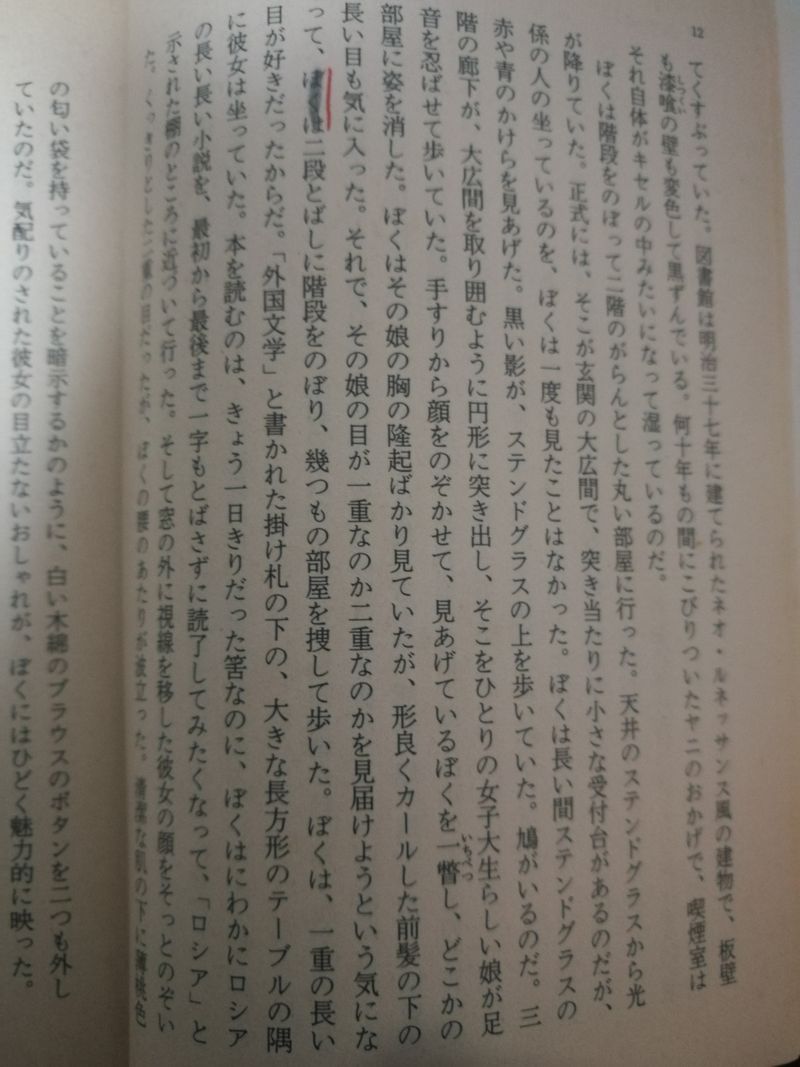
この「僕は」は、いらない。
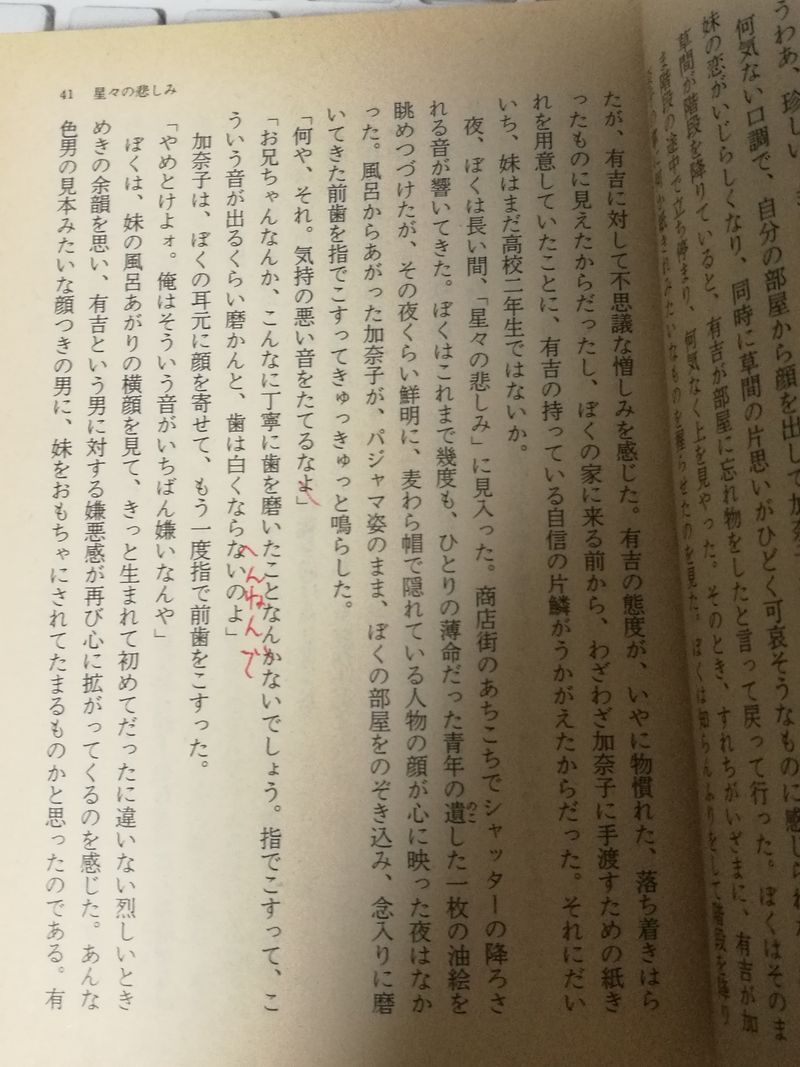
こんなん、大阪弁になってへん。
けれども、今はどうでもいい。
この小説の前半、有吉と草間に出会ったシーンでなにげなく投げた石ころが牛乳瓶に「ホールインワン」するシーンは、
小説の初めから終わりまでずっと全宇宙が、今ここに集約している文体であることを表している。
三島由紀夫は「文章読本」で森鴎外の「寒山拾得」の中の「水が来た」という一文をほめちぎる。
細かくは覚えていないが、一〇代の時のあえかな記憶では、三島は森鴎外の文体はすべてが宇宙の中で今ここでそれが起こっていることを表現していると言いたいのだと思った覚えがある。
しかし、そのときの僕は「ふーん」と拝聴しながらも、本当はそこまでのものだとは思わなかった。
そこまでのものだと小説の描写で思ったのは、志賀直哉の「城之崎にて」と宮本輝の「星々の悲しみ」だけだ。
喫茶「じゃこう」に飾ってあった二十歳で夭折した絵描きの「星々の悲しみ」と題された絵。
その絵の描写を初めて読んだときから僕はそれがジョン・レノンの最初のソロアルバム「ジョンの魂」のレコードジャケットと重なって仕方ない。
葉の繁った大木の下で少年がひとり眠っていた。
そこには膝枕をしているヨーコがいるところは違う。
けれども、すでにこの時、10年後には射殺されることを知っていたのだ、宇宙的には決定していたのだという感覚が、僕を打つ。

牛乳瓶に石ころが命中し、三人が出会ったとき。
まだ何ものでもない予備校生であるこの仲間の最も優秀なひとりが死んでしまうことは、もう宇宙的に決定していたのだ。
離婚してからもう何年も会っていない娘がまだ6歳のころ、沖縄の家族旅行で、ホテルの縁日の出店で投げたダーツが吸い込まれるようにど真ん中にあたって一等賞の賞品を得たとき
家の近所のゲームセンターで息子にぬいぐるみをとってやるために僕が操作したUFOキャッチャーが一度にふたつのぬいぐるみをつかんで取り出し口に運んで、周囲にいたギャルたちまで大騒ぎしたとき
家族そろって最初で最後に行ったコンサートで何千かの観客の中に降った紙吹雪の一枚を受け止めた息子がその紙を開くと、ただ一枚だけ、楽屋でユーミンに会って記念撮影をする「当たり券」で親子四人でユーミンと写真を撮ったとき、
僕らの家族はもうバラバラになることが宇宙的に決定していたのだ。
(以上は、あび自身の回想)
死ぬ前の有吉に病室で最後に会った次のシーンは、あまりにも秀逸だ。
俺は犬猫以下の人間やと有吉が呟いたとき、ぼくは烈しい恐怖と憂愁に、夕暮れのかなたから手招きされているような気持ちに包まれたのだった。逃れようのない決定的な絶望に勝つためには、人間は祈るしかない筈だった。僕が立ち上がったのは帰るためだと有吉は思ったらしく、初めて顔を向けて、
「またな」
と言った。僕がぼんやり立ちつくしていると、有吉はもう一度、
「またな」
と言って、笑った。
これが生と死の間に見えない風が吹き抜けた瞬間でなくて、なんであろう。
小説が始まってすぐ、風が競馬予想紙を吹き飛ばし、トラックの見知らぬ運転手と何度も目があう中で、「ぼく」はこう述懐している。
そのとき、むしょうに、ぼくは現実的でないもの、遠い世界のもの、心ときめくもの、しかも嘘いつわりのないものの中にひたり込んで行きたくなったのだった。
それが成就したのが、この病室のシーンだろう。
そして小説のラストで、いったん盗んだ絵「星々の悲しみ」を返すことに成功した夜明け、「ぼく」はこの有吉の「またな」を決定的な想いとともに思い起こす。
有吉は笑って「またな」と言ったのだった。だからぼくは思った。もしかしたら、薄命の画家が「星々の悲しみ」の中にはめ込もうとして果たせなかったものを、さらにはこれまで読みふけった百数十篇の小説が、語ろうとしてついに語れなかったところのものを、ぼくはあの瞬間に、かすかに垣間見たのではなかったかと。
小説は唐突にそれで終わり、いったい何のこと?と思う人には不親切ですらあるかもしれない。
しかし、僕にはこれで十分だ。
逆にこれ以上語ることは許されない。
これ以上語る文章が欲しければ別の本を選んだだろう。
僕はウィリアム・ジェイムズの「宗教的経験の諸相」すら選ぶことができたのだ。
投稿者の人気記事




バターをつくってみた

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

無料案内所という職業

京都のきーひん、神戸のこーへん

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

SASUKEオーディションに出た時の話

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話
