

大街さん企画のALIS夏の読書感想文に滑り込み参加です。今日は8月31日!
『震美術論』評 夏の現代アート雑感

マジ書きする。
実のところ、2年前に刊行されて以来、何度読んでもよく分からない本だと思っていた。いまでもよく分からないところが結構ある。けれども、ようやくまとめて書けそうなことが出てきた気がするので、この機会にメモ書きする。
またこの感想文はしばしば『震美術論』を離れて雑感的になるけれど、できれば普段あまり馴染みがない人にも現代美術の概況を説明してみたいという思いもあったりもする。
『震美術論』は、美術批評家、椹木野衣が311の震災以降、現代美術にとって課題となるものは何かをテーマにして『美術手帖』紙上で書いてきた論評をまとめた本だ。書籍の帯には「新たな美術史を紡ぎだす、画期的美術評論」とある。何が新しい美術史かはまだ自分には分からない。
椹木野衣は日本現代美術の中心的な批評家だ。ローゼンバーグやグリンバーグが抽象表現主義にとって決定的な評論家であるように、椹木がキュレーションを務めた「日本ゼロ年展」(1999年)が、以降の日本の現代美術にとって最も重要な展覧会になる。それは前年に彼が刊行した『日本・現代・美術』での主張を裏書きする展覧会でもある。
会田誠、大竹伸朗、小谷元彦、村上隆、ヤノベケンジ、できやよいほか主要な日本の現代美術家を集め、それに岡本太郎、横尾忠則、東松照明など戦後に重要な芸術家を加えたうえで、ゴダールの『ドイツ零年』のタイトルをもじったこの展覧会で、彼は「日本の現代美術をリセットする」を宣言した。
リセットといっても、美術界や画壇を解体するとか、そういうことではない。むしろ日本の現代美術にはさしたる伝統もなく、理解もされず観客も呼べず、画壇には正直権威なんてない、というか画壇なんてまともに成立していない。そんなものに反抗したりしても意味がない。もっと現実的でアクチュアルな課題があるだろう?それを問うていこうじゃないか。それが「リセット」の意味だ。
『震美術論』もまた、未曽有の被害をもたらし日本社会に決定的な打撃を与えたあの震災について、また今後も予想される天災、災害、被害に対して、これら現実的でアクチュアルな課題に対して、「現代美術はいったい何が出来るのか?」を問いかけるものになる。『日本・現代・美術』で提起された課題の延長上に本書はある。
現代美術というと、何かわけがわからないものとか、反芸術といった抽象的な概念を振り回す専門家の遊戯といったイメージがあるかもしれない。でも今やそれはかなり実際とは異なる。
近年になって現代美術はかなりの活況を呈している。ちょうどいま第四回が開催されている、瀬戸内の辺鄙な島々をめぐる瀬戸内国際芸術祭はのべ100万人以上を動員し、神戸の六甲山中で開かれる六甲ミーツ・アート芸術散歩も40万人に及ぶ。7年前に開かれた会田誠の「天才でごめんさい」展はのべ50万人近くを動員した。
或いは、人によってはオタク文化や消費文化との接近を見て取るかもしれない。多くの人が村上隆のポップアートや2004年のヴェネチア・ビエンナーレ建築展の「おたく部屋」を思い浮かべるかもしれない。
しかしながら、現代美術の「聖地」直島とオタクの「聖地」秋葉原とでは互いにまったく異質としか言いようがない光景が繰り広げられている。同じ国内にありながら、互いにあまりにも参照することがないこの状態について、僕はいつも不可解に思っているし思うところもあるけれど、とりあえずまったく状況は異なっているということだけは書いておく。
『震美術論』には、2人の人物が登場する。一人はリアスアーク美術館の学芸員、山内宏泰氏。もう一人は在野の歴史家、飯沼勇義氏。どちらも震災前に津波被害を訴える展覧会を企画したり災害を予言する研究書を出版したにもかかわらず、殆ど無視されてきた人物だ。
彼らの紹介を通じて椹木が問いたいのは、「文化、芸術はいったい震災に対して何が出来るのか?」だ。はたして、予測や被害の訴えに効果はあるのか?また被災の追悼にはどれほどの意味があるのか?
たとえば夏のこの時期に、広島や長崎や、また戦争の惨禍を訴え平和を祈念するセレモニーやイベントが数多く催される。年々、戦争の記憶は薄らいでいくと言われるが、事実、長崎の原爆資料館などは新設されてから随分と情緒的で演出的なもの、直接の記録からはやや離れた物語的なものになった。
かつての長崎原爆資料館(国際文化会館)は地下1階、地上6階建ての規模(展示は2~5階)を持ち、延々悲惨極まる被害の実物や写真の展示を見学した挙句に、最上階で被災者である丸木夫妻による巨大な「原爆の図」と対面するという、見学者を心底打ちのめしてあまりある施設だった。
現在の資料館は実物展示も組み込まれているものの、暗くスポットされた浦上天主堂の再現模型ほか、演出的な再現が中心で、最後に核廃絶に向けた各国の取り組みへと続く。
その是非はともかく、現在の資料館はおどろおどろしくはあるものの随分と情緒的であっさりしている。祈念的な色合いが強く、悪く言えば模型が並ぶ映画のセットか、ひょっとするとこの場所の意味を知らなければただのお化け屋敷のようにも見えるかもしれない。勿論、これはこれで訴求力があるという意見があるということも一応付記しておく。
これは東北震災にひきくらべるなら、先人達が被害の辛苦を「ここから下に家を建てるな」と石碑に血文字の如くに刻み込んだにもかかわらず、いつのまにか趣のある歴史遺産になっていた、というような話を思い起こさせる。
歴史によって物語化された表現は、どこまで力を持っているのか?
これに抗するものは、例えばかつての長崎原爆資料館のような、剥き出しの被害の実物なのだろうか?同様に、震災の瓦礫以上に雄弁に語りかける資料は存在するのだろうか?本書で取り上げられているリアスアーク美術館の取り組みは、たとえばそういう震災のリアルタイムを、混乱したさまを含めてそのまま展示するという試みだ。
椹木は「もの派」を援用しながら、被災物そのものがもっている息遣いをいかに取り扱うかについて、長々と、そして慎重に論じる。かなり迷っている手つきも感じるここらへんの論考は、繰り返しも多く、行きつ戻りつ再帰をしながら遠慮がちに展開されていく。
僕が本書についてどうもわかりにくい、何度読んでもよくわからないと思うのはこのくだりになる。言ってることはわかるが、理解ができない。具体的な感覚としてどうも理解することができない。
改めて整理するが、表現は悲惨であれば、劇的であればいいという話では勿論ない。だが、留意しなければならないのは、事物をそのまま投げ出せば、記録をそのまますればいいという話でも実はない。アーティストという主体とその想像力はどこに働いているのか?という課題が残っているからだ。
僕は、たとえばいま夏期開催中の瀬戸内国際芸術祭について思い起こす。国内でほぼ最大級の現代美術のイベントであるこの芸術祭に、初回から割と長い日数を費やして僕はこれまで通ってきた。残念ながらこの夏は訪ねることが出来なかったのだけれど、これまでの大雑把な印象をまとめて述べてみると、現代美術は記念碑になりたがっているのか?になる。
現代美術がタブロー(平面画)から飛び出して、その場、その空間での体験を重視するインスタレーションを主軸とするようになってからもうずいぶんと長い年月が経つ。瀬戸内国際をはじめ各地で町興しを絡めて行われる現代美術のイベントは、そうした「その場にいかないと意味がない」インスタレーション的な建造物や制作物が中心になっている。
その土地、その場所、その生活、その歴史、これに寄り沿ったインスタレーション。「祈り」だったり「記憶」だったりがしばしば主題になるが、これは要するに地蔵とか石碑とか、または盆踊りとか地鎮祭とか、どうもそういうものと同じなのではなかろうか?或いは無邪気に接近し過ぎてないだろうか?こういう感想を僕はずっと抱いてきた。
勿論、仏像や凱旋門などの記念的造形物は古典伝統的な「アート」ではある。祭りもまた無形文化財に指定されたりするだろう。それが現代美術の役割か?という疑念はさておくとして。
ところで芸術祭の舞台となっている瀬戸内の島々は非常にバラエティに富んでいて、廃鉱の島だったり鬼ヶ島伝説の舞台だったりとそれぞれどこも固有の歴史や表情に満ち、訪れる人を驚かせたり愉しませたりする。
ひとつ非常に印象に残るのは、高松沖の大島が芸術祭の舞台に入っていることだ。大島はハンセン氏病の隔離病棟の島である。眩暈がするような過酷な差別や国の隔離政策といった非業の歴史を思うとき、この島が背負っているものは極めて重い。
勿論、それぞれの歴史に軽重などはない。しかしながら、島に降り立った人は痛感するだろうと思う。高台に建つ納骨堂や現在も海辺に立ち並ぶ住居棟以上に、雄弁に歴史を語るものはない。この島には芸術祭以前から橋本清孝による石積みの墓碑『風の舞』が立っている。
一方で大島の北に浮かぶ豊島には、クリスチャン・ボルタンスキーによる『心臓音のアーカイブ』という建物が建っている。芸術祭の作品のうちの一つだ。ひと気のない海辺にひっそりと建つこの場所で、訪れる人々は記録された心臓の音を聞くことができる。また自分の心臓音を記録していくこともできる。


ここは、ここを訪ねた人々の生きた証、に耳を傾ける場所、つまりはこれもまたある種の墓標である。僕もこの場所に心臓音を記録していったが、絵に描いたように美しく静かなこの浜辺に、自分が生きた証が残っていくことにとてつもない充足を覚えながら、記録機に身をゆだねた。いつか訪れる生の終わりを思いながら、ここに長く残っていくだろう建物の姿をぼんやり思い浮かべながら過ごす場所だ。
しかしながら、考えてみれば数度しか訪れたことのない瀬戸内の島に自分の墓標を立てる意味はそれほどない。僕が馴染んでいて、日々悪戦苦闘しているのはうんざりするほどのビルと雑踏がひしめている都会の街だからだ。
それは、大島にあった墓標とあまりにも対称をなしている。豊島のアーカイブは大島を臨む海に向いて建てられてはいない。一方、病棟の並ぶ大島にあるのは、死後はせめて縛りつけられてきたこの島を離れ、風のように自由になればいい、との願いで建てられている『風の舞』なのだ。大島に心臓音のアーカイブを建てることは出来ない。僕にはそこに記録を残していく資格がない。
どちらが良い、悪いという話ではない。『心臓音のアーカイブ』が成立するのは、その場所が誰もが思い描くような風光明媚で、ある種抽象的な場所だからであり、またアーティストの想像力が勝った結果である。
芸術祭の作品は、またインスタレーションという作業は、それまで何もなかった野原や田畑にとつぜんモニュメントを打ち立てるという、悪く言えばでっちあげでもあり、観念抽象的な歴史やヴィジョンをその場に描きこむ作業でもある。それぞれのアーティストは真摯に土地や空間や歴史やに対峙し、作品を生み出してくる。
だが、この場合に「勝てる場所と勝てない場所がある」という、どこか底意地の悪い感触が、たとえば大島と豊島とを対峙させたときには出てきてしまう。これは別に芸術は及ばないとか勝てないとかいう意味ではない。大島にある『風の舞』もまた現代アーティストによるひとつの作品だからだ。そうではなくて、二つの場所を並べたときに出てくる、言いようのない断絶を埋める言葉がうまく見つからない。
アーティストの主体性や想像力はどこに、どこまで及ぶものなのか?勿論、これは芸術祭でも果敢に大島でも取り組まれていた課題ではあるけれど。
続いて本書では磯崎新の幻となった水上都市計画などに触れながら、「新しい神話的想像力」について語るところへと進む。
村上隆の『五百羅漢図』や藤田嗣治の『アッツ島玉砕図』ほか戦争画について、そこに破滅の音を聞き取りながら語られる、この「神話的想像力」とは、つまるところ危地を察知するカナリアとか、大災害の前に現れる件(くだん)とか、審判の日の前に予告ラッパを吹き鳴らす天使とか、そのあたりの能力のことである。
もしくは、これを超えて、または踏まえて新しいビジョンを提示する想像力のこと、この場合はベツレヘムの星だということだが、こんなわかったようなわからないような超自然的な例えでしか僕が感想を言えないのは、磯崎新の都市計画をはじめ、これらは実現しなかった幻だったからだ。まだ誰も実現を見たことはない。
もしくは僕が基本的にはわかっていないからだ。『震美術論』は、僕にとっておとぎ話とか、神話上の預言とか、そんな感触からやはりまだ離れない。「勝てる場所と勝てない場所がある」いつまでも疑問が頭の上を離れない。
僕は具体的な像を、手つきを、さまざまな作品の中にこれから探していかなければならない。
あらためて本書について感想文を書こうと思うきっかけとなったのは、だいたい想像がつくかもしれないけれど、この夏に愛知トリエンナーレで起こった「表現の不自由展」をめぐる騒動による。
あまり詳細しないけれど、税金で運営されているのにけしからん、なんてのは論にならない。たとえば選挙は税金で運営されているが、だからといって必ず国政与党に投票しなければならないということはない。求められる行政の中立性や公正性とは、選挙管理委員会の公正のことであって、候補者や投票者の立場を意味しない。
そんな原則論はともかく、もうひとつ、この騒動はあらためて僕にとっては「勝てる場所と勝てない場所がある」という問題意識を呼び起こさせるきっかけになった。
たとえば最も話題を呼んだ、というより一番揉め事の焦点となったらしい『平和の少女像』は、それ自体はただ朝鮮の少女が民族衣装を着て座っている像に過ぎない。
実際、各種のメディアは『平和の少女像』そのものを特にモザイクにしたり墨塗したりのプレスコードにひっかけることなくそのまま報道してきたし、だからこの像がどんなものであるかということをみんな知っている。
事実上、どこにもプレスコードや表現規制にひっかかるところがないにも関わらず、しかし芸術展に出すといきなり問題化するというかなり不思議な始末で、正直寝耳に水、みたいな騒動だった。
要するに政治的駆け引きや争いの前に、表現力やアーティストの主体性や想像力などまるで及ばない、「勝てる場所ではない」というわかりやすい事例にほかならない。主題や、物語や、こめられた言葉の上での意味合いばかり、つまりはタイトルばかりが重要であって、その是非をめぐって延々騒動が繰り広げられている。
仮にこの像に「馬鹿な女」とでもタイトルづけて展示していれば批判者は留飲を下げ喝采したのか、というようなことを考えてみると、作品がその固有の創造力で及ぶ範囲というのはどこまでなのか、という問いを改めてしてみないわけにはいかない。
歴史によって物語化された表現は、どこまで力を持っているのか?(もしくは危ういものではないのか?)と先に掲げた問いはこのあたりから書き起こしている。
結局、また何か起こるたびに、本書を読み返すことになるんだろう。いつかわかるまで、納得するまで読み返すことになるんだろう。『震美術論』はそんな本だ。
投稿者の人気記事


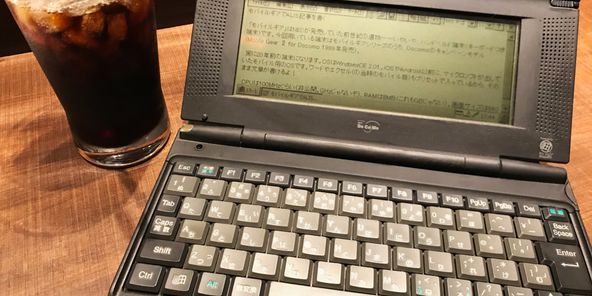

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

無料案内所という職業

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

わら人形を釘で打ち呪う 丑の刻参りは今も存在するのか? 京都最恐の貴船神社奥宮を調べた

京都のきーひん、神戸のこーへん

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

バターをつくってみた

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!
