

山沿いの竹林。
冬以外の季節は綺麗な竹のトンネルのように見えるが、
雪が積もる季節は、雪の重みで道の上にある竹はすべて積もった雪に倒されて車が通れない状況になるので、かなり邪魔扱いされている。
道が塞がれ竹を撤去している地区の役員の方は迷惑がっていた。
しかし、邪魔になった竹をただ切ってそこら辺に伏せておくよりは、
活用した人がいるならば、じゃんじゃん活用するに越したことないのではないかと思っていた。
そこでひらめいた。

以前、記事でも書かせていただいた、切り出してきて皮を剥き、車の廃油を塗ったニセアカシアの長い杭の出番。
竹との融合。
皮を剥き廃油を塗って数日しか経っておらず、浸透はいまいちだが、いてもたってもいられず使用した。

前から活用してみたいと思ってアマゾンで購入した竹割機を使用し、
四つ割りにした。
竹割機をある程度竹の断面の中心に当て、竹の先は安定感のある石などに当て、竹割機の持ち手の片方を手で握り、片方を中心かもう片方の手をかける部分をゴムハンマーで叩き、四つ割りにしまくった。



竹割り機を中心に当てたつもりでも割った竹の幅はバラバラ。

割った竹の内側の節部分が出っ張ってバリになっているため、
鉈を使ってある程度平らに節部分をそぎ落とし、
平たい竹素材をたくさん作った。

長い杭を大きなハンマーで打ち込み、垣根フェンスの組み立て作業。
奥には割った薪の山が見えている夕暮れ時。

竹の長さをもっと均等に切っておけばよかったと思うこともあったが、不揃いな竹の長さも手作り感が出てよいかも。


竹の表面の向きは同じだが、杭にジグザグに交差して編むよう段1ずつ段変えた。

二人で行う作業はかなり早い。
杭を打ち込んでからは竹を差し込んでいく作業はトータル30分程度だった気がしている。
紐や釘、ビスなどは一切使わず、竹と杭のみ。
厚みのある竹はある程度テンションが強めなので動きずらいが、薄い竹は少々緩め。
乾燥して痩せてくると動きやすくなると思ったので、厚いものと薄いものを交互に重ねるようにした。

はじめての池垣作り、思いつきで始めた作業もいつの間にか終了。
垣根フェンスを作るまでとは別世界。割った薪が遠目ではかなり見えにくくなった。

内側も遠目から見れば綺麗。
杭の長さのばらつきもちょっとしたアート作品を作った気分だと思えた。

道路から撮影。

思いつきから始まった今回の垣根プロジェクトは、これで終わらず、さらに作る予定。
風に耐えれるように杭を地中30センチ以上深く入れるにはどうしたらいいか、
スキーのストックを土に刺して石があるかどうか確認したり、その次は太目の鉄の棒を刺し、杭を打ち込む丁度よさそうな穴を広げたりと試行錯誤。
杭が長すぎるため、三脚に登った高い場所でバランスをとりながら重いハンマーを使用して打ち込んだり、それなりに大変な工程があったにせよ、
一つ一つの作業に集中して向き合えば、
さほど難しいことではなく、結果なんとか形になるもんだと思った。
身の回りにある活用できそうな様々な物、
ありがたく活用していきたい。
投稿者の人気記事




オランダ人が語る大麻大国のオランダ

SASUKEオーディションに出た時の話

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

バターをつくってみた

無料案内所という職業

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話
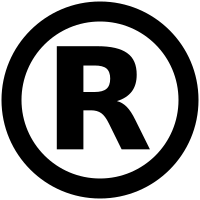
テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶
