

クオリアは一定の機構を備えてさえいればだれにでも観測可能なリアリティではなく、個人と世界とのあいだにそのつど新たに成立するアクチュアリティである(クオリアが個人と世界の界面現象として成立するという点は、のちの考察にとって重要である)
木村敏『関係としての自己』より※クオリア:意識的・主観的に感じたり経験したりする「質」のこと
自分に何かが起こるのは外側のものと出会った時だが、その時点では起きたことを消化できていない。無意識の部分に引っ掛かりとして、起こった感情と共に記録されている。起きたことを検証するのは時間が経った後、意識が内向きになっている時である。感情を手掛かりに意識に引っ張り上げて検証する。この消化までの一時的な保留は、他者も同じようにしているのかわからない。木村敏『関係としての自己』に出てくる統合失調症患者に共通する「自己の働きの弱さ」に、私は近しさを覚える。感情の理解し難さ以前に自分が自分であること(他者が他者であること)や個別に欲望を持つことは、非患者には自明で回顧もされない場合が多い。私の場合は自覚に言語化が必要で、しかも定期的に出力しないと別の引っ掛かりの検証に取り掛かれず生自体が停滞してしまう。自分がどんな人間であるかの内容はどうでもいいが、他者にとって当たり前のこと(欲望を持つことなど)を自分なりに理解しようとすることで、なんとか社会に対応してきたのかもしれない。前述の本では、有名な哲学者達による理論の解釈と、精神病理学者の著者が臨床で得た経験から進められてきた思索を通じて《私》の構造が丁寧に説明されている。まだ理解できていないのだが、初読では「複雑な私の在り方が立ち上がる根源部分では自他の別が無い」ということと「virtualという語句が示す意味の多重性」が印象に残った。
一人勝手に好きなようにできている時、社会的な私という意識はない。勝手に好きなようにと言っても、己の欲望の為に誰かを使役したり消耗させるような特別な状態ではなく、例えば人気のない道を自転車で飛ばしている時や、夕飯の支度をしている時、好きな本を再読している時など、日常的な状態である。社会的に無目的で居られる、わがままな時だ。社会における自らのふるまいの意識が頭から消えている状態の時、三人称的な私(客観的に説明し得る「これが私」というもの)は当人の意識にも存在せず、説明不能な現在進行形の私しかいない。私以外の存在を意識して初めて、社会的な私が意識され始める。他者を意識せず好き勝手にしている自分を動かす潜性的な私と、他者の存在と共に都度生じ、自省する時にも現れる社会的な私が存在し、意識はこの両方を行き来したり同時に捉えてみたり、状況に応じて使い分けている(無意識は平行して常に働き続ける)。意識が辿るところには、群れと私という軸もあるし(建前と本音)、種としての人間と私という軸もある(本能と理性)。群れを作り社会的に生きる猿は、複数の私を意識して生きている。同時に複数の私を意識しなければならない時、私の脳は疲労する。
個別に勝手に生きている状態においても、自分以外の世界を認識している。内容は器質の状態や感受性の種類や感度などにもよるが、時間軸に沿って生じる世界の変化と常に出会い続けており、変化に対応する形で、都度成立する私も生きている。さて、この個体において私を成立させる精神的な場それ自体は、個別の私と言えるだろうか。渡り鳥は個体毎には主に死なない為に、状況に応じて自分の判断で行動している筈だが、その結果集合的な一塊として長距離を規則的に飛ぶ。人間も合唱や合奏の際には《集合的な私》を感じ、他者が鳴らした音も自らの出した音と意識している。この「本能に引きずられた理性」や「建前と本音が一致した状況」とでも言えるような現象を思うに、私が立ち上がる場は、種全体と共有しているような気がしてくる。集合的無意識みたいなものにアクセスするような想像をせずとも、ほぼ同じ作りをした体を持ち(ほぼ同じ体で生きた結果ゆえに)ある程度理解し合える習慣、文化、風習を持つ人間という種のそれぞれの私は、状況に応じてふるまいは異なるが、仕組は同じと思われる。人間も群れを作る生物である以上本能的な機能は残っている筈であり、その仕組の一致が他者との共感も可能にしているのではないか。芸術に限らず表現とは、社会的な私に向かうものではなく、現在進行形で生まれ続ける私の意識を、立ち上がった場に向ける行為なのではないか。だからどれだけ異質な主観的私を持つ他者に対しても、共感や反感を起こし得るのではないかという気がしている。他者の主観的私は基本的には理解不能だし、社会的私の内容に興味がなくても、生きている限り私を生成し続ける場そのものを理解しようとしたり、逆にそこに刺激を与えようとすることは、結果的に他者の本質とも繋がることになるのではないか。
virtualという言葉を初めて意識したのは、ゲーセンで人気を博した「バーチャファイター」だった気がする。ネット上の空間をバーチャル・リアリティと呼び、その訳語として仮想現実があてられた。セカンドライフ的なゲームも流行ったし、映画『マトリックス』などを経てすっかり馴染みのある言葉になった。ゲームや映画から馴染んだこともあり、virtualと聞くと仮想とか、現物・実物ではない人工的な虚像というイメージがまず先に立つようになり、仮想通貨が通貨であるように、実質上の・本質のという意味を意識することはあまりなかった。木村氏の本を読んで、このもうひとつの意味を意識した時に思い出したのは、ジャミロクワイの『Virtual Insanity』だった。1996年にリリースされたこの曲は日本でもヒットし、思春期の私もカッコいい~と思った。だが歌詞の意味がよくわからず、曲名を仮想の狂気と訳して、人が頭の中で都合よく作った社会や、その社会に適用した人を「現実見てない人」として、皮肉ってるのかと漠然と思っていた。思春期~青年期に印象に残る曲はずっと覚えているもので、それから3年後の映画『ファイト・クラブ』のエンディングで流れるPixies『Where Is My Mind?』などもそうである。だがこの曲の場合は「自分の心を見失った状態を歌ってる」位で納得していたのに対し、仮想の狂気は納得し難く、わかった気にもなれずそのまま放置していた。だが実質の狂気だとしたら話が違ってきて、分裂した状態で生きている人間(ジャミロクワイ自身も含む)そのものや、そんな人間が作る社会も、その未来も実質は狂気からできてくるとしているのではないかと思った。狂気は混沌とした理解し難いものという意味で、否定的ではなくむしろそっちが本質だと歌っているのだ。virtual insanityとvirtual realityを対比する箇所もあるので、意識的なダブルミーニングとしてvirtualを使っているのではないか。ただ「地下に住む我々には何も聞こえない」という歌詞の解釈は、また謎を残す。本質は潜性的なもので即ち地下だが、本質には何も聞こえず無音だと言っているのか。それとも現実を見られない愚かな地上の私が吐く虚言が、一切聴こえないということなのか。「窓から叫べ」とも言っているが本音はどちらなのだろうか。ともあれvirtualの意味の多重性を意識したことで、前よりは理解に近づいた気はする。
社会的な私とは違い、他者にも自身にすら完全には窺い知れない私がいる。他者から見えない主観の私については、当人も意識した瞬間に説明できる形にされてしまうが、現在進行形の私そのものについては完全にはわからない。当人が予期せぬ事態においてどう行動したか、また理由のない謎の衝動に駆られて何かをした時などに、過去を振り返ってようやく一端が窺い知れるくらいのものである。だから興味深い。私の構造について知ると、天皇家の人など「公に象徴として生きる」とは究極的な不自然だと改めて思う。生まれにより社会的な私を他者に限定される不幸も想像できる。本来体の管理を任されたものとして、行動を自由に選択でき、望もうが望むまいが複数の違った未来を想像できる状態であらねばならない。私の在り方に自由がないと、精神的に疲弊していくばかりである。伝統や慣習という言葉を笠に思考放棄し、勝手に限定を強いる暴力性に怒りを覚える。何故野生動物を見るように他者を見られないのか。個々の主観的内面は異種との隔たりと同じ位違っているのだから、そこを一致させる必要は無い。互いに敵でないとさえ思えたら十分で、必要以上に干渉しないのがいい。そして他者と共有し得る本質的な場所に目を向けて、試行錯誤してたらいいのにと思う。それができる社会に住みたい。
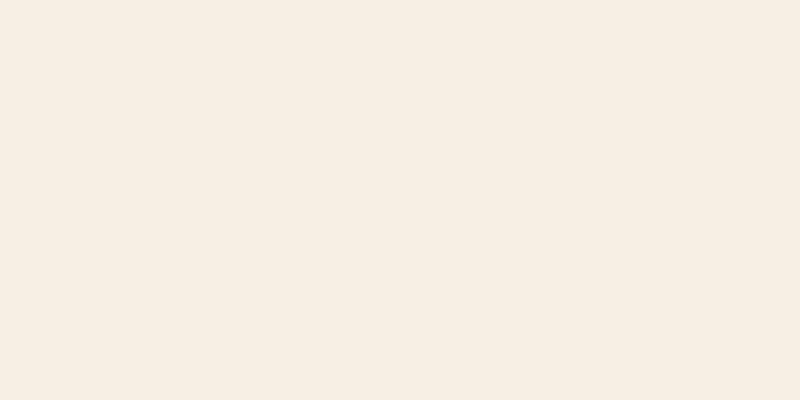

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

バターをつくってみた

Bitcoin史 〜0.00076ドルから6万ドルへの歩み〜

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】

京都のきーひん、神戸のこーへん

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

約2年間ブロックチェ-ンゲームをして

機械学習を体験してみよう!(難易度低)


