


ゆらゆらと揺れる真っ青な光と浮遊感。
出来損ないのカクテルのような人工の青色に浮かんでいた。
視覚は青い光、三半規管は浮遊感、それ以外の感覚はなかった。
自分がケイスという名前であることと、青い何かの中で浮かんでいる浮遊感。
透明なガラスの容器に満たされたブルーの液体。狭くもなく、さして広くもない空間。
次第に遠くから女性ボーカルの、低音で心地よく、頭蓋が震え、心がかき立てられる、歌声。
それが、キッチンにいつもおいてあった、あのアメリカンラジオから流れている音だと分かる。
あたたかな湯気の向こうのナオミの顔と、ホットケーキの甘い香り。
転瞬、バチリという音がして、痛みが走る。漏電していたコーヒーメーカに触れたときの感覚。
ケイスのすべての神経が一斉につながった。
映りの悪いブラウン管テレビが眼球にはめ込まれていた。見ようとするとノイズがいちいち邪魔をする。見えるようで見えない蜃気楼のように、周りの風景がぼんやりとしている。
青白い世界に写っているのは、白い壁に囲まれた一室。
時々入るノイズと、神経を逆なでするような、脊髄に走る痛み。
体は重かったが動かせる気がした。全身がボワンとふくれ、パンパンに腫れているように思える。
頭はベッドに固定されているのかまったく動かなかった。視界の隅に、口の辺りから何本ものチューブが伸びていた。
ケイスは固定されている何かを取ろうと右手を挙げようとしてみる。かすかにベッドの上で動いたと感じるだけで、その感覚はあまりにも遠いように思えた。
視界の範囲が限定され、ノイズのひどいモニター映像は、アンダーウォーター訓練で使われた、丸いフォルムの潜水服をケイスに思い出させる。
耐圧のために極端に視界を遮った丸い窓から見える海中。重い潜水服のせいで動きは鈍く、窓から見える視界は極端に制限されている。
あのときは重い潜水服の中から何とか手足を何とか動かすことができた。しかし、今は間接がロックされてしまったように動かすことができない。
しばらく、ぼんやりと全体を眺めていると、そこがガラスに囲まれ、いくつものモニターや点滴用のスタンドとチューブ、テーブルにのせられた医療器具に囲まれた病室だとわかってくる。
何かが、人形のような何かが、自分を見つめていることにケイスは気づいた。
ベッドに上体だけを少し持ち上げて固定されている。
頭はフルフェイスのヘルメットをかぶり、両耳のあたりには角のような物が生え、スキーのゴーグルのような目をしている。
茶褐色の皮膚と、人間をデフォルメして作られた彫刻のような体。
両手両足を投げ出して、頭だけでなく、まるで、内蔵を引き出されて、天井につるされているように、いくつものチューブが体から伸びている。
しばらく、その人形を見つめていると、ガラス張りの室内の右側が開き、桃色の看護服を着た女の子が入ってきた。その後ろから、軍服を着た細身の男。あごと目が細く、いかにも神経質そうだ。尖ったあごの上に、土気色の薄い唇。頬はこけて、シャープな印象だが、全体的に整いすぎていて嫌みな感じがする。
続いて入ってきたのは、黒のジャケットにタイトスカート、その上から白衣を羽織ったトンガリ眼鏡の女。長いまつげに装飾された切れ長の瞳、細いあご、厚い唇の下には小さなほくろが一つ。ジャケットの上からでもわかる細い肩と、眼を引く大きさの胸。年齢はケイスより上だ。十人の男が通り過ぎて、九人は振り返る美人だが、黒目の大きな瞳は、暗く湿っている。
軍服を見て安堵する。どうやら捕虜になっているわけではなさそうだ。西ドイツ軍のアーミー。
横から看護婦の姿が視界の隅に入ってきた。
看護婦が潜水服の丸い窓をのぞき込んできた。あどけない表情、まだ幼さの残る顔つき。
ノイズの多いモニターだが、なんとか良く見ようとする。一瞬だがノイズが薄くなり、看護婦に視界がクローズされたような気がした。
何とか声を出そうするが、まったく音が出てこない。声帯がごっそりなくなってしまったようだ。
看護婦がケイスの頭の辺りをのぞき込んでいる。ちょうど、開いた胸元が大きく視界の前来る。が、何かが足りない気がした。
次に大きな瞳が、ケイスのモニターをのぞき込む。長いまつげがパチクリと動くと、視界から外れ、右脇に添えてあるモニターへ向かう。そして、軍服と白衣の女に振り返り何かを伝える。
また、バチンと電気が走る。雑音混じりの音声がケイスの脳に伝わってくる。壊れかけたイヤフォンを耳にねじ込まれたような、不愉快な金属音が混じる。銀紙を噛んでしまった時のあの感覚。
「自我はあるのかね?ヴァレンティナ君」
と軍服。やはり、神経質そうな傲慢な高めの声。
「制御することは無理でした。もっとも、東と同じ方法を使えば別ですが」
ヴァレンティナと呼ばれた女。理知的な落ち着いた女の声。年齢もこの士官よりは上だろうと思う。ただ、この女も感情が欠落しているように聞こえる。
「私はそれでも良いんだがな」
「そうでしょうか?こちらですと色々と問題があるかと」
「君も人道主義かね?」
「事実を言っただけですわ。アイヒマン大佐」
大佐と呼ばれた制服の男が、とがったあごをなでた。ケイスから見ると、こちら側、西側の人間には見えない。カーテンの向こうからの亡命者か?
「先を越されてから、あのときやっていればでは遅いんだ。現に、例の化け物がチベット人を食い荒らしていると言うじゃないか」
自己を主張しだすと、だんだんと声が高くなるタイプだと、ケイスは思った。基本的に好きではないタイプ。
「制御できないなら、薬物(クスリ)でも素子(デバイス)でも使えばいい。」
相当嫌いなタイプとケイスは訂正した。さっきから自分のことを見る目が、物を見ているようなのも気にくわない。
「あの、繋げてみますか?」
ピンクの看護婦が、おずおずとしたこえで二人に聞く。舌っ足らずな甘えた声。幼そうなこの看護婦に動かない体をいじられていると思うと少し不安になる。
「前の被験者の時みたいにならんかね?」
アイヒマンと呼ばれる大佐が、少しおびえた感じで、白衣の女、ヴァレンティナ女史にアイヒマンが聞いた。
「彼の場合は、脳に近い神経の損傷も大きかったので。この被験者の場合は大丈夫ですよ」
「また、大暴れでもされて、施設を壊されるのはな。彼らときたら、内蔵の詰まった動力装甲(モータードレス)と一緒だからな」
カツカツと軍靴の音も高く、制服の男がこちらに近づきのぞき込んでくる。
(モータードレス?)
ケイスはにらみ付けようと顔に力をいれようとして失敗する。
「つないでみますか?」 看護婦が再度聞く。 「いいだろう。やってみたまえ」 怯えているのか、アイヒマンは少し声がうわずっていた。 ケイスには、それが自分に関わることとは思えないほど、彼らのやり取りは、モニターに見える遠くのできごと、イヤフォンから聞こえる空虚な声。 看護婦が再び前に着て、大きく膨らんだ胸元を見せつけるように、ケイスの頭にとりつく。 ケイスは、カシリと言う音を聞いた気がした。自分の頭蓋骨の一部が、はめ込まれたような感覚。
瞬間。
ビリビリと鳥肌が全身にたった。全身をくまなく包む悪寒が一気に脳へと押し上げてくる。 ケイスの体は弓なりに反って硬直し、すぐに腰をベッドに打ち付け、また持ち上がる。
制服の男が、数歩後ずさる。額に一気に汗をかいて動揺を隠せない。
その横で、白衣の女と、看護婦は無表情にケイスの状態を無表情に見つめていた。 ざわざわとした感覚が手足の先から脊椎をせりあがってくる。
体中をでかいムカデが数百匹も入り乱れるようだ。
ジャリジャリとした真っ黒な闇が、大きなスカートをどんどんと広げて被さってくる。
やめろと叫ぼうとして、言葉は声にならず、代わりにブーンと電子音。
頭が左右に振られ、何度もベッドに叩き付ける。首を伸ばし、動かない手が、頭蓋を外そうと必死に藻掻く。
「よし、もういいだろう。今日はもうやめてやれ」
アイヒマンが怯え声で言うのを、無視して、
「αメチルドパを追加しましょうか?」
看護婦がモニターを見ながら言った。
「五〇〇ミリ投与」
「了解」
ヴァレンティナと短く言葉を言い交わすと、看護婦がモニターを操作する。
首の辺りから脊椎に何か冷たいワイヤーが通る感覚。冷たい氷が背筋を通り抜けると、ケイスの動きはようやく緩やかに静かになった。 額の汗をぬぐいつつ、アイヒマンはその様子を眺めていた。
それでも、ケイスの頭がぐわんぐわんと回り続け、まるで、酷い二日酔いの朝に、メリーゴーランドに乗っているようだ。
ベッドの上に寝ていることが難しい感じがする。
その、酔いのような感覚がゆっくりと沈静化してきた。呼吸を沈めようと深呼吸を仕様とするが、肺や肋骨の感覚がない。
脊椎を損傷して、体がまったく動かないのか?体を動かせない失望感と、それに伴ってなんとも言えない恐怖が襲ってくる。
自分がどこにいるのか?どんな戦傷を負ったのか?どんな姿をしているのか?
しかし、最悪な事態は目の前にあった。
ずっとケイスの目の前のガラスに映る人形。
次第にはっきりとしてくる視界。
否定しようと試みるが、はっきりとしだした視覚。自分の目の代わりとして働いているその映像は、自分の姿を映している。
全身を特殊なギブスに覆われているのではないか?およそ、人とは思えない彫像のような姿。
それが自分の姿だと、現実味が増すほど、息が詰まる。こんな狭いギブスの中に閉じ込められていると思うと、さらに苦しくなった。
自分の姿を確かめようと、右手で体を起こそうとする。さっきとは違い右手が少し反応し持ち上がった。
呼吸を整えようとして、口から伸びるチューブが邪魔だと思う。
実際、自分が呼吸しているかどうか、それすらもケイスにはわからなかったが。
制服の男が、どうやら大丈夫そうなのを確認すると、つかつかと前に出てきて、ケイスの顔をのぞき込んだ。
ヒューヒューとふいごのようにまだ荒い呼吸を続けるケイスには、どうすることもできない。
「アイヒマンだ。階級は大佐、この脳味噌保護施設の責任者もかねている」
言いながら、握手を使用と手を出してくる。手が動かせたとしても、ケイスは握手なぞするかと思った。
「その体にもそのうち慣れるだろう。何せ君の肉体はあの攻撃の中で全身を失ってしまったからな」
ケイスはこの男が何を言っているのかわからない。全身を失ったって?
基地では、現役の軍人でもそれらの生体パーツを使って、戦闘で失った体を補ったり、あるいは、自ら強化している連中もいた。
砂漠や極寒冷地での戦闘に参加する前に、心肺機能や内蔵機能を、生身より優秀な人工の臓器と入れ替える移植手術を受ける者もいるという。
意識のないうちに、ある程度、神経強化プログラムによって、リハビリを進めることもできるため、戦闘で危険な目に遭うよりかは、"エンハンスメント"、すなわち、部分的に人工物と入れ替えることを選択する兵士も多いと聞く。
いつか自分もそんな日が来るとは思っていたが、これはナンセンスだ。しかも、適合が最も難しいとされる、全身の"オールリプレイスメント"、脳や一部の器官を除いてすべて人工物に“換装”されている。
ケイスにはまだ現実感がない。何かの冗談か、夢の続きかと思う。ただ、映像のような視界、時々雑音の入る音声、目の前のガラスに映る人形。
「慣れてもらわなくてはな。君には金がかかっている。西側のすべての生体技術、リプレイスメント技術、神経技術をつぎ込んでいる」
あいかわらず、物を見る目でアイヒマンが言った。
「その体の外装と神経は日本、内器官はアメリカ、各オプションはイギリスからの提供だ。君は西側(ウェスト)側、国家の持ち物なのだよ」
アイヒマンは握った拳でコツコツとケイスの胸を叩いた。およそ、人間の物とは思えない、硬質の胸板が響く。
「これから、地獄のリハビリに耐えてもらう。その後、私の極秘プロジェクトに参加してもらう」
そう言うと少し自慢たらしく胸を張った。リックならきっと嫌みの一つも言っただろうに。
相変わらず呼吸音しかしないケイスを見て、少し訝しむようにして見守る。
「奴は起きているのかね」
モニターを見つめる看護婦に振り返った。
「レイチェル?どうなの?」
モニターを凝視していた看護婦が、ヴァレンティナに振り返る。
「あ、はい、大丈夫です。脳波は出てますから、聞こえてるはずです」
「元の声のデータがなくてね。あなたの声帯はまだ調整中なのよ」
ケイスの方を向いて、ヴァレンティナが言った。
アイヒマンが目顔で促し、ヴァレンティナと共に出て行く。レイチェルと呼ばれた看護婦も続くが、出口で振り返るとケイスの脇に走り寄った。
「ごめんなさい。けれど、あなたが生きていて本当に良かったです」
舌足らずな声で言うと、ペコリと頭をさげて、そのまま走って行く。
ベッドに仰向けに寝た人形が、じっとこちらを見つめていた。
それが、自分の姿だとどうしても信じられない。
起き上がって確かめたいが、体はまったく言うことを聞かなかった。 皮膚の感覚、周囲の音すら遠く、遙か彼方から届くよう。
視覚は狭く、映像は昔のテープ映像を見ているよう。
茶褐色の石膏で固められベッドに寝かされている。
ガラスに映った自分の姿を見つめる。それが質の悪い冗談だと思えるまで。
きっと、悪い夢に違いないと思う。一眠りしたら、基地のベッドで冷や汗をかいて寝ているに違いない。
人口の体によって生かされたたケイスの脳に、突然、ナオミの最後の姿が浮かんだ。
今まで見たことのない絶望を浮かべた顔。
流れる血が痛々しく、眼は涙で濡れている。
そして、ラジオからの流れるシャンソンと、暖かな日差しと、ホットケーキ。
涙腺は装備外品。いや、目頭は確かに熱く、涙は頬を確かに伝う。
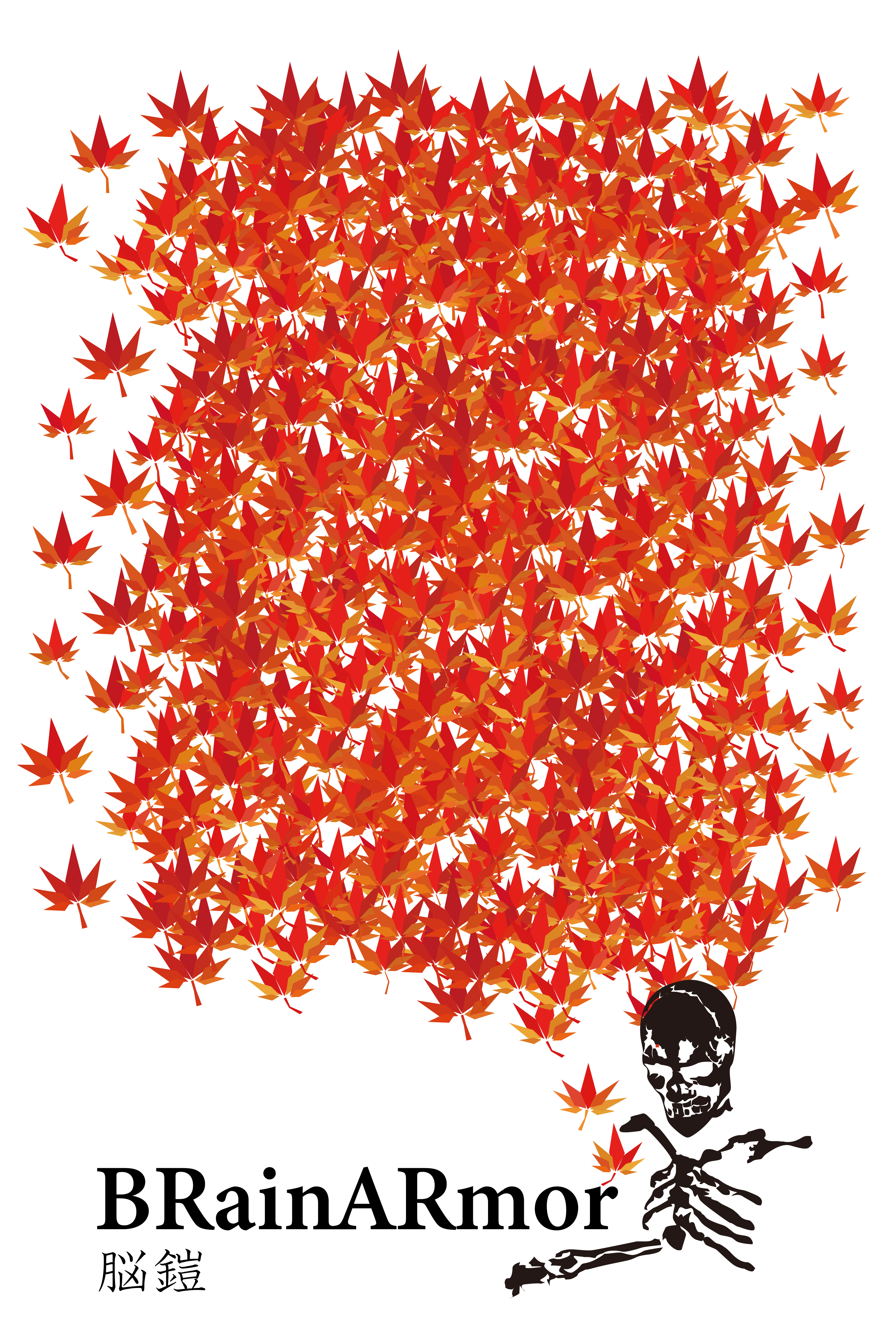
投稿者の人気記事




「もののけ姫」着想の地であり魑魅魍魎の最後の砦 知られざる京都洛北・志明院へ

【個人メディアとは?】個人メディアの種類と特徴を徹底解説

装甲騎兵ボトムズ 塩山キリコと谷口キリコの違い

初投稿です🌱|発売まで@1か月|ワクワクがとまらないFF14パッチ6.0

解剖学から考えるグラップラー刃牙の必殺技:三半規管破壊

ジャンプ+掲載の画像使っていいか念のため聞いてみた件と電車で読みたい漫画4選

かわいいキャラクターの作り方

ファイブスター物語のロボットがゴティックメードに変わって驚いた

まんが日本昔ばなしのこわい話

iOS15 配信開始!!

甘露寺蜜璃ちゃんのカラダのヒミツ【”筋肉密度が常人の8倍”を真面目に考える】
