

自意識の総体(いわゆる自己)は他者との間に生成される一時的なもので、その都度変わっていくのだと思う。常に確固たる自己が体の中に存在し続けていて、それが経験により変化する、ということではないような気がする。もちろん毎回一から生成されるわけではないだろう。他者と対峙するのは(基本的には)体であり、体は場所という制約により環境の影響を受け、それぞれ独自の経験を積みながら変化していく。そのユニークな土台の上に、土台を参照しつつ、他者と会う度に新たな自己を生成させているのではなかろうか。なかろうか、というよりそう思いたい程に私の自意識は不安定だ。自己同一性は「自分はこういうもの」という思い込みをどう保つかということなので、体ほど限定されていない。比較的いつも同じように思えるのは体が持つ固有性の方で、固有の体での経験の積み重ねによる偏り、すなわち個性の方である。個性自体も経験と共に変化し得るが、自意識ほど慌ただしく変わるものではない。他者と向き合う時、自分がどう見られているのか、自分で自分をどう思っているのかという意識が前面に出てくる。
そう考えると哲学とは最初から社会的なものである。もし仮に他者がいなくなったら自己は生成されないのだとしたら、如何に生きるかという問いの主語が消えてしまう(『ヴィトゲンシュタインの愛人』は自分以外に人がいなくなった世界で生きる自己同一性のない人物による、一人語りの小説である)。認知症などで自分が誰かわからなくなるというのは、自己生成の機能が働かなくなった状態なのではないか。記憶や知覚した情報を読み取り、自己を再現したり新たに生成する機能については、常に他者の認識の仕方や認識する意欲が鍵のような気がする。他者との出会いの捉え方である。
自己が生成される際に向き合う他者は人に限らず、関係を結べる対象は体の外に在る全てである。対象に対する知識を得た後は、自分との関連性を意識することで人以外のもの(多分何らかの現象すら)と自分との仮初の関係が頭の中に結ばれる。家にあるぬいぐるみ達もそうで、最初は自分が動かす為に命あるものとみなしたものだった。それに自分が触れて動かす経験を積むにつれて、自然と自分の中に動かす対象自身の知性や人格が生じてきた。人格を意識したら、自分にとっては他者となる。ということは、人にはどんなものでも命あるものと見なす能力があると言える。見て、接することで命を感じるようになる。それは感じた人にとっての命でしかないかもしれないが、同じような体験をしている人とは共有できる命である。他者として認識できる対象の範囲は、世界そのものまで拡張されそうな気がしてくる。範囲が広くなると自意識が生成される(と少なくとも自分は思っている)関係も増えていき、生成される自己もより多面的になっていく(と自分では思える)。人以外との関係において生じる自己は、人との関係において生じる自己にも影響するだろう。他者との関係は「どんな自己が生成する/されるか」に左右される。互いに好ましいものであればよいが、何か不安にさせたり見たくないものなら忌避し合うだろう。自分が他者にどんな自己を生じさせる存在なのかは観察してみないとわからない。自意識は観察の度に上書きされるにおいのようなものである。
なお他者に向けて語るとは、語り部としての自分を作ることでもある。語りに限らず表現する時にはそうなのかもしれないが「こう思われたい自分」が浮かび上がってきてしまう。私の場合は、わかってないと思われたくないというのがあって、それは社会常識的なことの多くが腑に落ちず、他者と当たり前を共有し難いのが原因だ。他者とリアルタイムでは共有できなくても、後で語ることでそういうことだったのか、とか、わかってないわけじゃないんだな、とか、思ってもらいたいのだ。私が自覚している自分の特徴は「他者から信頼されない」ということなので、つい信頼まではいかなくても、せめて安心してもらいたいという気持ちが湧いてしまう。そうでないと他者に私の存在を否定され、排除されかねないと恐怖しているのかもしれない。ともかくそういう気持ちから語った結果、ますますわからない、と思われるのかもしれないが、面倒くさいから放っておこう、と思われるのは搾取回避にも繋がるので、自由という観点からは割と成功である。さみしいけれど。
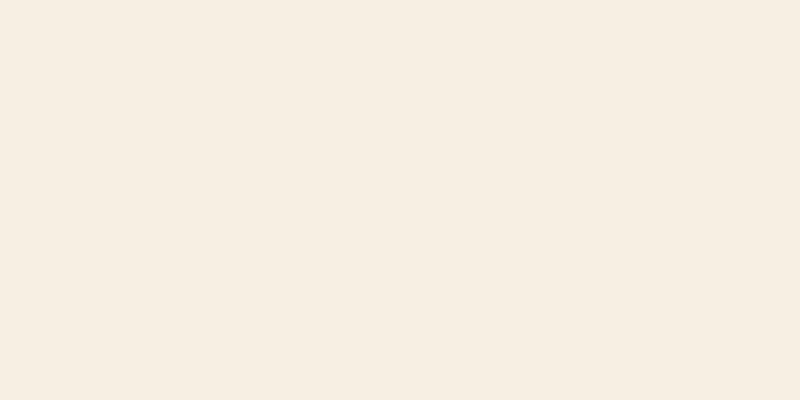

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

SASUKEオーディションに出た時の話

オランダ人が語る大麻大国のオランダ

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

バターをつくってみた

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

無料案内所という職業

機械学習を体験してみよう!(難易度低)


