

自分がいつか死ぬことに気付いた時のことは覚えていない。きっと衝撃だったと思うが、生まれた時代・場所・外見などの「自分が自分であること」に限定されている内容は好きでも嫌いでもなかったし、とにかく自分の行動を縛るものを嫌っていたので、まあいいかと思うところも少しはあったのではないだろうか。
子供は知識も経験も少ないので、あらゆることを自分なりに考える。欲しいものや不思議に思うこと、思い通りにならないことなど、いちいち全て考える。考える時に足掛かりにするのは、やはり経験である。経験が増えると考えなくなるのは、これはこうだ、こういう場合はこうするという仮定を行動に移すことを繰り返した結果、大丈夫だったものが「正解」として定着していくからだと思う。考えなくてもそれを選ぶようになり、例外が起こるまで省みられなくなる。その足掛かりは偶々そうだっただけであり、建築現場の足場のようなものに過ぎないということを忘れる。
子供の頃は年寄りが何故新しいことに興味を持たないのか不思議だった。自分にとって未経験なことが物理的にも倫理的にも明らかに可能な時、それをやりたいという気持ちに抗うのは難しい。それなのに年寄りは外に目を向けようとせず、子供の目には同じに見える事を繰り返しているだけに見えた。
今は何となくわかるような気がする。良いものも嫌なものも一通り経験したつもりなので、大体わかってるような気分。そして大概のことはもう自分とは関係ないような気分。体が衰え、失敗や実現可能性の低さを想像して行動を起こさなくなる。欲望が満たされること自体が次の欲望を刺激するものなので、欲望を満たそうとしなくなると欲望を抱かないことにも慣れてくる。
暖房の効いた部屋で眠くて仕方ない時など、子供の頃の真夏の風景を思い出す。母方の墓は山の中にあり、墓地一帯には木が無く、てんでばらばらの方を向いて建つ墓石を直射日光が容赦なく照らしていた。朽ちている途中の墓石に供えられた瑞々しいおはぎ。墓参りが終わり、寺の地獄絵を独りで見た後、墓石同様に朽ちかけている家に帰る。井戸水で冷やした美味すぎるスイカやアイスを食べながら感じていたのは、どうしたって自分の人生がこれらの死と切り離せないという諦めだった気がする。ちなみにその家には幽霊が出るという話も聞いた。出てくると言われたのがひい婆さんだったか大叔母さんだったか、仏壇の上に飾られた写真の顔も覚えていないが、昼間でも暗い室内の、見えないものが息をひそめているような雰囲気は覚えている。
老いて死ぬのは仕方がないということ、これまで死んでいった人たちのように、自分も当然死んでいくということ。これはあらゆる行動の根底にある縦糸である。生まれてから死ぬまでのことが縦糸で、現在共に生きてる人達とのことが横糸である。頭の中でぴんと引っ張ると、物事を認識する際に使える軸にもなる。
例えば、体臭は縦糸のことである。30代後半になり、自分から親父や叔父さんの懐かしいにおいがしてくる。二人とも故人だが、耳や鼻や首の後ろのにおいが彼らが40代の頃のにおいに似ている。意識すると老廃物のにおいは、体だけでなく家の内外に無数に染み付いている。床屋や銭湯のにおい、病院のにおい、居間に置かれた死体のにおい。全部縦糸で繋がっている。
例えば、建前は横糸のことである。人は社会において色んな顔(家族の一員としての顔、仕事の顔、独りでいる時の顔)を持っているように、自分が属している集団やカテゴリーも状況の変化に応じて「いずれ入るところ」「入り得るところ」「入り得ないところの手前」などを行き来しつつ、その場に応じた顔を使い分けているのだと思う。
いつから大人でいつから老人なのか、どこまでが自分でどこからが他人なのか、物理的な身体の状態なら分かりやすいが、いわゆる内面や価値観は曖昧なので、言語化しておくと認識し易くはなる。真面目な話、価値観や考え方などは、現在ある集団の中で最適だと思われていても、現実の変化に対応して更新されないままでいると将来、必ず子供たちに不利益を強制する障害となる。生き物や環境が変化し続けるように、カテゴリーの境界も常に動いている。言語化して現在の境界を見定めようとしたり、境界から両側を観察していたいと思う。
他者の物言いにムカつくのは横糸のことである。社会の在り方について価値観が固まっている人が、上から目線で話す感じはなんなんだろう。固まっていることに自覚的でない感じ。自覚してるが「それが私」として開き直ってる感じ。同じ価値観で支持されているからには、動揺してはいけないと思っているかのような感じ。動揺してみせるには、自分のタイミングで自分発信でなければいけないと思ってる感じ。が無意識に滲み出ている。
他者を傷付けてはいけないというルールは、基本的には誰も破ろうとはしないと思う。だが現実は常に変化しているし、価値観にも種類や幅がある。価値観とは総合的なものだろうが、何をよしとするのかは個別に、項目別に無数に存在し、しかも経験によって変化し続けている。現実に向き合う為の足場にするような価値観は、自分の判断や選択で固められたものだ。その人固有の経験から成っているし、大事にするのは構わない。個別に快感や未知の刺激を求めるのはよいだろう。でもせっかく固めた足場であっても、社会に関わる情報が更新されず、過去に固まった時のままであるのは、本来不安で仕方ないはずだと思う。
知らない内にその気はなくとも、他者を傷付けているかもしれない。その不安による揺れが物言いに全く感じられない時、ムカつく。ムカつくといえば個人的にはクチャラーが筆頭に挙げられるが、私はどうも「気付いてない状態」が気に入らないようだ。咀嚼音のようなこと以外でも、自分の常識や価値観など、大事にしてることこそ現在に照らし合わせて問い直していかなければならないでしょうにと思う。そして他者の批判「それ、古いですよ」「現状に即してないですよ」が聞こえる状態が保てるように、気を付けていかなければならないでしょうよと。それをさぼると過去に生き始めることになり、現在を生で感じられなくなるのだろう。老いである。
基本的には自分の感情も他者の感情もよくわからないが、コミュニケーションの中で、言葉の持つ影響力に震えることがある。父が死んだ時は、母と兄が看取った。私はその少し前に「またね」と言って帰ったので、死に目には会えなかった。聞くところによると、父は死ぬ直前のまどろみから醒めた時、とても動揺していたらしい。兄曰くおびえているようだったというが、何を見たのだろう。兄は優しく「大丈夫だから」と繰り返し言い聞かせ、父は目を閉じ死んだ。
死んだ後で父がどういう人だったのか知りたくて、facebookアカウントにまとめてみようかと思ったことがあった。父に関する情報を全てそこに集約すれば、教師をしていた父のことだ、公表することで新しい情報が追加されることもあるかもしれない。それでわかることもあるだろう。でも結局はしなかった。生きている時の父自身に直接向き合うことがなかった以上、決して知る事はできないのだと思い直した。私がそう思ったのは、父との間で交わされた言葉の為だ。
どんな言葉が父との関係に影響を与えたのかといえば、自分にとっては「思い付きで行動するな」という言葉がそうだった。子供の頃はとにかくその言葉でよく叱られた。「危ないから注意深くなれ」「傲慢になってはいけない」単に「手を焼かせるな」とかいう意味合いに過ぎなかったと思うが、私は「在るがままにいるな」という不自由さを課す命令と受け取り反感を持ち、距離を置いたのである。
別に「生まれてこなければよかったのに」などと言われた訳ではないが「生まれてきてくれてよかった」と言われたこともない。難産で母子共に危険状態だった時「俺は母体を優先しろと言ったんだ」とは言われた。酔っぱらっている時「お前は計画的に作ったんだからな」とは言われた。「よかったと思っている」ということは、自分への態度や行動では表してくれていたと思う。だが親子関係という建前とは別の部分で、言葉によるコミュニケーションがなかった。
父にとっては「少なくともお父さんではないね」という言葉がそうだったと思う。これは「お前は誰か尊敬してる人とかいるのか」という問いかけの答である。ひどい。自分にとって他者は大差なかったので、とっさに挙げられるような人はいなかった。それを咎められた気がしたのと、反抗心からそう答えたのだろう。言葉は前後の文脈で意図が変わってくるものだが、少なくともこの言葉には拒絶しか感じられない。向こうからしたらせっかくこちらを理解しようとしてくれたのに、拒絶されたことになる。後にこのやりとりについて話すこともなかった。やりとりされた瞬間に意図が通じるとは限らないが、言葉は意味が明確な分だけ影響が大きい。結局は互いに素直ではなかったので「面倒くせえこいつ」と疎遠になったのだろう。
「思い付きで行動する」というのは、哲学の実践のような感じがする。もし哲学が何の役に立つのかと訊かれたら、常識として考えなくなってしまったものごと、足場について考え直すのに役に立つと答えたい。形而上的な概念などに限らず、抽象的な考えを身近な具体に当てはめて行動してみることで、固定化していた見方が壊れたり、物差しが増えたりするのではないだろうかと思う。少なくとも自分にとっての「生きているってどういうことなのか」が前よりは腑に落ちる気がする。
だが考え直したりしたところで、それを言語化して他者とやりとりしないと意味がない。言葉が通じる相手とは、言葉によるやりとりもできる限りしていかないと、と父との経験から思う。面倒くさくても、いずれそれはできなくなってしまう。ちなみに意味がない、というのは共感や理解を求めることではない。自分の外側に違う人や違う世界の存在を言語を通して「知る」ということである。言語に限らず表現は、他者に「知って」もらえさえすればよいのだと思う。
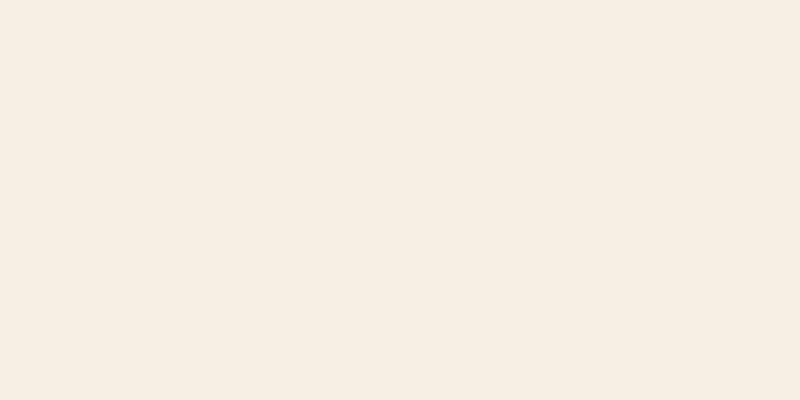

Bitcoinの価値の源泉は、PoWによる電気代ではなくて"競争原理"だった。

【初心者向け】Splinterlandsの遊び方【BCG】

警察官が一人で戦ったらどのくらいの強さなの?『柔道編』 【元警察官が本音で回答】

京都のきーひん、神戸のこーへん

海外企業と契約するフリーランス広報になった経緯をセルフインタビューで明かす!

梅雨の京都八瀬・瑠璃光院はしっとり濃い新緑の世界

テレビ番組で登録商標が「言えない」のか考察してみる

無料案内所という職業

17万円のPCでTwitterやってるのはもったいないのでETHマイニングを始めた話

ジョークコインとして出発したDogecoin(ドージコイン)の誕生から現在まで。注目される非証券性🐶

NFT解体新書・デジタルデータをNFTで販売するときのすべて【実証実験・共有レポート】


